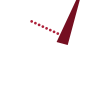家住 利男 「M.181001」
板ガラス、着剤
近年において、技法や表現の多様な展開をみせる「現代ガラスアート」。本展では、作家8名による8通りのクリエイションから、ガラス素材の表現の可能性を探ります。ガラスは、私たちの視覚や感覚に何を問い、何を触発させるでしょうか。
透明で無機質なマテリアル、ガラス。暮らしの道具として、また、窓ガラスや建築資材として、私たちの生活に馴染み深い素材です。その一方でガラスは、1960年代にアメリカで起こった“スタジオグラスムーブメント”(※1)により、アートにおける創造の媒体として広く定着し、工業・工芸の域を超えて進化を続けています。
ガラス技法には、高温で溶かし加工する“ホットワーク” (※2)、電気炉(キルン)の中で熱し形成する“キルンワーク” (※3)、固い表面に直彫りや彩色を施す“コールドワーク” (※4)の3大分類があります。 無機質なガラスに様々な技法を駆使することで作家のイメージを授けられた作品は、精神性を宿し、佇まいに光を包有することで有機的な表情さえ感じさせます。光の屈折や反射、表面の揺らぎ、ざらつき、研磨された質感、それらは観る者の多様な視野や心情を映し出すでしょう。
ガラス素材の潜在力に問いかける8名の作家たち。8通りの具象・抽象の表現が、現代ガラスアートが孕む可能性の閃きを放ちます。
【出展作家】
家住利男、扇田克也、小田橋昌代、加藤尚子、小池志麻、小牟禮尊人、張慶南、所志帆
(※1)ハーヴェイ・リトルトンを中心とした、ガラスの自由なアート表現を目指す芸術運動。作家のガラス炉所有を推奨し、工場に頼らない創作活動を目的とした。
(※2)約1000℃以上の高温で水飴のように熔けたガラスを加工する技法。
(※3)500℃〜1000℃に熔けたガラスの状態変化を利用し、くっつける、捻じ曲げるなどして形成する技法。
(※4)常温のガラスの表面に加工を施す技法。切子やステンドグラスはこれにあたる。