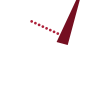©Angelo Trani
この魅惑の夜、星空の下で、ピエロ、イニャツィオ、ジャンルカと共に過ごし、彼らを指揮することができるのはとても幸せだ。フィレンツェのような美しい街で!
多くの人々がクラシック音楽を聴くようになったきっかけは、ルチアーノ、ホセ、そして私が歌った《3大テノール》コンサートだった。この3人の青年たちは、私たちの思いを継いでくれている。──プラシド・ドミンゴ

世界中で大人気の、イタリアの若きオペラ歌手3人による男声ヴォーカル・ユニット 《イル・ヴォーロ》 が、“3大テノール”の一人プラシド・ドミンゴと共演した特別なコンサートは、フィレンツェで最も美しい場所の一つであるサンタ・クローチェ聖堂前の広場に、2万人の大観衆を集めて開催された。
コンサートは、ドミンゴ、ホセ・カレーラス、ルチアーノ・パヴァロッティ、3人の世界的なテノール歌手による20世紀最大のクラシック音楽プロジェクト“3大テノール”に捧げられ、演奏曲は全て3大テノールのレパートリーから選ばれた。特別ゲストのプラシド・ドミンゴは指揮者として、また歌手としてもイル・ヴォーロと共演。フィレンツェの星空の下、圧巻の歌唱力と美しいハーモニーに酔い、会場はやがて熱狂の渦に!
《演奏曲》
・「運命の力」序曲(ヴェルディ)
・誰も寝てはならぬ(プッチーニ:歌劇「トゥーランドット」より)
・グラナダ(ララ)
・マッティナータ(レオンカヴァッロ)
・人知れぬ涙(ドニゼッティ)
・ラ・ダンツァ(ロッシーニ)
・星は光りぬ(プッチーニ:歌劇「トスカ」より)
・帰れソレントへ(デ・クルティス)
・「マノン・レスコー」間奏曲(プッチーニ)
・カタリ・カタリ(カルディッロ)
・太陽の土地(ダンニバーレ)
・マリア(バーンスタイン:「ウェスト・サイド・ストーリー」より)
・マイ・ウェイ(ルボー、フランソワ/P.アンカ作詞)
・トゥナイト(バーンスタイン:「ウェスト・サイド・ストーリー」より)
・恋する兵士(カンニオ)
・マンマ(ビクシオ)
・「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲(マスカーニ)
・シェリト・リンド(メキシコ民謡)
・アランフェス(ロドリーゴ)
・そんなことはあり得ない(ソロサーバル:サルスエラ「港の酒場女」より)
・オ・ソレ・ミオ(ディ・カプア)
・忘れな草(デ・クルティス) [with プラシド・ドミンゴ]
・乾杯の歌(ヴェルディ:歌劇「椿姫」より)
・誰も寝てはならぬ [アンコール]

《イル・ヴォーロ (IL VOLO)》
●羽生結弦、プルシェンコが楽曲使用!
●ワールドツアー全てソールドアウト!
●全米クラシック・チャート1位!
イル・ヴォーロは3人の若きイタリア人男性オペラ歌手、ジャンルカ・ジノーブレ、イニャツィオ・ボスケット、ピエロ・バローネによるヴォーカル・ユニットで、2009年、当時14~15才だった3人が、それぞれソロ歌手として人気オーディション番組に出演し、共演したことがきっかけとなって結成された。圧巻の歌唱力と、それぞれの特徴を生かした美しいハーモニーで、オペラからポップスまで幅広い楽曲を歌い、3大テノールを継ぐ新世代のスリー・テナーズとして世界的な人気を獲得している。2017年に初来日。本年4月には4枚目のアルバム「ムジカ」をリリース。5月に再来日公演を行う。
フィギュアスケーターによる楽曲使用も有名で、羽生結弦が2016~17年のシーズンエキシビジョンで「星降る夜(ノッテ・ステラータ)」を使用。エフゲニー・プルシェンコが「グランデ アモーレ」を使用した他、多くのスケーターがイル・ヴォーロの曲を使用している。
《プラシド・ドミンゴ (Plácido Domingo)》
1941年、スペインのマドリード生まれ。両親はスペイン版オペレッタとでもいうべき“サルスエラ”の歌手だった。8歳の時にメキシコに移住、メキシコシティの国立音楽院で学び、59年メキシコ国立歌劇場でデビュー。65年にニューヨーク・シティ・オペラと契約。67年にはウィーン国立歌劇場にデビューし、またたく間に世界中の有名歌劇場を席巻して名声を確立した。
豊かなバリトンの音域も兼ね備えた特筆すべき多様性をもつテノールであり、極めて広汎な演目をレパートリーとしている。80年代にはその素晴らしい演技力で数々のオペラ映画にも主演。90年代は、ルチアーノ・パヴァロッティ、ホセ・カレーラスと共に“3大テノール”としても活動し、世界的な人気を得た。
1985年のメキシコ大地震で親しい人々を喪う経験をしているドミンゴは、2011年の東日本大震災の直後、原発事故の影響で海外アーティストの来日中止が相次ぐなか、来日公演を敢行。アンコールで観客と共に日本語で歌った《ふるさと》は大きな感動を呼んだ。
最近ではバリトン・ロールを歌うことも多く、新たな境地を切り開いているほか、本作のように指揮者として、またオペラハウスの芸術監督としても八面六臂の活躍を見せ、その音楽活動は豊かな結実の時を迎えている。