Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第26回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

中村文則 著
『私の消滅』
(2016年6月 文藝春秋刊)
| 選 考 | 亀山郁夫 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |
| 授賞式 | 2016年10月13日(木) 於:Bunkamura
当日開催された授賞式の模様を動画でご覧いただけます。 レポート記事はこちらでお読みいただけます。 |
受賞者プロフィール

© Kenta Yoshizawa
中村文則(なかむら ふみのり)
1977年、愛知県生まれ。福島大学卒業。2002年、『銃』で新潮新人賞を受賞しデビュー。2004年、『遮光』で野間文芸新人賞、2005年、『土の中の子供』で芥川賞、2010年、『掏摸 スリ』で大江健三郎賞を受賞。『掏摸 スリ』の英訳が米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの2012年年間ベスト10小説、米アマゾンの月間ベスト10小説に選ばれる。2014年、ノワール小説に貢献した作家に贈られる米文学賞デイビッド・グディス賞を日本人で初めて受賞。作品は世界各国で翻訳され、支持を集めつづけている。他の著書に『何もかも憂鬱な夜に』『去年の冬、きみと別れ』『教団X』などがある。

亀山郁夫(かめやま いくお)
1949年、栃木県生まれ。
名古屋外国語大学学長。ロシア文学者。東京外国語大学卒業、東京大学大学院博士課程単位取得退学。前東京外国語大学学長。
2002年に『磔のロシア―スターリンと芸術家たち』で大佛次郎賞、2007年に翻訳『カラマーゾフの兄弟』で毎日出版文化賞特別賞、プーシキン賞を受賞。2012年には『謎解き「悪霊」』で読売文学賞受賞。ドストエフスキーの新訳では、他に『罪と罰』、『悪霊』があり、現在は『白痴』の翻訳に取り組んでいる。2015年11月、自身初の小説作品『新カラマーゾフの兄弟』を上梓。
受賞の言葉
これから向かう先へ / 受賞者 中村文則
小説を書く度に、新しいことに挑戦したい、と思っています。
自分の核はそのままに、何か新しい要素を一つ加えていく。もう十一年前になりますが、芥川賞を頂いて以降、ずっとそのことを自分に課していました。
理由は当然、作家としてもっと成長したいからなのですが、僕の読者さんはずっと読み続けてくれている人が多いので、そういう人達に応えたい、という思いもあります。「また同じか」と思われないように。「核は変わっていない。でも今回はこういう驚きがある」。そう思ってもらえるのが理想と感じています。
『私の消滅』では、ノンフィクションを取り入れることに挑戦しました。元々、ノンフィクションを書きたい、書くなら宮崎勤元死刑囚か前上博元死刑囚、もしくは山地悠紀夫元死刑囚を、と思っていました。ですが、どの出版社からも依頼は長編小説で、様々な出版社をお待たせしてしまっている状況でもあり、「ノンフィクションが書きたい」とは言えず、いつになったら書けるのだろう、と思っているところでした。そしてふと「小説に混ぜてみたらどうだろう?」と気づき、試みてみたら、あくまで自分では、ということですが、とてもしっくりくることになりました。結果的に、そのことが今回の挑戦となりました。
考えてみれば、小説の可能性は無限です。色々なことができる。わざわざノンフィクションを書かなくても、それは小説に組み込むことができる。そのことに気づき、今は、ノンフィクションを書きたいという願望はなくなりました。
なぜ宮崎勤元死刑囚だったかというと、理由は色々あるのですが、一番は、彼が「現代」の犯罪者の中で、最も複雑な内面を持っていると常々感じていたからです。彼の中に、「現代」の犯罪の核があるのではないかと。彼の内面の奥に入り込む作業をしている途中、自分自身が、小説の中に引きずり込まれるような印象を受けました。こういった経験は、『教団X』という小説の「沢渡の過去」のパートを書いていた時以来のようにも思います。そのこともあってか、小説そのものも、これまで僕が書けなかった領域まで――特にプロット――行くことができたように思います。
ロシア文学者であり翻訳家、そして小説家でもある亀山さんをずっと尊敬していました。その方から今回の賞を頂けたのは大変光栄なことでした。僕は亀山さんにお会いすると背後にドストエフスキーを感じるのですが、まるでドストエフスキーからも賞を頂けたような、そんな感覚まで抱くほど内面が今揺さぶられています。
僕が文学に目覚めたきっかけは太宰治の小説を読んだことですが、この原稿を書いている今、僕は太宰が自殺した、ちょうどその年齢に来ています。太宰は彼の誕生日の数日前に亡くなったのですが、僕は自分の誕生日の数日前に、この賞を頂く知らせを受けることになりました。
僕の人生において、ファースト・インパクトはその太宰治で、セカンド・インパクトがドストエフスキーでした。まるでその僕の人生の流れが、今回の受賞の中に凝縮されているように感じます。太宰が亡くなった年齢の誕生日を越え、太宰治からドストエフスキーへというような。人生を無理やり終わらせた太宰治ではなく、最後まで小説を書き続けたドストエフスキーの精神へ、僕の作家生活がこれから向かうというような。
何か、今回のことに周辺の意味をつけ過ぎているのかもしれません。でも、こんなことを思うほど、今回の受賞は僕にとって大きなことでした。
これまで応援してくださった、全ての人に感謝します。ありがとうございました。今後も書き続けていきます。
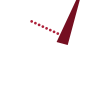















選評
「『私』をめぐる限りない謎とその予言的ヴィジョンの提示」/ 選考委員 亀山郁夫
第26回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を中村文則氏の『私の消滅』に贈る。
中村文則のファン、と公言できるほど私自身若くもなく、最近の彼の作品にはいくつか頷けない点もあるが、作家としての彼の類まれな資質と、この小説のもつ「先進性」に敬意を表して最終候補作とすることにした。
思い返してみると、私が彼の小説に文句なしの賛嘆の思いを抱くことができたのは、初期の『銃』『土の中の子供』、さらに少し間を置いて書かれた『掏摸 スリ』の3作品である。それらの作品でとくに抜きん出ていると感じたのは、みずからが描こうとする対象への憑依力である。デビュー以来、彼のリアリズムは、他の作家より一次元高いレベルにあるという感想を持ち続けてきた。
もっとも、本受賞作『私の消滅』を最初に手にしたときの印象は、かなり複雑だった。一見して露悪的ともとれる電文調や、散見されるい抜き言葉、ら抜き言葉に何かしら座りの悪さを覚えた。しかし、そうした負の印象に耐え、最後までページを繰ることができたのは、ひとえに作品のタイトルが示唆する世界への期待感である。事実、「手記3」に入ってから印象は大きく変化し、本筋からやや独立して語られる宮崎勤をめぐる考察では、彼の憑依力の何たるかを見せつけられる思いがした。
物語は、呪わしい記憶に苦しむ恋人の診療にあたった若い心療内科医による復讐の道行きを描く。「洗脳」ないし「記憶の移植」がそのための手段となる。使用されるモチーフ自体、フィリップ・K・ディックの先例もあってとくに目新しくはないが、作者独自のサドマゾヒズム的世界観との結びつきや、構造的に恐ろしく複雑な仕掛けが、独自の境地を生んでいる。抽象的な言い方になるが、従来の作品でつねに不吉な低音をかき立ててきた《絶対悪》の神的シンボルとマゾヒズム人間を結ぶ縦の回路が、この作品では横倒しにされて、加害者と被害者いや善悪の関係がウロボロスの輪のようにからまりあう構図である。「告白」「手記」「手紙」「メール」などの仕掛けをとおして、書き手自身の「消滅」というメタ小説的な趣向が凝らされている点も面白かった。
では、この小説が提示する世界観――固有の人間存在はもはやなく、人間とは身体という器を転々とする意識存在にすぎない――の「独創性」はどこにあるのか。ごく私的な感想だが、私はそこに、筒井康隆『モナドの領域』、松浦寿輝『BB/PP』などが拓く超越文学ないしAI文学の新しい実験に連なるものを感じとった。中村が、この小説の彼方に見ているのは、一方では輪廻転生のニヒリズムであり、他方では「シンギュラリティ(特異点)」後の人間世界である。前者における「私」は、限りなくゼロをめざして昇華され、後者における「私」は、ある究極の「一」をめざしつつ幾何級数的に増殖を続ける。逆説的な言い方になるが、それはまさにAI時代における「私」の「消滅」のプロセスをなぞるものだ。
『私の消滅』を手にした夜、「手記3」まで読み進めたところで私は眠りに就いた。物語の世界がたちまち夢の世界に溶けだし、私はつかのまの不快な眠りから覚めた。その瞬間、自分があたかも「洗脳」されていたような錯覚に陥った。
一年間にわたる選考プロセスで、「私」の内に住み着いた3人の批評家が、3世代にまたがる3作品をめぐって議論を戦わせた。決め手となったのは、ドゥマゴ賞の趣旨に触れた次の言葉である。
「more off-beat and less conventional」――。
遅れて現れた4人目の批評家は、今の中村と同じ30代、「オフビート」にして非「因習的」な未来派の研究に勤しんだ過去があった。彼は、懐かしげにその時代を思い返しつつ3人の批評家の説得にかかり、ついでながら『私の消滅』を手にした夜の悪夢について語った。モノクロームの線画で描かれた表紙カバーからふいに堕天使が顔を出し、帯に書かれたコピーを濁った声で朗読しはじめたというのだ。
「このページをめくれば、あなたはこれまでの人生の全てを失うかもしれない」
思うに、中村文則の文学を愛する読者とは、想像力の冥界に降り立つことを恐れない、傷だらけの「子供」たちである。