Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第30回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

石川宗生 著
『ホテル・アルカディア』
(2020年3月 集英社刊)
| 選 考 | 野矢茂樹 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円 |
| 授賞式 | 2020年10月26日(月)於:Bunkamura
当日開催された授賞式の模様を動画でご覧いただけます。 受賞記念対談の動画はこちらからご覧いただけます。 |
受賞者プロフィール

© 松林寛太
石川宗生(いしかわむねお)
1984年、千葉県生まれ。オハイオ・ウェスリアン大学天体物理学部卒業。
約3年間の世界放浪、メキシコ、グアテマラでのスペイン語留学などを経て、翻訳者として活動。
2016年、「吉田同名」で第7回創元SF短編賞を受賞。2018年、受賞作を含む短編集『半分世界』を刊行。

野矢茂樹(のやしげき)
1954年、東京都生まれ。1985年、東京大学大学院博士課程修了。東京大学大学院教授などを経て、現在、立正大学文学部哲学科教授。専攻は哲学。
著書に『哲学の謎』『無限論の教室』『入門! 論理学』『ここにないもの』『はじめて考えるときのように』『心と他者』『哲学・航海日誌』『語りえぬものを語る』『心という難問』『大森荘蔵-哲学の見本-』『論理哲学論考を読む』『新版 論理トレーニング』『哲学な日々』『増補版 大人のための国語ゼミ』『そっとページをめくる』『まったくゼロからの論理学』など多数。
受賞の言葉
どこまでも無責任で / 受賞者 石川宗生
フランツ・カフカから始まった不条理文学は、近年、マジックリアリズムの再興の影響を受け、ポップカルチャーまでをも雑食的に呑み込んで、エンタメやら純文学やらSFにまでその枝葉を押し広げている。ボーイフレンドがヒヒや亀に退化していく物語(エイミー・ベンダー『思い出す人』)など、日常に”奇”のエッセンスを一、二滴垂らしたようなものもあれば、登場人物たちが著者に戦争を仕掛ける(サルバドール・プラセンシア『紙の民』)など、メタフィクション要素を最大限に昇華させたものまであり、それがいわば現代文学を、本流とは言わずとも支流のひとつを形成している。
と、いうような思い込みにも近い認識をぼくは勝手に抱いており、『ホテル・アルカディア』においても同様の流れに乗って筆を執ったつもりだったのだが、このたびの野矢茂樹さんの選評、特に「なんだこりゃ」との感想を受けて、爆笑しつつもふっと冷静になってしまった。時を置いて読み返してみれば、なるほどこれはたしかになんだこりゃだったから。
ためしに書店を巡ってみてもこの手のイカレタ小説はとんと見かけない。ことさら日本文学の棚にはなく、『ホテル・アルカディア』がほかのまともな小説群に窮屈そうに挟まれている様はやや場違い感すらあった。
野矢さんは本書の選評にあたって妄想の暴走という言葉を使われているが、構想段階からしてその兆しはあった。はじまりは担当編集さんに文芸誌での掌編の連載を依頼されたことだった。その際に、本にするときは枠物語にしようと思い立ち、さっそく代表格たる『デカメロン』、『千夜一夜物語』、『カンタベリー物語』を読み込んだ。
しかし読み終わるや、今度は単なる枠物語に終わらせるのは勿体ないのではないかとの思いが脳裏をよぎり、枠物語の体裁は残しつつもエッシャーのだまし絵みたいに視点次第で物語の見え方が変わる、始まりも終わりもない、どこからでも読める疑似長編にすることにした。
果たせるかな、妄想はそこで止まらず野火のように燃え広がり、次いで文学世界の地図をここに広げてしまおうという考えが閃いた。大学で学んだ現代劇や人文学の参考書籍を押し入れの奥から引っ張り出し、はたまた趣味で蒐集していた放送大学の文学や芸術コースの教材を参考にしつつ、今昔の小説を下敷きに、ないしは意識しながら毛色の異なる掌編をたくさん書き、国から国を渡り歩くようにして読者が文学世界を旅できるような形にしようと努めた。
かくなる妄想の炎で焼き上がった『ホテル・アルカディア』は焦げすぎのような、ふっくらしすぎのような感もあるが、少なくともぼくが常より目指しているもの、他に類を見ない異形の小説となったとは思う。
ぼくの好きなキューバ人作家のレイナルド・アレナスは「それぞれの小説が一つの実験に、新しいものになること」をモットーに掲げていたが、その実験精神が今現在ぼくの執筆の支柱になっている。とかく新たな試みを。売れなくても評価されなくとも。あとのことは知らん、などと無責任に、生意気に。
そういった意味でも、今回Bunkamuraドゥマゴ文学賞をいただけたことは非常にありがたいことだった。これまでの努力が報われた、というよりも、このような勝手極まりない妄想を暴走させるチャンスを与えていただいた編集さんに少しでも報いることができたことが嬉しくて。でもまあ、またそのうち性懲りもなく暴走してしまうのだろうが。そしてそのときもまた、どこまでも無責任であり続けるのだろうが。
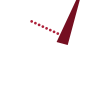















選評
「よくもこんないいかげんな話を……」/ 選考委員 野矢茂樹
読み始めてすぐに「あ、他の小説とぜんぜん違う」と感じた。しばらく読んで「こいつは私の手には負えない」と思った。さらに読み進めて「なんなんだこれは?」とつぶやいた。正直に申し上げて、石川宗生さんを私は知らなかった。百ページぐらいまでだろうか、私はやはり「なんだこりゃ」という気持ちで読んでいた。と、次第に私の中で軽い異変が起こってきた。そして三分の二ほど読んだところで「まいりました」と屈服したのである。何に屈服したのか。ひとことで言えば、よくもまあこんないいかげんな話を次から次へと、とあきれたのである。
ホテル・アルカディアの敷地のはずれのコテージに、支配人の娘のプルデンシアが閉じこもった。そして、ホテルに居住していた芸術家たちによって、コテージの外から彼女に物語を聞かせるという計画が始まった。口から出まかせの短い物語が、入れ替わり立ち替わり語られていく。ある物語では、ある夜に本の挿絵がやってくる。ええと、ですから、玄関を上がって入ってくるわけですよ、本の挿絵が。ある物語では、知人の親戚の義母の元夫の商売敵の恩人の愛人のメル友のファンの隣人のコレコレさんからものまね師のシカシカさんが紹介され、シカシカさんのものまねに翻弄された後は、シカシカさんから口寄せ師のマチマチさんが紹介され、マチマチさんが口寄せした生霊のコチコチさんに丸太造り師のナタナタさんを紹介してもらって……。またある物語では、ノアの箱舟を思わせる話なのだが、乗船を許されるのは一つの種につきひとつがいのみなので、動物たちの間で凄惨な殺し合いが起こる。そしてある物語ではリンゴの鐘がごぉん、ごぉん、ごぉん! と鳴り響く。
なんなんだこれはという気持ちはいまも抜けない。だけどそれを楽しんでいる私がいる。たんなる妄想の開陳ならば、少なくとも私にとってそんなに面白くはない。本書では、妄想が暴走するのである。あるとき私は自分のことを「理系でも文系でもない、妄想系だ。妄想系論理派なのだ」と称したことがある。(ちなみに、妄想系・現実系・体育会系とあり、妄想系には論理派と情緒派がある。そして妄想系情緒派は文学に向くだろうが、妄想系論理派は哲学に向く、などと戯言を述べたのである。)石川さんの妄想には論理展開がある。してみればこれは妄想系論理派の文学と言うべきなのかもしれない。最初のアイデアの種がどんどん膨らみ、これがこうなったら次はこうなる。そしたらこうなって、ここまでいくだろうと、妄想が勝手に突っ走っていく。この妄想のグルーブ感がなんとも楽しい。屈服した私は、小説ってこういうものだったよな、と、物語を語り出すことの根源に触れたような気にさえなったのである。
さらにもう一点強調しておきたいことがある。文章である。硬質な表現と軟派な表現のチャンポン。本格的なのかチャチなのか判然としない文体。しかし確かに言えるのは、随所に詩的感興が浮かび上がることである。表現の選び方、言葉の反復のさせ方、リズム、響きあい、そうした点において、ときに散文詩と言ってもよい表情を見せる。しかも、そうした文章にありがちな、もったいぶった思わせぶりは感じさせない。私がこの作品のどこに最も惹かれるかと言えば、実はこの文章なのかもしれない。
おまけにもう一言。どうもこの本は小ネタ満載であるようだ。「ようだ」というのは、私はいかんせん無教養で、石川さんの仕掛けた小ネタ(出された料理がヨルノハテヘノタビのグリルだったり)がよく分からない。たぶん私に分からない小ネタがまだあちこちに隠されているのだろう。彼の妄想もまったくゼロからの発想ではなく、古今東西の小説などが肥料として鋤きこまれているのだと思う。そしてそんな肥沃な土地を持っているかぎり、そこから妄想がニョキニョキ生えてくるに違いない。これからも、よくもまあ、と私をあきれさせていただきたい。