Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第24回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

山浦玄嗣 著
『ナツェラットの男』
(2013年7月 ぷねうま舎刊)
| 選 考 | 伊藤比呂美 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |
| 授賞式 | 2014年11月6日(木) 於:Bunkamura |
当日開催された授賞式の模様を動画でご覧いただけます。
当日開催された受賞記念対談内で行った山浦玄嗣による朗読(受賞作『ナツェラットの男』P.280~281より)もご覧いただけます。受賞記念対談の模様は雑誌『文學界』(文藝春秋/2015年2月号)(1/7発売)にて掲載されています。
受賞者プロフィール
山浦玄嗣(やまうら はるつぐ)
1940年、東京市大森区山王生まれ。生後すぐ岩手県に移住し、大船渡市で育つ。医師・言語学者・詩人・物語作家。故郷の大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市唐丹町(旧気仙郡)一円に生きている言葉・ケセン語を探求する。掘り起こされたその東北の言語を土台として、新約聖書を原語ギリシャ語から翻訳した『ケセン語訳新約聖書四福音書』で知られる。2013年2月「バチカン有功十字勲章」受章。著書に、ケセン語研究が結実した『ケセン語入門』(1986)、故郷の歴史に材をとった物語『ヒタカミ黄金伝説』(1991)、福音書の新訳『ガリラヤのイェシュー──日本語訳新約聖書四福音書』(2011)などがある。

伊藤比呂美(いとう ひろみ)
1955年東京都生まれ。1978年に第16回現代詩手帖賞を受賞してデビュー。99年『ラニーニャ』で野間文芸新人賞、2006年『河原荒草』で第36回高見順賞、07年『とげ抜き新巣鴨地蔵縁起』で第15回萩原朔太郎賞、第18回紫式部文学賞を受賞。『伊藤比呂美詩集』『良いおっぱい悪いおっぱい 完全版』『読み解き「般若心経」』『父の、生きる』など著書多数。
受賞の言葉
山猿 / 受賞者 山浦玄嗣
複雑に入り組むリアス式海岸の漁村、岩手県気仙(けせん)郡越喜来(おっきらい)村(現・大船渡市)がわたしの故郷だ。村にキリスト教徒は我が家一軒だけ。淋しい潮騒を聞きながら杉皮葺きの陋屋(ろうおく)で母の語るイエスさまの物語が燃える憧れを子供心に注ぎこんだ。
空想と現実の境が曖昧な幼い脳には村の大工はイエスさまに見え、そのおっ母さんはマリアさま、網元の旦那の二人の息子はヤコブとヨハネ、岩のようにいかつい漁師の親父はペトロに違いなかった。福音書の人物はみな村に住んでいて、村人と一緒に陽気に笑い、叫び、体と体をぶつけ合って暮していた。
大好きなイエスさまのことを友だちに紹介したかった。あの人がどんなに愉快で、友だちのためなら命もぶん投げる俠気のある男かといくら語ってもだれも聞いてはくれなかった。家にある聖書やキリスト教の本を読んでも聞かせたが、小難しい東京弁の文章は村童には外国語だった。わたしのイエスさまは気仙の言葉を喋るのだ。この聖書ではだめだと痛切に思った。
聖書のすてきな物語りを気仙の言葉に直したい。でも、標準語とかけ離れたわれわれの言葉の音韻を書く文字はなく、整った文を組み立てるための文法も整備されていなかった。それどころか、東北弁は愚鈍醜悪な方言で、撲滅すべきだというのが国の教育方針だった。東北人はその訛りの故に国中の笑いものだった。屈辱だった。わが母語に文字を与え、これによってふるさとの仲間にイエスの心を伝えたい。これが大きな夢だった。
長じてわたしは医者になり、多忙な医業の中で夢は棚上げされていたが、東北大学に奉職していた35歳の時にふるさとのおじさんと久しぶりに再会し、あの夢が燃え上がった。余暇のすべてを注ぎこんでふるさとの言葉「ケセン語」の研究にのめり込み、文字を考案し、文法を整備し、教科書を書き、辞典を作った。60歳になった。
これでやっとペンができたと喜んで、新約聖書の四福音書の翻訳に着手した。はじめは既成の日本語訳聖書をケセン語にしようと思っていた。だがあらためて見直すと、それは日本語として意味の通じない奇妙な翻訳用語の羅列だった。これではだめだ。それで、古代ギリシャ語の原典からの翻訳に挑戦した。『ケセン語訳新約聖書・四福音書』ができ、時のローマ教皇ヨハネ・パウロ二世はこれを嘉し、2004年、われわれケセン遣欧使節団28名はバチカンに招かれ、ケセン語訳聖書を献呈する栄誉を受けた。
多くの読者の求めに応じて、ケセン語を広く日本中に通じるセケン(世間)語にして訳し直す仕事を始めた。途中あの大津波の被害を受けたが、何とかこれをかいくぐり、2011年に登場人物にその出身に合わせて全国の方言を喋らせる『ガリラヤのイェシュー 日本語訳新約聖書四福音書』を出版した。
一連の訳業を通じ、聖書の行間には文字になっていない実に豊かな世界が広がっていることに気づいた。当時の人々にとっては格別文字にする必要もなかった瑣末なことであっても、現代のわれわれにとってはむしゃぶりつきたくなるほど魅力的な内容が含まれているのだ。これは単なる翻訳だけでは伝えられない。何とかして、聖書の行間から立ちのぼるイエスとその仲間たちの生きた息吹、血の躍るような物語りを日本中の仲間に伝えたいと熱く思った。
小説『ナツェラットの男』はこうして生まれた。わたしは小説の書き方など勉強したこともない。ただただ熱に浮かされたようにして書いた。思いもかけず選者の目に留まり目もくらむような賞を頂戴する。しかも、ドゥマゴのマゴは仏和辞典によれば「山猿」の ととある。わたしの若いときのあだ名だ。わが友ナツェラットのイェシュー殿の哄笑が聞こえるようだ。嬉しくもありがたいことである。
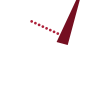















選評
「語りの声だ」/ 選考委員 伊藤比呂美
山浦玄嗣さんのケセン語聖書のすばらしさは言い尽くせない。ここ数年わたしは、語りとしてのお経に興味を持っているのだが、お経とは、もともと大乗仏教の布教者が、町から町へ、辻から辻へと語って歩いたのが原型だそうだ。『ケセン語訳の聖書』を読んで(付属のCDで耳でも聞いて)、福音書というのも、まさにそうだと気づくことができた。
そしてこの『ナツェラットの男』。
不思議な読後感だった。完成されているかというとそうでもない。語りの力で読ませるかというともう一息である。むしろなんだかとても野暮ったい。ださいとすら思う。でも魅力がある。無造作で、無鉄砲で、無頓着で、無邪気で、無垢で、無限で。わたしはやみくもに感動して、人に勧めた。勧めまくった。すごいですよ、こんなにださい小説はめったにありませんよ、と。
イエスはかっこよく、ユダもいいやつで、ペテロは「鶴亀鶴亀」とか言ってて、みんなとっても人間的で、お話はうんちくだらけで、でもそのうんちくから、あの頃の人々の暮らしがクッキリ見えてくるようで、ところどころ歌が挿入されるんですけど、それがまたものすごく美しい詩で、女たちの一人称は過剰に女っぽい女ことばで、オノマトペは可笑しいくらいありきたりで、話を区切ろうとするときに、いつも一文よけいなんです、と。
伊藤さんの勧めることばを聞いてると、いいのか悪いのかわかんないんですけど、といろんな人に言われた。
文学を作ろうと志せば、たいていは、まあ、まず、既製の文学を読む。そして「それらしいもの」を作ろうとする。みんな逸脱したいと思っているのに、逸脱はとてもむずかしい。でも『ナツェラットの男』は、逸脱も何も、最初から「それらしいもの」など何も考えていないようだ。
「藪の中」を連想する。でもそれは、複数の一人称語りという理由だけだ。「駈込み訴え」も連想する。でも、違うのはすぐにわかる。イエスは太宰ではなく、ユダも太宰ではない。もっとまっとうな真摯な意図がそこにある。ある意味、この感じは、石牟礼道子さんの書くものに似ているとも考えた。『苦界浄土』ではない、もっと後に書かれた諸作品。わたしたちの知っている近代文学や現代文学じゃない、もっと獰猛で、野蛮で、無造作で、無限で。
ドゥマゴ賞のことを考えはじめたとき、この本が、いちばん先に心にひっかかった。そしていつまでも消えていかなかった。いったいなぜこの本が、欠点がいっぱい目につくのに、わたしを惹きつけるのか、わからないままだった。引き受けたときは七月で、秋が来て、冬になり、春が来て、夏が来た。いよいよ一作に決めねばならず、悩み抜いているときに、七月、熊本で、渡辺京二さんが石牟礼さんの文学を評して「説経節です」と言うのを聞いた。そのとき、ああ、開けたと思った。『ナツェラットの男』も、説経節。
説経節とは、近世初期に盛んになり、浄瑠璃や歌舞伎に押されて衰えていった、元をたどれば能や仏教説話にもたどりつく、語りの文芸である。説経節とくくるためには、まず神仏の縁起を語ること。そして、それに関わる人の生きざまをいきいきと語ること。底辺の人々の暮らしに密着した語りであること。ときどき歌を入れること。そしてときどき野蛮なくらい逸脱した語りであること。『ナツェラットの男』にはそれがぜんぶある。信仰がある。生きざまをいきいきと語る。底辺の人々が力強く生きる。歌はほんとうに美しい。そして文学として、野蛮なくらい逸脱している。
わたしはここ何十年と、説経節こそ(ある種の)詩の理想的な形だと考えてきた。それでわたしをこんなに惹きつけた。
そこに聞こえてくるのは、岩手の大船渡の町医者である山浦玄嗣さんが、診察室で、老若の患者たちに、請われるままに語る声だ。ときになまめかしい女声になったり、子どもの幼な声や老人のしわがれ声になったりしながら、次々につづいていく語りの声だ。