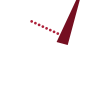先進性と独創性のある新しい文学の可能性を探るため、毎年かわる「ひとりの選考委員」が受賞作を選ぶ「Bunkamuraドゥマゴ文学賞」。第35回となる2025年度はノンフィクションライターの最相葉月さんが選考委員を務め、東京を拠点に評伝や旅行記を執筆している川内有緒さんのノンフィクション『ロッコク・キッチン』(「群像」2024年10月号~2025年8月号隔月連載 講談社刊)に決定。その贈呈式が11月27日(木)に執り行われました。
 『ロッコク・キッチン』の書名にもなっているロッコクとは、東京から仙台を結ぶ幹線道路である国道6号線の通称で、本作の舞台である福島県の浜通り地域を縦断しています。東日本大震災と福島第一原発事故から10数年が経過する中、避難指示が徐々に解除され日常の暮らしが戻りつつある浜通りの人々は、どんなキッチンで何を作り、誰とどんなものを食べているのか? そうした興味に駆られた川内さんがまず住民からエッセイを募集し、興味をかき立てられた人を詳しく取材し、食を通じて人々の暮らしや人生を温かく描き出した再生と希望の生活史です。
『ロッコク・キッチン』の書名にもなっているロッコクとは、東京から仙台を結ぶ幹線道路である国道6号線の通称で、本作の舞台である福島県の浜通り地域を縦断しています。東日本大震災と福島第一原発事故から10数年が経過する中、避難指示が徐々に解除され日常の暮らしが戻りつつある浜通りの人々は、どんなキッチンで何を作り、誰とどんなものを食べているのか? そうした興味に駆られた川内さんがまず住民からエッセイを募集し、興味をかき立てられた人を詳しく取材し、食を通じて人々の暮らしや人生を温かく描き出した再生と希望の生活史です。
なお、本書は文芸誌「群像」2024年10月号から2025年8月号まで隔月連載された内容をまとめたもの。最相さんは連載中から本作に注目し、選考期限ギリギリに連載が終了すると知り授賞を決めました。贈呈式で最相さんはその経緯について「福島という食の問題に揺れた地にいらっしゃる方たちが何を食べているかというのは、ジャーナリスティックな意味で重要。それに加え、生きるとはどういうことかという根本的なテーマも私たちが知っておくべきことだと思い、最後まで連載を見届けました」と説明。さらに「本書は川内さんの作品ですが、たくさんの人の息遣いが聞こえる共同作品的なものでもあります。もしかしたら文学というのは、こういうふうに生まれるものなのかもしれない──そしてこれから次々と何かが生まれそうな予感を覚えました」と今後への期待も寄せていました。

贈呈式では川内さんがお子さんからお祝いの花束を受け取って目を潤ませるという感動の一幕も。壇上に立った川内さんは受賞について「当時は単行本の加筆修正について悩んでいる最中でしたが、お知らせを受けて新しいエネルギーをもらいました。頑張って完成させようという目標と、賞に値するものに仕上げなければというプレッシャーを抱き、何とか本を出すことができました」と大きな力になったことを告白。そして「多くの方から協力をいただき、この本が成り立ちました。駅伝にたとえると私がたまたま最終走者だから注目されているだけで、本当に注目されなければいけないのは浜通りの皆さんや今も故郷に帰れない皆さんです。私は全国の方に浜通りの今の状況を知ってもらいたいと思っています。福島に興味を持ちそうな方が周りにいらっしゃったら、ぜひ本書をプレゼントしてお力添えください」と呼び掛けました。
続いて、贈呈式の直前に行われた最相さんと川内さんの対談をお届けします。
話がしっかり伝わるなら写真の力も映像の力も借りたい
川内有緒さん(以下、川内):私がロッコクに注目し始めたのは10年くらい前でした。それ以降、街がどんどん変わり、避難指示が出て真っ暗だった街に少しずつ明かりが増え、避難指示が解除されていく中で「みんな今どういう暮らしをしてるのかな」という素朴な疑問が出発点となり、約2年前から本格的に取材を始めました。
最相葉月さん(以下、最相):本書は「浜通りに暮らす人々が何を食べてるんだろう?」がテーマですが、取材でご馳走までなっちゃうというのが驚きました(笑)。
川内:そうですよね。みんなが何を食べてどう生きてるんだろう?という疑問が始まりなのですが、「○○を食べてます」と言われたら、やっぱり私も食べてみたい!という野次馬根性が増幅してしまうんです。
 最相:今回の取材は川内さんお一人ではなかったんですよね。
最相:今回の取材は川内さんお一人ではなかったんですよね。
川内:はい。『ロッコク・キッチン』は本と映画を同時進行で作るというプロジェクトで、私と監督、プロデューサー2人と写真家の5人で取材相手のお宅にぞろぞろとお邪魔しました。中にはワンルームにお住まいの方もいらっしゃって、大人数でギュッとなりましたけどそれはそれで楽しかったです。
最相:川内さんはもともと映画監督を目指していたそうですが、今回、本の取材と映画撮影を同時進行で行ったのはそれと関係しますか?
川内:関係あると思います。私はチームワークが苦手なので文章を書くスタイルに行き着いたのですが、自分の筆1本の力で話を伝えたいとはこだわっていません。もし伝わるのならどんなメディアでもいいんじゃないかと考えていて、必要であれば写真の力も借りたいし映像が撮れるなら撮っておきたい。そういう気持ちが今回の取材体制につながりました。
最相:私の場合は取材に編集者が同行せず1人で行くことがほとんどなんです。それは、お相手に心の中を深く潜っていくような話をお願いすることが多く、第三者がいることで取材中の空気を壊されたくないから。今回の取材でもそういうケースはありましたか?
川内:はい、生と死をテーマに扱うような繊細な内容の場合は私1人で取材しました。それ以外のケースは臨機応変に対応しましたが、同行する場合もそこにいることに意味がない方には付いてきてほしくないという思いはありましたね。
最相:川内さんは吉本ばななさんのファンだそうですが、川内さんにとってキッチンとはどんな場所ですか?
川内:私は吉本さんの『キッチン』が大好きで、その中に、遠くにいる友人にわざわざカツ丼を届けるという場⾯があるのですが、誰かのために作ってあげたいとか、誰かに食べさせたいとか、キッチンにはいろんな思いが詰まっていますよね。どんな形でも家の中には必ずキッチンがあり、暮らしのすべてがそこに凝縮されているような場所。だからこそ今回キッチンをテーマにしたいと思ったんです。
取材での体験を通じて本の構想が芽生えていった
 最相:チームでの取材が終わったら文章に起こす作業へ入るわけですが、どのように切り替えましたか?
最相:チームでの取材が終わったら文章に起こす作業へ入るわけですが、どのように切り替えましたか?
川内:私は文章に自分が出てきてしまうタイプで、エッセイとノンフィクションの中間だとよく言われます。今回も、自分の一次体験を起点に、自らの中から湧き出るものをどんどん書いていきました。また、文章にするにあたって話を詳しく掘り下げたいというケースもあり、その場合は追加で取材させていただきました。何度もお会いして関係が深まったところでしか書けないものもありますから。
最相:レコーダーをオフにした瞬間に本音を語り始めることもありますからね。本書には魅力的な人物がたくさん登場しますが、毎日必ずハガキを3枚書く中国出身の大竹さんが一番気になりました。何気ないハガキの内容を朗読されただけでも、それまでの彼女の人生を想像してしまいました。
川内:今回の取材ではあらかじめ目星をつけた人を訪ねて旅していくのではなく、旅の中で出会えた人を掘り下げていきたいという気持ちが最初からありました。大竹さんもエッセイを通じて偶然出会えた方で、事前知識もなくゼロの状態から取材しました。何度か取材を重ねる中で知った事実もありましたが、初めてお話を聞いた時の驚きを読者にも届けたいと思い、あえて加筆せず最初の会話をそのまま本にしようと決めたんです。
最相:東京電力のOBである石崎さんとの対話も印象的でした。原発事故や原発の是非にも話題が及んでいて、どの立場で話を聞きどう書くか難しかったんじゃないでしょうか。
川内:そうですね。読んでいただくと私がどんな立場で書いたか分かると思いますが、お話を伺う際に私の立場を明確にするとお相手も構えてしまうので、なるべくニュートラルなスタンスを心がけました。しかし、これだけ難しいテーマを扱うにあたって本当にそれで良かったのか?という自問自答が自分の中に現れるようになり、最相さんも読んでいてお気づきになったのかもしれません。
最相:福島第一原発の現場で働く方も登場していましたね。夜は屋外の更地で書店を営業しているという武内さんで、素敵な写真が掲載されていました。
川内:大熊町の「読書屋 息つぎ」ですね。武内さんは初めの頃に取材した方で、彼が言ってくれた言葉が大きな指針として本全体を導いてくれたんです。
最相:どんな言葉ですか?
 川内:武内さんは震災があった時はまだ小学生で「震災前と比べて今は街が変わりすぎて、昔のことが思い出せない。懐かしもうと思っても懐かしめないんです」と言うんです。この言葉はとても刺さりました。それでも武内さんは新しい場所に本屋さんを作り、新しい人たちと新しい文化を日々築こうとしていて、これはぜひ描かなければいけない物語だと思いました。
川内:武内さんは震災があった時はまだ小学生で「震災前と比べて今は街が変わりすぎて、昔のことが思い出せない。懐かしもうと思っても懐かしめないんです」と言うんです。この言葉はとても刺さりました。それでも武内さんは新しい場所に本屋さんを作り、新しい人たちと新しい文化を日々築こうとしていて、これはぜひ描かなければいけない物語だと思いました。
最相:武内さんの知人が作ってくれたクラムチャウダーが、夜の闇と寒さと対極的に感じられました。
川内:あの時は本当に寒かったですね。最初はどうしてこんな場所で武内さんは本屋を続けるのかと思いましたが、この寒さや暗さこそが本当に必要なものだとだんだん分かってきたんです。本来の地球はこんなに暗くて寒い場所なんだということが、彼の屋外本屋さんの活動から伝わってくることでした。
文章ではなく映画だから伝えることができたものとは?
最相:映画も拝見したので、そちらについても伺いたいと思います。「おれたちの伝承館」の中筋館長がキュレーターとして集めたアート作品が本でも映画でも紹介されていますが、映像だと作品のエネルギーがこれでもかと迫ってきて、本とは違った空気感が感じられました。
川内:アートを文章で表現するのは難しいし、想像しづらいものについて読むのは読者にとってもストレスなので、本ではあまり書きませんでした。そのぶん映画では一つひとつの作品をじっくり見ていただこうと思い、しっかりフィーチャーしています。
最相:ほかにも映画では浜通りの人たちの震災前の生活風景を写したホームムービーが使われ、現在との対比が印象的でした。
川内:現地に行くと「震災前ってどんな風景だったんだろうね」と話すことが多々あり、先ほどの武内さんの言葉もだんだん胸に迫るようになりました。また、新しく移住してきた人たちからも「昔の風景を知らないのが残念だ」と言われて、せっかくだから、記録映像などを借りてくるのではなく、住民の皆さんたちが撮影したホームムービーを集めようと思ったんです。どうやって映画に入れたらいいか悩みましたが、最終的に今の形に落ち着きました。
最相:子どもたちがピンク色のかき氷を食べている映像は良かったですね。
川内:そうですね。浪江町の商店街で食堂を営まれていた方のなんてことのない映像ですが、震災が起きたことで特別な意味を持ってしまいました。今、その地にいられない人たちにどう思いを馳せていくかというのが本でも映画でも1つの課題でしたが、そこに住んでる人たちは今いない人たちのことをずっと心に思っているわけで、彼らを通じて今いない人たちを思うという形にしたいと思いました。そう考えてからはホームムービーの入れ方が分かったんです。
最相:本と比較しながら映画を観るのも面白いと思います。映画でしか伝わらないこともありますから。

写真:大久保惠造 構成:上村真徹