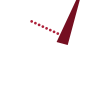第34回(2024年度)Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞者の高野秀行さん、世界各地の危険地帯を取材してきたジャーナリスト・丸山ゴンザレスさん、第34回受賞作『イラク水滸伝』で旅を共にした探検家の山田高司さんによる『ドゥマゴサロン 第22回文学カフェ「ネットでは出会えない世界のリアル ノンフィクションを届けること」』を、2月にBunkamuraで開催しました。当日の模様をお送りします。
高野さんと丸山さんの最初の出会い
高野 今日はみなさんお集まりいただき、ありがとうございます。ノンフィクション作家の高野秀行です。
丸山 ジャーナリストなどをしている丸山ゴンザレスです。
山田 高野から山田隊長と呼ばれている老いぼれです(笑)。本書では挿絵を担当しました。
丸山 まずは高野さん、受賞おめでとうございます!

ノンフィクション作家、第34回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞者 高野秀行さん
高野 ありがとうございます。僕と隊長のご縁はすでに本でご存知の方も多いでしょうから、まず最初に丸山くんと僕の馴れ初めを、軽くお伝えしましょうか。最初に会ったのは、もう10年以上前で、丸山くんもまだテレビに出る以前でしたね。
丸山 はい。僕は高野さんの著作を全部読んでいたからぜひ会いたかったんですが、その頃いろんな人が殺到していて、お目にかかるのもハードルが高かったんですね。そしたら双葉社の担当編集の方がちょうど高野さんの探検部の後輩で、「僕は高野さんの『ワセダ三畳青春記』が本当に大好きで、それをお伝えください」って言ったら、「そういうマインドの人だったら大丈夫ですね」とOKをもらって。
高野 なんかえらそうで、すみません(笑)。
丸山 そこで高野さんと初めて会って、すごく刺激を受けたんですね、こういう大人いるんだって。自分もライターとして、どう旅をして、どう書いていくべきかを考えさせられました。
高野 最近では圧倒的に丸山くんのほうが有名になって、なかなか会えない人になってるじゃない。
丸山 全然そんなことないです。映像畑だからチームで動くことが多く、昔みたいに自由にならないだけで。でも最初、高野さんが「クレイジージャーニー」に出てくれるとは、正直思ってなかったんですよ。
高野 そうなの? お声がけいただいたのは、昔の写真や動画を見せながら体験を話すだけだったし……。
丸山 でもネタが、まさかの『アヘン王国潜入記』の裏話!
高野 テレビでは基本的に、アヘンの話なんて絶対にできないですよね。TBSの法務部や弁護士の方と綿密に打ち合わせしたのを覚えていますが、あれは面白かったですね。
丸山 今日は『イラク水滸伝』がメインテーマですから、あらためて山田隊長と高野さんの関係性もぜひ。

ジャーナリスト 丸山ゴンザレスさん
コンゴの怪獣”ムベンベ”捜索中にニアミス
山田 高野と初めて会ったのは1991年だけど、実はそれ以前の88年にニアミスしてるんですよ。高野がアフリカ・コンゴのテレ湖にムベンベを探しに行ってたときに。
高野 僕がまだ早稲田探検部にいた頃の話で、8歳年上の山田隊長は東京農大の探検部出身でした。
山田 僕は在学中に南米の三大河川であるオリノコ川、アマゾン川、ラプラタ川を舟でめぐったあと、85年頃からアフリカの川をずっと探検して回ってたんですね。で、88年にコンゴの川を下っているときに、「この先をもう少し行ったジャングルの中で、高野ってやつが怪獣ムベンベを探してるらしいよ」と聞いたのが名前を知った最初です。
その後、89年にナイル源流が治安悪く、川旅を一時中断し、91年からアフリカのチャドで植林のプロジェクトを始めました。フランス語で現地の政府とやりとりする必要が出てきて、「誰かフランス語ができるやつはいないか」と探していたら、探検部の後輩に紹介されたのが高野。「我々は金がないんで、晩飯と酒つけたら申請書とか書いてくれるか?」ってお願いしたら書いてくれてね(笑)。
高野 僕はコンゴに怪獣探しに行っていたので、コンゴ政府とフランス語でやりとりしていたんですね。もしムベンベが見つかったら、どちら側にどういう権利があるかとか、契約書を作るために交渉していたんです。「最初に発表する権利は、絶対にうちに欲しい」とか、取らぬ怪獣の皮算用をやっていた(笑)。
だから、アフリカのフランス語圏の政府に出す公式文書を書くのがすごく得意になっていて、その特殊能力が活きたわけです。
丸山 山田隊長は怪獣探している後輩がいるって聞いて、どう思いました?
山田 純粋に面白いなって思ったよ。ムベンベは、ネッシーみたいに「もしかしたらいるかもしれない」と日本でも紹介されていたし。
高野 でも当時ね、怪獣探しなんて「邪道」だったんですよ。探検部の世界でも揶揄されていたから(笑)。
丸山 探検家界隈では、山田隊長はすでに伝説でした?
高野 そりゃもう川下り冒険のレジェンド。南米の三大河川のあとアフリカに行って、日本にも滅多に帰ってこない、伝説の人ですよね。

探検家、環境活動家 山田高司さん
高野さんの琴線に触れた山田隊長の生き方
丸山 そんな山田隊長と高野さんが、一緒にアフリカを旅し始めたのは、川つながりだったんですよね。
山田 チャドで5年間植林をした後、木を植えながら、カヌーでナイル川を下る計画だったんです。当時はウガンダ(北部)とか南スーダンあたりの治安がすごく悪くて、アフリカ人のあいだでも「あそこだけは行くな」というところだった。だからそれ以上一人でまわるのは危険で、ウガンダから「高野、暇か? 4か月一緒にナイル川を巡れるか?」って言ったら「行けます!」という。
高野 今から考えるとすごい話ですよ。英語とフランス語がある程度できて、アフリカをある程度知っていて、4か月仕事ができて、しかもノーギャラ。普通そんな人材いるのか?
山田 日本全国探しても、1人しかいないだろうね。それが高野だった(笑)。
高野 でもそのとき僕は人生最悪の時期で、直前までミャンマーのワ州でアヘンの取材をしていたわけです。アヘン取材に人生を賭けていたのに、書いた原稿は全く出版社に相手にされない。酒をどんどん飲むようになって、アル中になってしまった。
30過ぎて仕事もない、貯金もない、彼女もいない。「自分は何なんだ?」という思いがグルグルめぐる日々で……精神的に本当にヤバかったときに隊長からそんな話がきたから、タダで4か月アフリカに行けるだけで、とても嬉しかったんです。

丸山 アフリカの旅では何をしたんですか?
山田 植林プロジェクト形成調査という名目で助成金を引き出して、ナイル源流から陸路で、ルワンダ、ケニア、ナイロビ、エチオピア、スーダンまで一緒に川の流域をめぐりましたね。ちょうどルワンダで3年前にひどい内戦があった頃でした。
高野 97年にナイル川流域を4か月めぐって、地元の環境NGOをサポートしました。僕は環境問題の知識がまったくなかったから、隊長に一から教えてもらいましたね。
一緒に旅をするなかで、隊長からいかに川が面白いかという話を何度も聞きました。とくに琴線に触れたのは、「川はその地の一番低いところを流れる」という話。一番低いところから、その土地を見るべきだと。
例えば、アフリカでは、外国人が村にやってくるとき、ランドクルーザーみたいな大型車に乗って道路から来るわけです。しかも道路は一段高くなっているから、地元の人からすると「上から下りてくる」感じ。脅威ですよね。でも、山田隊長は、一番下を舟でいく。川を舟で下るってスピードが遅いし逃げ場がないから一番セキュリティ的にダメなんですよ。でもこれが一番地元の人に警戒されないんですね。
一番目線の低い所から丸腰で手を上げて入っていくと、取材でも見えるものがまるで違う。「地を這うような」取材でなくて、「地面よりもっと低いところから物事を見る」――そんな隊長の生き方に触れて、迂闊にも痺れてしまったんだよね。
丸山 迂闊にも!?
高野 そう、迂闊にも。そして旅の最後に、今度は絶対にナイル川を一緒に下ろうと誓ったんです。
山田 4か月タダ働きさせた代わりに、ナイル川を下れるようになって行くときは、「席を一つ高野のために空けとくからな」って約束しました。でも、20年たってもナイル川は一向に下れる状況にならない。で、今から8年ほど前に、「いい所見つけた、行きましょう」と高野に言われて行ったのが、今回のイラク湿地帯=アフワールだったわけです。
舟旅の専門家から見たタラーデの乗り心地
丸山 すごい絆ですね! 舟旅の専門家から見て、イラクの伝統的な舟タラーデは乗ってみてどうでした?
山田 どうもこうも、本をよく読まれると分かるんですが、僕らタラーデには2時間しか乗ってないのよ! やっとの思いでつくって川に出せた舟をこげたのはたった2時間なのに、こんなにも壮大な一冊になって。高野はたいしたもんだと思ったね。

伝統的な舟タラーデに乗って ©高野秀行
高野 でもけっこう舟の操作性よかったじゃないですか。安定性もいいし、スピードもそこそこ出て。
山田 多分、長期の旅もできる舟だね。本当にハリボテみたいなつくり方で、最後はコールタールで固めるからすごく重たいんだけど、意外にも安定性がよかった。
丸山 今回、全3回の旅をされてますが、一度、コロナ禍のさなかで急遽行けなくなったときに高野さんにお会いしたら「イラクに舟置いてきたから取りに行かなきゃー」って言ってましたよね。
「いやーイラクには湿地帯があって、水滸伝なんだよね」って言われてちんぷんかんぷん。でもそれが本として見事にまとまっていたので、すごく嬉しかったですね。
高野 ことの顛末は本書をお読みいただくとして、アフワールで川下りをするはずがとんだ迷走になり……「失敗を書かせたら、高野秀行の右に出るものはない」って、誰かが謎の名言を伝えてくれましたよ(笑)。
ネタを探し出す嗅覚
丸山 『イラク水滸伝』もそうですが、毎回よくぞこんな場所とテーマを見つけたな、という嗅覚が高野さんならではです。アフワールのような知られざる地の発見、これ意外にも新聞記事だったんですよね。
高野 そう。朝日新聞の国際面のトップに出てました。
丸山 全国紙で出ていたのに、現地に行ってみようと反応したのが高野さんだけだったというのが、またすごい。
高野 よくそんなことが起こるんですよ。最新刊の『酒を主食とする人々』も、元ネタは京都大学の砂野唯さんという研究者の方が本を書いてるんです。ジュンク堂書店の文化人類学の棚でたまたま見つけたその『酒を食べる』という本には、エチオピアのある民族の信じられない食習慣が書いてあったんですね。
よくいろんな人に、「どうやって、あんなネタ見つけてくるんですか?」って聞かれるんですけど、どうもなにも、本屋に本が置いてあっただけです(笑)。
丸山 僕のネタの探し方とも近い気がします。危険地帯の取材だからといってなにも特殊なルートがあるわけではなく、先日「クレイジージャーニー」で放送したエルサルバドルの刑務所も、2年前にBBCの独占でカメラが入ったという放送を見て知りました。後日、別の国の知り合いのジャーナリストから「BBCとエルサルバドル政府の間をつないだのは俺だけど」というのを聞いて、「じゃあお前から頼んでくれないか」と頼んで実現した企画です。
だから、普通に全世界の人たちと同じものを見ていても、その先に一歩踏み出すかどうかの違いだけなのかも知れませんね。高野さんは、最初から、本を書くための取材なんですか? それとも、ただの好奇心が勝つときがある?
高野 ただの好奇心が勝つときが普通によくあって、今回もとにかく隊長と一緒に川下りがしたいっていうシンプルなところからスタートしています。いつも未知に対する憧れと自由に何かやりたいっていうのが渾然一体になっていて、自分でも区別がつかなくなっていますね。まあ結果的に、川下りの話ではなくなったけれども。

山田隊長は19世紀の探検家?博物学者?!
山田 イラクは初めてでしたが、南米やアフリカの大湿地には行った経験があったので、湿地帯の旅はかなり大変だぞと言ったんだけど、高野は都合の悪いことは見事に耳を通り抜けてしまう(笑)。
丸山 それが高野さんのいいところ。あと今回『イラク水滸伝』を読んでいて本当に助かったのは山田隊長のイラストです。絵というものがこんなにも文化的背景の理解を促すことに驚きました。写真よりもイラストのほうが、ビジュアルイメージとして残るしわかりやすいんですよね。

©山田高司
高野 写真は正確だし細かいけれども、余計なものまで映り込んでしまう欠点がある。でもイラストなら、例えば水牛を飼って暮らしている人の浮島を丸ごと斜め上から俯瞰したりできますからね。
丸山 山田隊長がイラストを描いたのは日本帰ってきてからですか? 旅先ではメモ程度で。
山田 両方ですね、現場でもけっこう描きました。欲しがる人が多いからどんどん上げていたら、高野に怒られてね。「貴重なものなのだから、あげないでください」って。
高野 現場の状況をすごくよく伝えている絵だし、絶対に本にも使いたいと思って。僕からすると、山田隊長は19世紀の探検家や博物学者に近い存在で、当時はまだ写真なんて普及してないから、ダーウィンでもフンボルトでも、みなイラストを描いていたでしょう。そうした絵は精密に描かれているし、いろんな説明書きが入っていて資料価値も高い。隊長はつねに自然環境から世界を見ているので、文化系の僕の視点とはまったく異なり大きな刺激になります。
あとナチュラリストなのに、文学や昔の故事成句にやたらと詳しくて、すぐに名言を吐くんですよ。老子がこう言ってるとか、ポンポン出してくる。
山田 単に老子好きなんです。
高野 言語哲学者のウィトゲンシュタインとかも出してくるんですよ。「歯の痛いものにしか、歯医者の看板は見えない」って。「高野にいくら教えても、全然関心を持たないから覚えないんや」という意味でお小言を言われる(笑)。
丸山さんが砂漠嫌いになった理由
丸山 レベルの高い説教ですね! 何にでも関心をもつ大切さというか、食わず嫌いはよくないなと身にしみます。
というのも、僕はイスラム圏にはちょっぴり苦手意識があって、昔22歳の頃ドバイに行ったときにひどい目にあったことがあるんですよ。夜中の便で到着して、タクシーの運転手と一緒にホテル探していたら、途中で運転手が面倒くさくなったみたいで、「もう、いい。ところでお前イスラム教に入らないか?」と言い出す。「嫌だよ」と断ったら、突然運転手が怒って、砂漠の真ん中にある建設中のショッピングモールの工事現場に置いてかれたんです。
そこで夜を明かして、明け方太陽が昇っていくに連れてどんどん身体が干からびていくのを感じましたね。たまたま通りがかった車がいて助かったんですけど、以来、砂漠嫌いになって。高野さんはイスラム文化圏のどういうところが好きなんですか?

高野 とんだ目にあいましたね! 一口にイスラム文化圏といっても、本書に出てくるマンダ教徒はイスラムじゃないし、実際中東には、イスラム国に制圧されて奴隷として売られてしまった悲劇で知られるヤズディ教徒や、イスラム教徒なんだけどお祈りもしないしモスクにも行かないし酒を飲むというアレヴィー派もいたりします。湿地帯もイスラム色が弱いですし。
ヨーロッパのキリスト教が中世に、いろんな宗教が混じり合うグラデーションを異端として徹底的に潰したのに比べて、中東エリアには元来多様性があって、イスラムも少数派やグラデーションがあって結構面白い世界なんですよ。
旅の面白さをリーダビリティ高く書く
山田 でもほら、似顔絵を描いてたら、一度本当に危ない目にあったことがあったじゃない。
僕は現地でよく似顔絵を求められて描いていたんですが、ある家庭を訪問したさい頼まれて女の子をスケッチしていたら、その家のお母さんとお姉ちゃんが「私も描いて」って、急にベールを脱いじゃった。隣にものすごく怖い父ちゃんがいて、もう殺されるかと思ったよ!
高野 そうそう、お父さんがすさまじい形相で怒りかけてね。マズイ!って命の危険を感じて、僕はみんなの前で地元の電気漁でビリビリしびれる魚の真似の一発芸とかで笑いをとるわけです。イスラム圏の男社会は男子校みたいなノリだから、そういう馬鹿な芸がウケる。お父さんはホストだから、みんなが笑ってウケてると怒るに怒れなくなって、なんとかおさまりましたが。
丸山 それはヤバかったですね! ノンフィクションを書く難しさって、その土地の奥行きや旅の面白さをいかにリーダビリティ高く書くかだと思うのですが、そういう笑えるエピソードも含めて、高野さんの文章はぐいぐい読ませますよね。
高野 その点、今回誤算だったのは、歴史が深すぎたこと。今まで行ってきた辺境は記録が残ってない地域が多かったんですが、なんせここは世界で一番古い歴史が残っている場所。調べることが大量にあったし、かといって説明ばかりが続くと読者は飽きてしまう。背景の説明なども、いかにお勉強にならないようにするかで苦心しました。
丸山 そのお勉強の部分の読みやすさは、山田隊長のイラストの貢献も大きかったですよね。これまでの高野作品とはちょっと毛色が違うビジュアル寄せの見せ方で。
高野 本当にそう。ある意味、隊長は僕の“延命装置”なんです。何を言ってるかわからないでしょうが、その昔、早稲田探検部の大先輩だった船戸与一さんという作家が「作家25年寿命説」を語っていたんですよ。
どんなに才能のある作家でも、大体25年で終わる。最初は粗削りだけど勢いがあって、段々洗練されて上手くなっていく。けれどピークを過ぎるとどんどん文章がツルツルしてきて自己模倣が始まりマンネリ化していく。そうして編集者もだんだん声を掛けなくなるのが大体25年だ、と。
僕は、それを聞いて戦慄したんですよね。だって、僕は22歳の頃から書いているのに売れるまでに異常に時間がかかったから、すでにもう書き手としての寿命が尽きかけていた。これは、ヤバイぞって。そのとき、自分だけではどう頑張っても25年の壁を越えられないから、「外部の力」が必要だと思ったんですよ。僕はこれまでさまざまな外部に頼ってきましたが、中でも大きな存在が山田隊長です。隊長の視点を取り入れると、自分の作品がまったく違う次元のものにできる。その意味で、山田隊長は僕の強力かつ大切な延命装置なんです。
丸山 山田隊長的にはどうなんですか?
山田 それはお互い様じゃないかな。僕は僕で、高野からエネルギーをもらっているし。

三人にとっての”旅”とは?
丸山 お二人の旅にこれからも期待したいです。最後に、会場からきている質問「御三方にとって、一言でいうと旅とはなんですか?」に答えて締めくくりましょうか。
高野 では丸山さんからぜひ。
丸山 旅は、好奇心を満たす最良の手段です。僕はやりたいことと仕事を全部一致させる生き方をしてきたから、旅は僕が生きていくうえでなくてはならないものですね。
山田 僕は長いあいだ旅をするなかで、いつからか、「旅するように新鮮に日々を暮らし、日々の暮らしのように地道に旅をしたい」と思うようになりました。旅先ではそこで地道に生きている人を大事にしたいし、自分の暮らしのなかに旅人がやってきたときはきちんともてなしたい。「地道に旅したいし、毎日新鮮に暮らしたい」というのが僕の旅のモットーです。
丸山 素晴らしい、心にしみました。
高野 隊長の名言、出ましたね! 僕はもうシンプルに、旅=未知を探す行為ですね。旅をするときには常に「何かを発見したい」と思っています。もっと言えば、自分の常識を変えたい、常識の外にあるものを見たいという思いが強くありますね。
丸山 今日は興味深い話をいろいろと聞けて非常に楽しかったです。
高野 こちらこそ本当にありがとうございました。
山田 とても面白かったです。ありがとうございました。

撮影・末永裕樹(文藝春秋)
第34回Bunkamuraドゥマゴ文学賞の選評、受賞の言葉はこちら