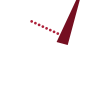2022年10月17日(月)、「第32回Bunkamuraドゥマゴ文学賞」授賞式が、オンライン同時配信のもと執り行われました。受賞作は、06年にデビューし、09年『月食の日』、18年『雪子さんの足音』で芥川賞候補となった木村紅美さんによる『あなたに安全な人』(2021年10月/河出書房新社刊)。海難事故による少年の死に苦しむ女と、沖縄新基地建設反対デモ警備中の出来事を思い詰める男が、新型コロナ「感染者第一号」に怯える地で出会ったことで生まれる、内への逃亡生活を描いた小説です。
選考委員は、日本文学者のロバート キャンベルさんが務めました。授賞式では「近所の書店で積まれている本書を見たときに、『タイトルがおかしいな』と思ったんです。間違っているということではなく、安全な場所とか、安全な時間といった使われ方が一般的なのに、人が安全であるとはどういうことなのかと。逆説的に考えさせるタイトルだなと手に取りました」と、まず本書との出会いに触れたキャンベルさん。
そこから「非常にクリアな短い文で区切られていて、ひとつひとつモザイクを張っているように物語が運ばれていきます。この時代、安全ではない社会の状況で、危険を向けている存在がなんなのか、どこにあるのかが見えない。漠とした不穏といったものが、理屈ではなく、文章そのものからこぼれている、溢れているようなものとして吸い込まれていきました。今年に入り、新たな世界状況のもとで読み直したところ、昨年読んだときとは違う景色が見えました。音楽でも絵画でもそうですが、優れたものは、再び出会ったときに異なる景色、問いかけを自分に突き付けてきます。本書もそうした力を持った小説だと思います」と受賞作を称えました。
「憧れの賞のひとつでした」と口を開いた木村さんは、「キャンベルさんのお言葉を聞いて涙が出そうになりました。どうして目に留めていただいたんだろうと思っていたのですが、このタイトルを付けてよかったです。『世界を覆うインバランス(不均衡)に声と形を与えようとしている』と選評をいただき、非常に感激しました。この作品を出発点にして、もっと大きな小説もこれから書けるようになりたいと思えるきっかけになりました」と語りました。

そして続いて行われた記念対談では、「見事な布石があったり、構造的にもとても丁寧に面取りされている」と感服するキャンベルさんに、「プロットを立てたことがない」と木村さんが驚きの執筆法を明かしました。
==
キャンベル:まずこの物語はどうやって生まれていったのでしょう。
木村:コロナ禍に書いてはいるのですが、もともと私が2018年の12月に沖縄の辺野古に座り込みに行った際に、機動隊員に体を持ち運ばれるという経験をしまして。そこで暴力を振るう側の視点で小説を書きたいと思ったのが最初のきっかけでした。そして暴力を振るった記憶で苦しんでいる男と対比させて、誰かを非常に傷つけて死に至らしめたかもしれないと悩んでいる女を出そうと。私は林芙美子の『浮雲』とか、韓国のハン・ガンの『ギリシャ語の時間』といった小説が好きなんです。男と女が一緒にいても違うものを見て考えていたりする、そうしたズレがきっかけで読む人を引き込む小説を書けるんじゃないかなと、今回このような形式に挑戦しようと思いました。ただそのふたりをどうやって繋げるか見えていませんでした。2020年の10月末に東京から盛岡の実家へ引っ越したのですが、コロナ禍の初期に、東京から移住した方が謎の焼死を遂げた事件が起きました。事件がヒントになって、ふたりの媒介となる設定が浮かんでいきました。

キャンベル:木村さんは、ご自身がされたことを反転させて、加害者といいますが、そちらの視点に溶け込ませたわけですが、今お話しにあったように、女も登場します。立ち位置のくっきりした語り手がいるわけではなく、男と女それぞれに寄り添って語られていきます。その流れが縫い目なく、ふたりの固有性を超えながら進んでいく感じがしました。そうした構想は、緻密に組み立てていくのか、ある日突然降りてくるのか、あるいは確信がないままに書き始めるのでしょうか。
木村:確信のないままです。私の場合は、プロットを立てて書くということをしたことがないんです。小説ってある一行を書いて次の一行に行くときに、無限に選択肢があると思うのですが、その一文でのベストの展開というのが必ずあるはずなんです。けれどそこに気づくのにすごく回り道をするんです。まっすぐ書けるときもあるんですけど、間違いの繰り返しで、5番目くらいにやっとうまくいくといったことを積み重ねています。何度も書き直しをして、やっと最初の30枚ぐらいができて、さらに30枚くらい書くと、最初のほうの問題点にぶつかって、またそこから書き直す。全体ができあがってから、ここずれてるなと気づくこともあって、そうするとまた何十枚も削ってまた書き直して、そうした繰り返しです。

キャンベル:では、どう終わるかということも。
木村:はい。たどり着くまでわかりません。
キャンベル:それは不安ではないのですか?
木村:初稿を書き上げるまでは常に不安でいっぱいです。書いたものを編集者に読んでもらって書き直すのですが、私は書き直しの作業が好きなんです。迷走しているものを、人に読んでもらうことで、自分が書きたいものにたどり着いていくのだと思います。
キャンベル:本当に見事な布石があったり、構造的にもとても丁寧に面取りをされたりしているようにしか思えませんが、そうして迷いながら掴む手ごたえによって掘り出されているんですね。ところでいまコロナ禍ということで、周囲の人から、「キャンベルさんは、勇気づけてくれるような話を選ぶのかなと思っていた」と言われました。確かに、目をつぶるのではなく、痛みや疎外感を緩和するような作品も素敵だなと思っていました。一方で私は、その中心に向かっていくものもありだと思っていました。木村さんの小説は紛れもなく後者ですね。魚雷のように。現在、コロナだけではなく、さらに大変な世の中になっていますが、まさにこの物語は、読み進めるにつれどんどん深いところに入っていく。希釈のない濃厚な内容です。書く際に、時代の濃度について意識的に考えているのでしょうか。
木村:沖縄の座り込みに行ったりもするとお話しましたが、意識しすぎても書けなくなる気がするんです。というか、シュプレヒコールみたいな小説は絶対に書きたくないという気持ちがあります。この小説でいうと、私は抵抗運動に加わって、持ち運ばれた側ですが、そのまま基地反対といったストレートなものを書くことは、私は小説という表現では避けたいんです。小説はもっと自由だし、いろんな要素を含んでいいものだという気持ちがあるので、意識はしても意識しすぎないように書くということを考えています。そのバランスが難しいんですけどね。
写真:大久保惠造 文:望月ふみ