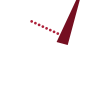2021年12月13日(月)、『ドゥマゴサロン 第20回文学カフェ』を開催。初めての自伝的エッセイ『父のビスコ』を発表した平松洋子さんと、日本におけるサウナ史をまとめた『日本サウナ史』を上梓した草彅洋平さんが登壇しました。
「自然、デザイン、サウナ…フィンランドに学ぶ幸福のヒント」をテーマに、2022年1月30日(日)までBunkamuraザ・ミュージアムにて開催していた『ザ・フィンランドデザイン展』の感想を皮切りに対談をスタートさせたおふたり。フィンランド人にとってなくてはならないものであり、草彅さんの得意分野である「サウナ」について、熱く、楽しく語り合いました。
◆フィンランドのデザインの在り方は日本の民藝と似ている
 平松洋子(以下、平松):さきほど『ザ・フィンランドデザイン展』を見てきたのですが、やはりフィンランドは奥深いと実感しました。テキスタイルにしてもガラスにしても陶器や磁器にしても、すべてが有機的なものと繋がっていることを再確認して、じつは日本の民藝の在り方と相通じていると思ったんです。
平松洋子(以下、平松):さきほど『ザ・フィンランドデザイン展』を見てきたのですが、やはりフィンランドは奥深いと実感しました。テキスタイルにしてもガラスにしても陶器や磁器にしても、すべてが有機的なものと繋がっていることを再確認して、じつは日本の民藝の在り方と相通じていると思ったんです。
表現の仕方は全く違うように見えながら、その根本にいずれも天然、自然の存在がありますね。
草彅洋平(以下、草彅):僕は実はもともと家具屋で働いていたので、今回の展覧会はエモい気持ちで見てました。それから改めてフィンランドのデザインの発展には、1952年のヘルシンキオリンピックがすごく重要だったんだなと感じました。
平松:そうですね。そしてフィンランドという国を考えると、戦争の歴史が大きいです。内戦もありましたし、なにより厳しい冬をくぐり続けてきた。
フィンランドといえばやっぱり「サウナ」ですが、草彅さんはフィンランド政府観光局公認のフィンランドサウナアンバサダーでいらっしゃるんですよね。
ご著書の『日本サウナ史』がすばらしくて、2021年の3冊を選べと言われたら絶対に入れます。
草彅:めちゃくちゃ嬉しいです。サウナアンバサダーは現在、何人いるのか分かりませんが、良かったのは、フィンランド大使館のサウナに入れたことです。
平松:大使館のサウナ!いわば聖域ですね。私は4年ほど前に初めてフィンランドでサウナに入りました。
草彅:2月くらいの寒いときに行かれたとか。
◆初体験のフィンランドサウナでビックリ

平松:大寒波が来ていてマイナス20℃くらいになりそうだと言われてたんですけど、実際にはマイナス5℃くらいでした。雪に覆われていて、朝8時半過ぎても暗い。
フィンランドの方たちは、こうやって長い冬を暮らしているんだなと体感しました。
私は旅に行くと課題をひとつだけ決めるのですが、フィンランドでは「1日1サウナ」。
スポーツセンターや市民が行くジム、ホテルのサウナ、100年ぐらい続いている老舗サウナ、大きなプールが併設されているところとか、色々行きました。
草彅:フィンランドは人口550万人くらいですが、300万以上、一説には350万くらいのサウナがあるんです。つまり、めちゃくちゃ多いんですね。
平松:そこで「コティハルユ」ってところに入って。
草彅:ヘルシンキにある一番古いところですね。みんなで裸で外気浴する。
平松:そうなんですよ!路上でおじいさんたちが上半身裸でビールを飲みながらワイワイやってて。最高ですよね。
草彅:めっちゃ、かっこいいです。
平松:日本の昔ながらの銭湯に似た雰囲気もあって、番台があって脱衣所があって。なんとなく内輪のルールみたいなのがあるのも似ている。ただ湿度計などはないですね。
草彅:ないですね。テレビもないですし。というかテレビは日本だけですね。
平松:あと市営の大きなプールのあるところで、初めてプールで裸で泳ぎました。
草彅:たぶん映画『かもめ食堂』に出てきたプールですね。男女入れ替え制なんですよね。
平松:そうなんですけど、裸で平泳ぎをしていて、息継ぎのときに顔を上げたら若い男性の監視員さんが目に入って。「ええー!」ってビックリ。おおらかというか、フィンランドの人たちってユニークだなと思いました。
◆フィンランドでは家を建てるとき、最初にサウナを作る
 草彅:フィンランド人にとってサウナは機能的な意味を超えて、精神的にすごく大切なものなんですよね。
草彅:フィンランド人にとってサウナは機能的な意味を超えて、精神的にすごく大切なものなんですよね。
すごく簡単に説明しますと、サウナとはくぼんだ土地という意味なんです。フィンランドは寒さが厳しくて、凹んだ暖かい場所に住居を構えてきた。そこで赤ちゃんが生まれ、人が死んでいく。家を建
てるときに、最初にサウナを作るんです。サウナを作って温めてから母屋を建てる。それくらいフィンランド人にとって大切な場所なんです。
平松:出産の場であり、亡くなったときの清めの場であり、社交の場でもあり、一生がサウナと密接につながっている。それからなぜあんなに広いプールがあるんだろうと自分なりに考えて、これは湖なんだなと理解しました。
草彅:おっしゃる通りです。日本は自然にも権利があって、海の上の権利とか、湖上権とかがありますが、フィンランドでは自然は国民のもので、どこの湖でも飛び込めるんです。
フィンランドのサウナに水風呂が少ないのは、そのためです。だからプールはまさにその通り、湖です。
◆サウナと水風呂を初体験した日本人はアスリートだった
平松:『日本サウナ史』を拝読して興味深かったのが、日本人で最初にサウナに入ったのがアスリートだったという事実です。
草彅:日本にどうサウナが入ってきて、どう定着していったのか僕も分からなくて、調べまくって書きました。
20世紀頭のころ、フィンランドはオリンピックでめちゃくちゃ強くて、花形の陸上でアメリカと対等に戦って金メダルを独占してたんです。日本は1912年のストックホルムオリンピックに、三島弥彦さんと金栗四三さんが出場しましたが、ボロ負けでした。
平松:日本人金メダル第1号は織田幹雄選手(1928)ですが、織田さんは、日本人で初めて水風呂を体験して、いわゆる“ととのう”記録を残した人だったと。
草彅:僕調べですけどね。
平松:織田さんの文章も『日本サウナ史』に収められてますが、オリンピックとサウナの関係しかり、その後の発展についても、この本を読んでいるとたくさんの驚きや発見があります。
草彅:ありがとうございます。サウナってハマっちゃうと本当にすごくて、果ては僕みたいに自費出版するまでになるわけですが(苦笑)、いまサウナブームだとか言われてますけど、僕にしてみたら、ずっとブレイクが続いているカルチャーだと思います。
◆外気浴で“ととのう”深~い理由とは

平松:ちなみに“ととのう”という状態とは。
草彅:サウナっていうのは死のゲームなんです。健康にいいと言われていますが、いきなり温めて次は冷たくしてって、めちゃくちゃですよね。結構激しい遊びなわけです。
命のギリギリのところにいる。火事から逃げたら水風呂だったみたいな仮想空間ですから。体験したことのない落差を作ることによって、脳がバーストすると。
そして外気浴することでいろんな物質がどば~っと出て、サウナトランスとか、“ととのう”状態になる。
平松:やっぱり外気浴まで含めた3段階が必要なんですね。
草彅:そうです。サウナ入って水風呂入って、またサウナの繰り返しじゃなくて。
それだと死を繰り返してるだけですから。外気浴でなぜととのうかというと、「助かった」ってことなんです。2回の壮絶な死から命カラガラ逃げて、「助かった~」というのが“ととのう”なんです。
平松:草彅理論(笑)。
草彅:でも全然フィンランドスタイルじゃないですけどね。フィンランドに行って、バンバン水を浴びてると、止められますから。フィンランドの人には怒られると思います。
平松:日本は外国のものを取り入れて、独自に発展させていくのがお家芸ですからね。『日本サウナ史』、ぜひ読んでもらいたいです。
草彅:すみません。『父のビスコ』のお話しが全然できませんでした。
平松:いえいえ、熱く語っていただけて良かったです。サウナだけにね(笑)。
写真・構成:望月ふみ