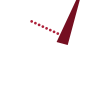第28回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞者 九螺ささら
鋳型と鋳物の関係というものを、わたしはよくイメージする。影響とか、環境とか、関係とかといったものを考えるときに。
部屋は人の鋳型だと感じる。人は部屋の鋳物だと思う。だから、どういう部屋で生きるかが、その人を決める。
Bunkamuraドゥマゴ文学賞の副賞として、パリのドゥマゴ賞授賞式への招待をいただいた。滞在したホテルの部屋に、わたしは感化された。人間関係でいうなら、愛された。わたしは愛を受け止め、受け入れ、その愛に応えた。つまりできるだけそこにいた。存在同士で限られた時間を共有するのが愛だと思うから。
ああ、ここに電気ポットか。ああ、ここにコンセントがある。 なるほど、この重く厚いカーテンはほとんど完全に遮光できるんだ。でもビニールじゃない。縦糸と横糸があるから。重いカーテンを開くと、ああ、窓いっぱいにサン=ジェルマン=デ=プレ教会が見える。「我思う故に我あり」の言葉を遺したデカルトが眠る教会だ。教会だけを、天井までの窓が風景として切り取っている。ぴったりだ。ちょうどぴったり。画家がアングルを決めたみたいに、窓から教会がはみ出てもいないし空が余分でもない。一幅の絵だ。
なるほど、この重く厚いカーテンはほとんど完全に遮光できるんだ。でもビニールじゃない。縦糸と横糸があるから。重いカーテンを開くと、ああ、窓いっぱいにサン=ジェルマン=デ=プレ教会が見える。「我思う故に我あり」の言葉を遺したデカルトが眠る教会だ。教会だけを、天井までの窓が風景として切り取っている。ぴったりだ。ちょうどぴったり。画家がアングルを決めたみたいに、窓から教会がはみ出てもいないし空が余分でもない。一幅の絵だ。
『フランダースの犬』のネロが死に際にやっと見ることができた、アントワープ聖母大聖堂のルーベンスの絵のことを思い出す。それまで絵を覆っていたカーテンが、画家になりたかったネロの臨終を知ったかのようにその日はめくれていて、ネロはお金がなくて見られなかった憧れの絵を見てから死ねたのだ。
これは運命の部屋だ。
ここにいたい。
部屋には天使役のメイドもいた。彼女と目が合ったとたん初対面なのに懐かしく、ずっと会いたくて仕方なかった人がどうしてここにいるんだろうと狼狽した。
「あなたの名前は何ですか?」
わたしは、掃除道具のワゴンを押している彼女に英語で聞く。彼女は微風のようなフランス語で、自分に付けられた名を発音する。
「わたしはあなたが好きです」
わたしは英語で告げる。彼女は目を細めて微笑し、わたしの名前を聞く。わたしはわたしに付けられた名を発音する。
ベッドメイクされたシーツをはがし、わたしはスプリングを確かめる。沈みすぎもせず、硬すぎもしない。ちょうどぴったりだ。わたしはベッドに身を委ねる。深海魚のように、わたしは深く眠れた。眠っているあいだに、生きてきたこれまでの時間が、過去が、記憶が、すべて洗われた。目覚めるたびに、生まれ変わったみたいに本質的に元気になった。
ライトが、然るべき場所に然るべき光量で灯る。水と湯が、然るべき水量と温度で流れる。わたしの動線が滞るその場所にスツールがあり、わたしが考える場所にライティングデスクがある。バスタブは裸体の鋳型だ。バスタオルとバスローブが、恋人のようにそこにいる。部屋の何もかもが、わたしの少し先で待っている。またはわたしの少し後に付いてくる。運命みたいに。
できるだけ部屋と一体化していたくて、わたしはほとんど観光というものをしなかった。どこに行くより、その部屋にいることが心地よく、気付きになり、成長になると感じられた。この部屋が、少し先の理想の自分を叶える鋳型だ。この環境を、体にダウンロードしなければならない。
わたしは「Don't disturb」のカードを掛け続け、部屋との蜜月を過ごした。
チェックアウトする際に、ライティングデスクのメモに「merci」と書いた。「i」の上の「・」をハート形にして。わたしから部屋への、書き置きだった。
石畳の道は昨夜の雪が染みて色が濃くなっている。ホテルとサン=ジェルマン=デ=プ レ教会のあいだに哲学者ドニ・ディドロの全身像がある。そこからカフェ・ドゥマゴが見える。サルトルがこの石畳を歩いてドゥマゴに通ったのだろう。実存主義を唱えながら、ボーヴォワールと愛し合ったのだろう。「もし神がいないなら、実存は本質に先立つ。それが人間だ。希望は行動の中にしかない」。サルトルは昼間そう訴えながら、夜はこの街のどこかでボーヴォワールを抱いていたのだろう。
レ教会のあいだに哲学者ドニ・ディドロの全身像がある。そこからカフェ・ドゥマゴが見える。サルトルがこの石畳を歩いてドゥマゴに通ったのだろう。実存主義を唱えながら、ボーヴォワールと愛し合ったのだろう。「もし神がいないなら、実存は本質に先立つ。それが人間だ。希望は行動の中にしかない」。サルトルは昼間そう訴えながら、夜はこの街のどこかでボーヴォワールを抱いていたのだろう。
石の街の随所に、神としか言いようのないものの気配を感じる。アスファルトとコンクリートの街には感じないもの。石畳や石壁のひとつひとつの石がそのまま、侵しがたい「尊厳」や「存在」という言葉のようだ。わたしは何度も、その石壁を触る。神の肌を確かめるように。存在というものを確かめるように。
帰宅したわたしは、鋳物として、鋳型の感触を忘れないうちに鋳型を再現しようと思った。その、鋳型と鋳物のあいだの輪郭が、愛だから。
あのホテルの部屋の電気ポットに似た電気ポットを買い、あのホテルの部屋のベッドカバーに似たベッドカバーを買い、あのホテルの部屋のスツールに似たスツールを買い、あのホテルの部屋のバスローブに似た肌触りのバスローブを買った。わたしの部屋は日ごと、あのホテルの部屋に似てゆく。そしてわたしの手のひらには、あの街の石壁の感触が甦る。
わたしの手のひらとあの街の石壁。あの街では石壁が鋳型で、わたしの手のひらが鋳物だった。
鋳型を失った今、わたしの手のひらが鋳型になる。
わたしが何か摑もうと手のひらを窪ませると、そこに神が、尊厳や存在という言葉が鋳物として宿る。神や尊厳や存在はこの世のどこにでもある。神や尊厳や存在がそのままこの世と言ってもいい。
信じる場所に、それらは象られ、宿る。そして信じる存在と信じられる存在のあいだに、愛という輪郭が生じる。
わたしの手のひらに、あの街の石壁が甦る。雪が染みていて、濡れながら硬く、鉱物特有のざらつきがある。この惑星の実存的なざらつきだ。
甦るたびに、わたしの手のひらは尊く、湿って温かくなる。その手のひらでコーヒーカップを包む。未知の生物が育つかのように、カップの中から湯気がのぼる。