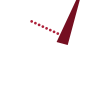この秋、フランスは政治危機が最高潮に達した。10月6日にはルコルニュ首相が就任からわずか一カ月弱で辞表を提出し、内閣は総辞職へ。恒例のドゥマゴ賞の授賞式は、ちょうど同じ日に催された。国の混乱を横目に、秋の陽光が降り注ぐサン=ジェルマン=デ=プレの老舗カフェでは、文学愛を分かち合う穏やかな時間が流れていた。
正午過ぎ、すでに会場では9人の審査員が中央の席で審議中。その周りを、カメラを構えたジャーナリストがぐるりと取り囲む。壁の上方には、店名の由来となった木製の中国高官像二体(ドゥマゴ)が鎮座し、賞レースの行方を厳かに見守っている。

第92回ドゥマゴ賞の最終候補は4作品。行方不明となったイラク人飛行士の叔父に思いを寄せるフラ・アラニの自伝風ドラマ『Le ciel est immense (空は広大だ)』(JC Lattès社)、異教徒夫婦が子供の暴力に直面するルーシー=アンヌ・ベルジーの初著作『Il pleut sur la parade (パレードに雨が降る)』(Gallimard社)、女性が人魚に扮してスペクタクルを披露するジョゼフ・アンカルドナの小説『Le monde est fatigué (世界は疲れている)』(Finitude社)、子どもを失った40代カップルが旅をするヴィクトル・プーシェの愛と喪失の物語『Voyage voyage( 旅、旅)』(Gallimard社)だ。
ほどなく審議は終了し、マイクを握るエティエンヌ・ド・モントティ選考委員長が立ち上がった。「本日、フランスは政府が存在していません。しかし、ドゥマゴ賞の審査員たちは投票のために働いてます。 2025年のドゥマゴ賞はジョゼフ・アンカルドナの『Le monde est fatigué』となりました」。周囲からは温かな拍手と「ブラボー!」の掛け声。国の混乱に乗じたユーモア交じりの挨拶に、フランス的エスプリ(機知)も感じさせるひとコマだった。

『Le monde est fatigué』の主人公は、轢き逃げ事故で両足を失った女性。下半身をシリコン製の尻尾に変え、“プロの人魚”となる。復讐心を胸に抱えながらジュネーヴ、パリ、東京、ドバイなどでスペクタクルを披露するという寓話的な物語である。
本作は『Voyage voyage』と最後まで賞を争った。だが、伝統的なルールに則り、接戦の際に2票分の投票権を持つド・モントティ選考委員長が最終判断を下した。「今回は特にフィクションを生み出す作家の豊かな創造性を賞賛したかったのです。現代社会の厳しさや暴力性までドラマに刻まれていたのも見事でした」。
フランスでは8月中旬から約2カ月間を「Rentrée littéraire(文学の新学期)」と呼び、出版社は新刊を集中的に販売。その動きと連動しながら、ゴンクール賞やルノドー賞などの主要文学賞が次々と発表される。選考委員長によると、今年の「文学の新学期」における大きな潮流は「家族」。エマニュエル・カレール、アメリー・ノートン、ローラン・モーヴィニエら有名作家も、こぞってこの流れに乗っていたという。「今年はとりわけ父や母を描いた作品ばかり。しかし、『Le monde est fatigué』の受賞で、ドゥマゴ賞の個性がより強調できたと自負しています。そもそも “人魚”が登場する文学作品は、ホメロスやアンデルセン以降、あまり登場してこなかったのでは」。

著者のジョゼフ・アンカルドナは1969年生まれ。スイス人母とイタリア人(シチリア)父を持つ。ジュネーヴを拠点に、これまで約15冊の小説や短編集を発表。漫画やテレビ、演劇の脚本も手がけ、映画監督の経験もある多才な人物だ。
会場に上機嫌で姿を現したアンカルドナ氏に、受賞への思いを伺った。「カフェと賞の歴史に重みを感じられ大変光栄です。ドゥマゴ賞はマージナル(周縁的)な存在に光を当てながら、新しい価値を提唱し、名誉を与えているのが素晴らしい。真の読書家である審査員はしがらみに囚われず、自由な選択ができたと思います。最高に美しい日となりました」。ちなみにアンカルドナ氏の息子は熱狂的な親日家であり、現在日本語を勉強中だと楽しそうに教えてくれた。本作の舞台に東京が登場するのは愛息の影響もありそうだ。
アンカルドナ氏の指摘通り、ドゥマゴ賞は1933年の創設当初から、文学における新しい価値を提唱し続けてきた。今回、受賞作の版元となったFinitude社は、2002年にボルドーで誕生した小さな独立系出版社。老舗のGallimardや仏最大の出版社Hachette系列のJC Lattèsなど、大手発のライバル作品を抑えての受賞は注目に値する。作家のみならず、マージナルな出版社にも花を持たせることができた意義深い回となったようだ。

写真・文:林瑞絵(在仏映画ジャーナリスト)