
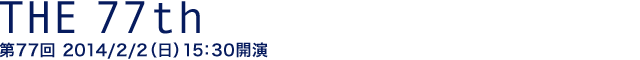
イギリス在住のピアニスト、小川典子さん。2013年には、ロンドンの夏の風物詩として人気の高い伝統ある「プロムス」にデビューした。彼女がアドヴァイザーを務めるミューザ川崎シンフォニーホールでそのあたりのお話からきいた。(2013年9月1日)
7月31日にBBCのプロムスに出演されたとききました。いかがでしたか?
「プロムスはすごく楽しかったです。今回初めて出演し、私も2013年のデビュー・アーティストの写真の一枚となりました。独特の雰囲気で舞台裏までお祭ムードで盛り上がっています。BBCのラジオでは出演者のインタビューを流すのですが、私と共演者のキャサリン(・ストット)との楽しいインタビューも放送されました」
プロムスでは何を演奏されたのですか?
「イギリス音楽の夕べで、私たちは、マルコム・アーノルドの《3手のためのピアノ協奏曲》を演奏しました。2台のピアノで、一人が右手、もう一人が両手で演奏します。私は両手のパートを弾きました。イギリスのピアニスト、シリル・スミスの左手が使えなくなったとき、友人のアーノルドが、スミスと彼の奥さんのために書いた曲です。技術的に難しいところがあるのですが、本番が一番うまくいってハッピーでしたね」
今回のN響オーチャード定期では、ラヴェルのピアノ協奏曲を演奏されますが、この作品をどのようにとらえてられますか?
「細部にわたって凝りに凝っている曲です。スローモーションで弾いた方がいいかなと思うほど、細部の細部まで趣向を凝らしています。チャイコフスキーなどの大ピアノ協奏曲に比べると、小ぢんまりとした印象を受けるかもしれませんが、書かれ方が他の協奏曲と激しく違います。私は、協奏曲では第1ヴァイオリンを頼りに演奏することが多いのですが、ラヴェルのピアノ協奏曲では、第1ヴァイオリンがメロディを歌うことは少なく、代わりに管楽器との掛け合いが多く、初めて演奏したときはすごく戸惑いました。オーケストラからピアノへ、ピアノからオーケストラへのバトンタッチが絶妙なのです。ピアノとオーケストラが主従の関係ではなく、大規模な室内楽のように、お互い組み合わさっている協奏曲です」
小川さんは、ドビュッシーのピアノ作品全集の録音をされていますね。同じフランス音楽でも、ドビュッシーとラヴェルはどのように違いますか?
「ドビュッシーもラヴェルも"水の精"をテーマにした曲を書いていますが、ドビュッシーが若干楽観的で健康的なのに対して、ラヴェルは、どこかに死の香りがあり、薄気味悪い部分がついてまわります。そして物悲しさがあります。ピアノ協奏曲の第3楽章は明るいですが、第2楽章は、ピアノの楽譜で1ページ以上、右手と左手が違う拍で進んでいく、ゆったりとしたワルツのような音楽。音の数は最小限まで削ぎ落とされて、1ページかけてクライマックスに持っていき、ピアノがオーケストラとともに絶叫する。そのあとのイングリッシュホルンとピアノには安堵感とともに物悲しさがついてまわります」
今回のNHK交響楽団との共演については、いかがですか?
「N響と最初に共演したのは、『若い芽のコンサート』で、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を弾きました。その後、演奏旅行でリストのピアノ協奏曲第1番を共演したこともあります。N響の印象は、音が引き締まっているということ。ラヴェルのピアノ協奏曲は、管楽器の個人芸がものをいい、楽器から楽器へと受け渡していく曲なので、とても楽しみにしています。細部まで凝りに凝ったこの曲を最良に演奏できるN響と共演できるのは幸せです。高関(健)さんの棒はこういう作品には最適です。楽譜の読みが深く、どうリードしてくださるのか楽しみ。オーチャードホールで弾くのは、東京フィルの定期演奏会(2008年6月)でのシューベルト(リスト編曲)の《さすらい人幻想曲》以来ですね」
小川さんは、イギリスのギルドホール音楽院の教授を務めるなど、後進の指導にも熱心でいらっしゃいますね。
「教えることは時間のかかる作業なので、私のやりたいことの半分しかできていません。でも、この間の学年末試験で成果が表れ、本当にうれしく思っています。毎週見られるわけではないので、1コマ2時間、学生がくたくたになるまで見ます。最近は私と勉強したいという学生が入ってきて、私のクラスという感じになってきています。若い人たちには私のもっているものや思いを伝えたい」
アドヴァイザーを務めてられるミューザ川崎シンフォニーホールでも子供のためのコンサートをされていますね。
「子供たちの演奏を聴く姿勢が素晴らしく、続けると確実に定着するものなのだと、こっちが感動しました。音楽会の聴き方でも子供たちは育っていくものだと勇気づけられて、また続けようとみんなで話し合いました」
インタビュアー:山田治生(音楽評論家)