Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第25回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

武田砂鉄 著
『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』
(2015年4月 朝日出版社刊)
| 選 考 | 藤原新也 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |
| 授賞式 | 2015年10月19日(月) 於:Bunkamura
当日開催された授賞式の模様を動画でご覧いただけます。 |
受賞者プロフィール

武田砂鉄(たけださてつ)
1982年生まれ。ライター。東京都出身。大学卒業後、出版社で主に時事問題・ノンフィクション本の編集に携わり、2014年秋よりフリーへ。「cakes」「CINRA.NET」「SPA!」「Yahoo!ニュース個人」「beatleg」等で連載を持ち、多くの雑誌、ウェブ媒体に寄稿。インタビュー・書籍構成も手掛ける。本作が初の著作となる。

藤原新也(ふじわらしんや)
福岡県門司港出身。
写真家・作家。
東京芸術大学油画科を中退後、インドを中心として世界を放浪。
著書に「インド放浪」「全東洋街道」「東京漂流」「メメント・モリ」「乳の海」「アメリカ」「コスモスの影にはいつも誰かが隠れている」など多数。
受賞の言葉
言葉はニンゲンが食わないといけない / 受賞者 武田砂鉄
偏屈な性分だから、書店で『伝え方が9割』というビジネス書のベストセラーを見かけると、9割の詳細など放って、残りの1割は何なのだろうかと考え始める。手土産のチョイスだろうか、今年の流行色をさりげなく取り入れた服装だろうか。それとも、話の中身も少しは問うてくれるのだろうか。
万事は10割になり得ないと思っている。どこかしら余白がある。いや、余白なんてない、と言い張る誰かが現れても、オマエの規定した10割は本当に10割か、とその枠組に疑いを向けていく。選挙で信任されたので好きにやらせてもらいます、と享楽的に暴走する昨今の政治は、過半数さえ手にしてしまえば「オレたちのやり方が10割」と勘違いし始めるけれど、たとえ9割が信任していても、まだ1割が残っているのである。
「残りの1割にも寄り添え」と嘆願することが、暑苦しい、偽善じみていると判断されがちな世相にある。冷静に諦めることが世の中に対応していくことだと信じ込んでいる人たちは、国の中枢に向かう必死な声を「対案もないくせに反対を連呼していたって仕方がないじゃないか」と冷笑する。
知っていることの補強ばかりしていると、知らないことを蔑むようになる。伝えるテクニックばかり鍛えていると、伝わらないことを軽視するようになる。言葉がいくらだって氾濫しているが、そこに流れる言葉が、いたずらに補強を繰り返すなかで絞られ、利便性の高い言葉だけが採用されている。就職活動で好印象を与える面接の答弁を指南するかのように、この場面ではこういう言葉を投じるのがベスト、と誘(いざな)う働きかけが、日々のあらゆるところで点在している。
今回の本では20のフレーズをあげ、その働きかけに満ちる不快の正体を抉(えぐ)り出してみた。ありきたりの言葉が、その奥にある思考を塞き止めてしまうような社会はつまらない。この言葉を使ってはならぬ、と言葉狩りを提唱したわけではないのだが、使ってはいけない日本語を羅列した本、と捉えられた機会が少なくなかった事実は、まさしく現代を流れゆく言葉が、いつだって効率性を問われていることを明らかにしてくれた。
志望動機を端的に答えられなければ入社への道が開けないように、効能が端的に定まっていなければ言葉を投じるべきではないと思い込まされている。だからこそ、過半数を得た言葉、賛同を得られる言葉ばかりを探ってしまう。本来、言葉は、どこでどんな勢力で流れているものであろうとも、自分のものとして咀嚼し直すことができる。要らなければ、吐き捨てることもできる。
高校時代、自転車通学だった自分は、大通りに面する巨大な古書店へ毎日のように立ち寄った。週に1度か2度、弁当箱ではなく、親から500円玉を渡され、学校の購買でパンを買っていた。パンを2つか3つ買い、その差額を貯め込んで、古本屋の値札とにらめっこした。藤原新也さんの『メメント・モリ』もその1冊だった。開くと、人を食らう犬の写真に「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」という言葉が添えられていた。この言葉を、家の本棚に連れ帰ってみたいなと思った。しばらく、500円玉を渡されるたびにパンの数を減らした。
私たちは、どこまでも自由を許されている。それなのに、みんな、誰かと一緒であろうとする。出来合いの絆を確かめるように、あの人とは違うよね、と排他することで認め合いを得る。自由を自ら手放し、凝り固まっていく。ニンゲンは犬に食われるほど自由だってのに。
犬が食えないのは言葉。やっぱり、言葉はニンゲンが食わないといけない。とりわけ今、それを怠ると、たちまち「権力の犬」になる。そんな紋切語をこれ以上使うのは、犬に失礼だろう。人間が自由を保ってきたのは、「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」と言い放つための言葉を保ち続けてきたからではないか。言葉のバリエーションを持たない権力者が「日本を取り戻す」と繰り返すならば、こちらは言葉を取り戻さなければならない。
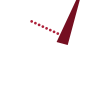















選評
「文化人類学的ジャーナリズムという新しいジャンル。」/ 選考委員 藤原新也
香水ソムリエの前で香水のブレンドをしたことがある。七種類の異なる香水を嗅ぎながらその中から選んだ三種類の香水をブレンドし、独自の香り高き香水を創り出すという趣向だが、当然人は自分の好みの香りの三種の香水をブレンドする。私も好みの三種の香水を選んでブレンドしようとしたが、待てよと思いとどまった。過ぎたるは及ばざるがごとし、という諺が頭を過ったのだ。そこで考えを変え、七種の香水の中で一番自分の好みでない香水を選び他の好みの二種とブレンドしたところ、ソムリエはニヤッと笑んで頷いた。
どうやら香水のブレンドというものは一筋縄ではなく、いやな香りをブレンドすることでなお一層香りが引き立つという鉄則があるらしい。
今回ドゥマゴ文学賞の選考をするにあたって、私はあの香水ブレンドの折の方法に倣った。自分好みではない作品をも含め多数の候補作から絞り込んだ七点を同時に読み合わせることによってより客観的視点をもたらしてくれると思ったからだ。
その結果最終的に選んだのが武田砂鉄『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』(2015年4月 朝日出版社)となる。
私はこの本を読みながら昔読んだレヴィ・ストロースの『悲しき熱帯』やマルセル・モースの『贈与論』のことが脳裏を過った。『紋切型社会』とその書籍の内容のどの部分がリンクしたということではなく、おそらくこの本をカテゴライズするとするなら新しい意味でのジャーナリズムであるとともに文化人類学の範疇に入るものだろうとの思いを抱いたからだ。
昨今気象異変によって日本は亜熱帯化してきているという。
その意味において『紋切型社会』は日本の言語環境における“悲しき熱帯”なのである。
ここには形骸化した常套句によって成り立つ社会のさまざまなシーンが描かれているが、思うにそれが“悲しい”のは世界の国々において日本ほど“気持ち”の介在しない形式化した言語が人と人との間のコミュニケーション(合意)として流通する国はないと考えるからだ。
たとえば東日本大震災以降“絆”という言葉が世間を席巻したが、思うに震災前に世間に流布していた言葉は“無縁社会”だった。つまり絆という言葉の内実は無縁であり、絆という紋切り型言語によるネゴシエーションによって構成される社会はそこに関係性や心が欠損していると言える。
そのような意味において紋切り型社会と逆対象と言えるのが本書の中の一篇「もうユニクロで構わない」の中に取り上げられているアマゾンの原住民ピダハンだろう。ピダハンの研究者によればこの400名しかいない部族のボキャブラリーは極めて限定されている。
しかし言語が限定されているということは貧しいのではなく、豊かだからである。彼らはおそらく言語ではなく“集合的無意識”というもっとも深いところで結びついているのであり、言語とはその集合的無意識の導線に過ぎないわけだ。
本書を読みながら豊かさのゆえにいわゆる言葉を持たないピダハンと、紋切り型言語の氾濫によって偽の合意が形成されている極東の島国の間の気の遠くなるような乖離を楽しんだ。