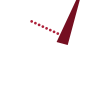去る1月28日(月)、パリ日本文化会館の協力のもと、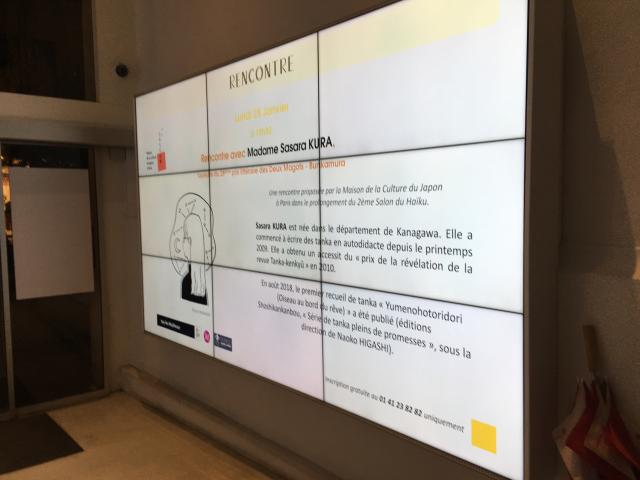 フランス・パリに隣接するイシー=レ=ムリノー市にある文化施設Espace Andrée Chedidにて、第28回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞者・九螺ささら氏を囲んでの交流会が開催されました。
フランス・パリに隣接するイシー=レ=ムリノー市にある文化施設Espace Andrée Chedidにて、第28回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞者・九螺ささら氏を囲んでの交流会が開催されました。
過去にも俳句サロンを開催するなど、日本文学への関心が深い本施設には、20名余りの参加者が集いました。
まず、九螺氏より、日本語の“せつない”という感情は詩の世界における真髄だと語り、フランス語で似た言葉があるのか観客へと問いかけました。参加者からは“spleen(憂鬱、哀愁、嫌悪などの意味を持つフランス語)”、“メランコリー”、“絶望”など、各々が考える単語が飛び交います。続けて、日本人の心情を体現している花“桜”のようなフランス人の感情を代表する植物について教えてもらうと、「コクリコ(ひなげし。美しさと儚さを秘めている)」「すずらん(縁起の良い花としてプレゼントしあう習慣がある)」、「プリヴェール(さくら草。春を告げる花として愛されている)」「楢の木(時を超えて持続していく強さをもつ)」など、個人が抱くイメージが明かされていきます。
また、受賞作『神様の住所』出版のきっかけとなった短歌「<体積がこの世と等しいものが神>夢の中の本のあとがき」を朗読。他にもいくつかの短歌で“神”という単語を使用していることについて、論理的な考えや想像だけでは表現できない部分を“神”という言葉で表し、存在・非存在を考えるよすがとなるようなものを作っていきたいと解説しました。
最後には、以前の俳句サロン参加者から、フランス語の俳句を聞かせてもらいました。音節を考えながら詠む様子は両国共通です。

「裸の木 空は書道のようで 文学(書くこと)へと誘う」
「秩序の正しい街 蝶々でさえも 横断歩道を渡る」 ※いずれも元はフランス語。
1時間余りの会では、活発な意見交換が行われ、終演後もドリンクを片手に、参加者とともに、日本とフランスの文学、精神の違いなどを語らい交流を深めました。