Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第22回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

金原ひとみ 著
『マザーズ』
(2011年7月 新潮社刊)
| 選 考 | 髙樹のぶ子 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |
| 授賞式 | 2012年11月21日(水) 於:Bunkamura
当日開催された贈呈式の模様を動画でご覧いただけます。 また、当日開催された特別記念対談の模様が1月7日に発売された『新潮』2013年2月号に掲載されています。こちらもあわせてご一読ください。 |
受賞者プロフィール

金原ひとみ(かねはら ひとみ)
1983年東京都生まれ。2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞しデビュー。同作品で04年に第130回芥川賞を受賞。10年に『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞を受賞。他の著書に『アッシュベイビー』『AMEBIC』『オートフィクション』『ハイドラ』『星へ落ちる』『憂鬱たち』などがある。
受賞作品の内容
母であることの幸福と凄まじい孤独。
同じ保育園に子どもを預ける三人の若い母親たち―――。
家を出た夫と週末婚をつづけ、クスリに手を出しながらあやういバランスを保っている〈作家のユカ〉。
密室育児に疲れ果て、乳児を虐待するようになる〈主婦の涼子〉。
夫に心を残しながら、恋人の子を妊娠する〈モデルの五月〉。
現代の母親が抱える孤独と焦燥、 母であることの幸福を描きだす。
(『マザーズ』帯文より抄録)

髙樹のぶ子(たかぎ のぶこ)
1946年、山口県生まれ。1980年『その細き道』を「文學界」に発表、創作活動を始める。 1984年『光抱く友よ』で芥川賞、94年『蔦燃』で島清恋愛文学賞、95年『水脈』で女流文学賞、99年『透光の樹』で谷崎潤一郎賞、2006年『HOKKAI』で芸術選奨文科大臣賞、10年『トモスイ』で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『マイマイ新子』『甘苦上海』『マルセル』など多数がある。
受賞の言葉
有限の絶望と瞬間の幸福 / 受賞者 金原ひとみ
友達もいない、言葉も通じない国に来て五ヶ月になる。原発事故以来、岡山に避難していた私は、今フランスにいる。これから先、どこに住むかは分からない。明日にも日本に帰るかもしれないし、来年にはアメリカやシンガポールにいるかもしれない。
去年の三月十一日以来、国と個人の関係や距離、人生の優先順位について意識的にならざるを得なくなった人は多いのではないだろうか。私はその前提を全て見失い、幸せの形、不幸の形さえ掴めなくなった。全てを自分の中で作り直さなければならないと感じていた。震災から一年半、生きた心地がしたことは一度もない。岡山にいた時も、東京に帰った時も、フランスに来てからも、ずっと同じだ。二十九歳になった今、私は今しがた産み落とされた赤ん坊の如く、自分がどこにいるのかすら分からないまま、藻掻き、目を見開き、戦慄き続けている。日本から離れれば、あらゆる意味で解放され、少しずつ世界を取り戻せるかもしれないと思っていた。だが混乱は増し、可能性は狭まり、世界はより曇って見えるようになっただけだった。絶望から始まった生活は、今も絶望とともにある。
今、言葉の通じない国で右も左も分からないまま、私は一人で子供たちを育てている。この子が歩けるようになるとは思えない、と泣きわめく赤子を抱え途方に暮れて一緒に泣いていた、あの時の私の絶望に偽りはない。でもその長女は今、キックボードで走り回り、次女の世話を手伝い、私が泣いているとティッシュを持って来てくれる。今も育児できりきり舞いだが、育児というものに絶望することはなくなった。私は身を以て知っている。絶望は有限だ。あの時々の絶望が「マザーズ」という小説に潜り込み一つの形となってから、私はその絶望を血肉とし受け入れることが出来たように、砕け散った世界はまたいつか、小説の中で世界の体をなすだろう。
八月の肌寒い朝、目覚めてすぐに携帯を開くと髙樹のぶ子さんの選評が送られてきていた。私を叩き起こした二人の子供は既にきゃーきゃー騒いで部屋中を駆け回っていて、私は選評を読むためベビーゲートで区切っているキッチンに入り勝手口から身を乗り出して煙草を吸いながら携帯をスクロールした。すぐに次女がやって来てベビーゲートにしがみつき、がたがたとゲートを揺さぶった。後ろでは長女が大声で歌を歌っている。全く頭に入らず、煙草を吸い終えるとトイレに入って鍵を閉めた。すぐにねえねえママーという長女の声が聞こえた。次女が突然きゃーと怒ったような声を上げ、ああ長女が何か取り上げたんだなと思う。私はトイレで子供たちの声をやり過ごしながら選評を読んだ。涙が溢れて止まらなかった。便座に体育座りをして、膝頭に顔を押し付けて泣きながら、書いて良かったと思った。自分の書いた小説を、書いて良かったと思える。それ以上に幸せなことはこの世にないと思った。その瞬間、私は幸福の形を一つ思い出すことが出来た。
そして私はトイレのドアを開け、子供たちを幼稚園と保育園に送り届け、買い物や家事を済ませ、今日の夕飯を考え、四時にはお迎えに行き、公園に連れて行き、夕飯を作り食べさせ風呂に入れ寝かしつける。何も考える事なく脳死状態で過ごす一日もあれば、考えが駆け巡り、止まらない不安に怯える一日もある。夫を想って泣く夜もあれば、寝坊してベビーカーを押しながら走る朝もある。過ぎ去る一日一日の中で、幸せになれることを祈る。幸福も絶望も全て瞬間の中にある。それは悲しく儚い事実だが、同時に激しく刹那的で美しい。
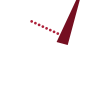















選評
「くもりの無い視線」/ 選考委員 髙樹のぶ子
動物界では「育児期」と「発情期」はかなり明確に別れている。繁殖行動の結果として出産や育児が在るのだが、通常動物のメスは、育児期間中は性行動を行わないしオスを遠ざける。育児を終えたあとでなければ発情期を迎えないのは、その二つは生きものとして相容れない性質のものだからだろう。ほとんどの動物は、子供に乳を与えながら同時にオスを迎え入れるようなことはしない。
けれど人間はそれが出来る。母親であることと女であることが同居し、性行為は生殖のためだけでなく、性欲、コミュニケーション、信頼感、安心感のために行われる。「女であること」と「母であること」は、一人の女性の中で混ざり合い、状況に応じてどちらかが表面に出て来る。けれど女性の心身には、常に戸惑いと葛藤があるのだ。
男社会はその現実に目を背け、「母性」の絶対化と神聖化を母親たちに押しつけてきた。女たちもこの押しつけを受け入れ、男たちには不可能な「母という特権的な立場」を獲得した。男女の役割分担が明確に保証されていた時代、それは安定的で有効だったと言える。
けれど今、女性も社会に出て仕事を持ち、女、母親、職業人としての顔を持つようになった。母に徹して女を諦めることなど出来ず、女で在り続けるために子を産むのを諦めることもならず、さらには仕事を捨てることも出来ず、不器用な女性たちは切なく混乱し、不完全な人間の姿を晒しながら暴走する。男性にとって都合の良い先入観で封印されてきたパンドラの箱が、いま開けられたのだ。
金原ひとみさんの「マザーズ」は、こうした母親たちの、誰も触れたくない、触れられたくない部分を、くもりの無い視線で捉えた画期的な作品である。
同じ保育園に通う三人の母親たちの現実は、息苦しくなるほど切実だ。専業主婦の涼子は、表面上は幸福の模型のような自分の家庭に嘘を感じ、育児を押しつけられた閉塞感からノイローゼになり、幼い子供への虐待に走る。虐待はいかなる理由があろうと許されない。その許されない気持は、虐待する涼子自身が最も強く持っている。なぜなら我が子を愛しているからだ。この自虐的な懊悩の凄まじさ。「虐待は良くない」といくら外部から叫んでも、何ひとつ解決しないことを読者は思い知らされる。同時に女性読者は、自分がそこまで追い詰められていないことに安堵し、けれど自分も、虐待をする可能性がある事に気付かされ恐怖を覚えるだろう。さらに多くの男性読者は、見たくないものに目を背けるか、自分の妻だけは違うと母性神話にしがみつき、脳天気を決め込むしかないのだ。
モデルの五月は夫の愛が失われていく恐怖から不倫に走り妊娠する。不倫で心のバランスをとってはいたが、やがてバランスは崩れ、生命に関わる選択に直面させられる。あげく、子供共々悲劇に呑み込まれてしまう。
もっとも確信的に人生を生きているかに見える作家のユカも、およそ世間で通用する母親のイメージではない。夜遊び、ドラッグ、結婚前のアブナい人間関係を捨てようとはしない。しかし作者の分身とも読めるユカの視線は強い。危険なエッジをぎりぎり曲芸的に渡りながらも、二子目を妊娠する。
母親になっても女は不完全で未熟だ。人間が大人になったところで完全になれないのと同じだ。それでも自分が産んだ子供を愛おしく思うことだけを頼りに、自らの生存をかけて育てている姿がここに在る。
女性文学史に残る作品に、ドゥマゴ文学賞を差し上げることができたのは、作家としてだけでなく女性としても、深い喜びである。