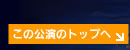 |
 |
「Swan Lake」サドラーズ・ウェルズ劇場公演のオープニングナイトの批評が、早速、タイムズ(The
Times)、ガーディアン(The Guardian)、インデペンデント(The Independent)、デイリーテレグラフ(The Daily Telegraph)等、ロンドンの主要各紙に掲載された。
五つ星を付けたタイムズ紙をはじめ、各紙とも新キャストによる10周年記念公演のステージを絶賛した。 |
タイムズ(The
Times)
2004年12月9日 |
| ダンス |
「白鳥の湖」
サドラーズ・ウェルズ劇場にて、デブラ・クレイン
★★★★★ |
マシュー・ボーンの手がけた「白鳥の湖」は、1995年、サドラーズ・ウェルズ劇場において初演されたが、その後の九年間で、この作品はほとんど伝説とも呼べるような地位を築くこととなった。ウエスト・エンドとブロードウェイで上演されて大成功をおさめ、数々の最高の賞に輝いただけでなく、世界各地で公演を行なってきてもおり、その上演回数は900回にも及んでいる。何より、この作品によって、マシュー・ボーンは、今日のダンス界におけるもっとも重要なクリエイターの一人としての座を確かなものとしたのである。
そして驚くべきことに、そのような年月が経過してもなお、「白鳥の湖」のもつ輝きは失われてはいない。十周年記念プロダクションは、サドラーズ・ウェルズ劇場で記録破りの業績をあげている――ボックス・オフィスでは、150万ポンド以上の売り上げを記録した――そして、火曜夜の初日において、「白鳥の湖」は大勝利をおさめた。
ボーンの「白鳥の湖」は、チャイコフスキーの音楽で知られる名作古典バレエを、我が国のロイヤル・ファミリーの姿をあつかましくも痛烈に反映させながら、ウィットに富んだ、おもしろおかしい現代的な物語へと読み替えたものではあるが、作品はその結末において、ユーモアをこえ、圧倒的ともいえる人間感情の真実の境地へとたどりつく。チャールズ皇太子にまつわるギャグや、おもちゃのコーギー犬、そして先行芸術の巧みな引用やオマージュが散りばめられてはいるものの、この作品は本質的には、愛に飢えた一人の少年の物語、社会によって課せられた義務に抑圧されている王子の物語である。そして、白鳥たちは、19世紀に創作されたバージョンと同様、このプロダクションにおいても物語の中で中心的な役割を果たしている。
ここで白鳥というのはもちろん、すでにご承知のように、チュチュを着た美しい女性ダンサーたちではなく、上半身は裸で、太ももを羽根でおおわれた、力強く恐ろしげな男性ダンサーたちである。彼らが踊るその威嚇的な白鳥たちは、一団となって、まずは王子に、さらには矛先を変えて、人間を愛するという愚を冒してしまった彼らの群れのリーダーにも、非難の叫び声をあげ、憎しみをたぎらせながら襲いかかってゆく。
このプロダクションは、才能にあふれたアーティストたちによる輝かしいコラボレーションの結果生まれたものでもあるが、ダンサー以外のスタッフの業績にもとりわけ目を見張らせるものがある。レズ・ブラザーストンの手による、1960年代の香りをただよわせたデザインはゴージャスな仕上がりを見せているし、リック・フィッシャーが手がけた照明は、室内のシーンにおいても屋外のシーンにおいても、リアルでありながら想像性にも富んでいて、非常にドラマティックな効果をもたらしている。そして、指揮のブレット・モリスは、まるで魔法のようなチャイコフスキーの演奏を聴かせてくれる。
今回のキャストたちが見せるパフォーマンスは、初演キャストたちのそれとはかなり異なってはいるものの、そのオリジナリティこそが実にすばらしい。ニール・ウェストモーランドは、物語が進んでゆくにつれ錯乱の度合いを深めてゆく王子として、抜群の演技を見せる。王子は、あらがいがたいほどひどく愛に飢えるあまり、苦悩にさいなまれ(そして、自殺を考えもする)、彼の母親である女王が、彼の憧れの対象である男性といちゃついている姿を目の当たりにして、殺意をはらんだ嫉妬心へと駆り立てられてゆくのである。ウェストモーランドは(彼はノーザン・バレエ・シアター在籍中も、非常に印象的な演技を見せていた)、テクニック面においても感情面においても表現力の豊かなダンサーであり、彼が造形した、白鳥をヒーローとして夢見る、心の平静を失った少年という人物像は、この作品の核心ともいうべき存在となっている。
ニコラ・トラナー(長らく英国ロイヤル・バレエ団の一員であったダンサーである)によって演じられている王子の母親役は、今回の演出においては中核的な存在を占めている。支配的で、抑圧的で、偽善的で、かつ、非常に適切なやり方でロイヤル・ファミリーをパロディ化してゆくトラナーの演技は、怪物のように冷酷な女王というこの役柄のキャラクターをすばらしく正確につかんでおり、エレガントな踊りがまたそれを引き立てている。
今回はホセ・ティラードが“ザ・スワン/ザ・ストレンジャー”(もしくは、そちらの方がお好きだという方は、オデット/オディールと呼んでくださってもかまわないのだが)を踊っているが、この点において、このプロダクションは以前のバージョンとは異なる特質を高らかに示している。この役の初演においてすばらしい演技を見せたアダム・クーパーは、情熱的でロマンティックなキャラクターとしてこの“ザ・スワン/ザ・ストレンジャー”を造形した。ティラードの“ザ・スワン/ザ・ストレンジャー”は、力強く野性的で、カリスマ性があるのはもちろんのこと、危険な香りもただよわせている。彼のキャラクター造形は、同性愛的な象徴というよりもむしろ、さまざまな側面においていくつもの魅力的な要素を兼ね備えている。
アルフレッド・ヒッチコック監督の映画「鳥」にインスパイアされた、もはや伝説ともなっている第四幕(「昨年の夏 突然に」<テネシー・ウィリアムズの戯曲の映画化で、精神病院におけるロボトミー手術を題材として扱っている>の恐怖も頭をよぎるが)において、ボーンはもっともあざやかな手腕を見せる。ありえないようなラヴ・ストーリーが、ダンスと音楽によって痛ましい結末へと導かれてゆくマシュー・ボーン版「白鳥の湖」は、この作品の数多くのバージョンのうち、もっとも悲劇的で、もっともすばらしい出来のプロダクションである。
First Night reviews |
| 訳:藤本真由 |
| © Bill Cooper 2004 |
|
|
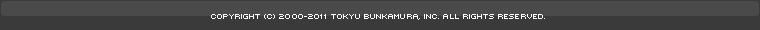 |
|