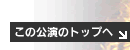 |
 |
 |
「オペラハウス=歌劇場は、街の文化の中心」と大野和士は語る。パリ、ロンドン、ウィーン、ミラノなどの大都市ばかりでなく、ヨーロッパでは小さな街にも歌劇場がある。そこで行われるオペラの公演、コンサート、バレエ等は、街の話題の中心で、だからこそ、歌劇場の音楽監督の仕事というのは重責なのだ。ましてや、大野和士が音楽監督をつとめるベルギー王立歌劇場(モネ劇場)のあるブリュッセルは、パリ、アムステルダム、ケルン、ロンドンなどとTGVでダイレクトに結ばれ、EUを始め国際機関も多い。国際都市というブリュッセルの位置が、モネ劇場をヨーロッパでも屈指の重要な歌劇場にしている要素なのである。
大野和士の歌劇場への道のりは平坦ではなかった。小学生の時に日比谷公会堂で初めてオペラを見たという大野だが、指揮者としてオペラの仕事に携わるのは日本では難しいことだった。オペラ団の公演のアシスタントや小さな歌劇団の公演を振る経験をし、大学を卒業した後、大野はドイツ、ミュンヘンのバイエルン州立歌劇場で研鑽を積む。本格的にオペラ、歌劇場と触れ合う機会がやってきたのだ。その時に教えを受けたのが日本でもファンの多いウォルフガング・サヴァリッシュ、そしてジュセッペ・パタネーという練達のオペラ指揮者たちだった。
歌劇場での研鑽を積みながら、大野はイタリアの指揮者コンクールで優勝し、まずクロアチアのザグレブ・フィルの常任指揮者というポストを得る。ここは通常のシンフォニー中心のオーケストラだが、大野の歌劇場への道のりはそこから始まった。日本国内でも東京フィルの常任指揮者として「オペラコンチェルタンテ」シリーズなど、独自のオペラ公演企画を成功させる一方、ヨーロッパでの活動でその実力を発揮し始めた大野は、1996年ついにドイツの中堅歌劇場であるバーデン州立歌劇場の音楽総監督のポストを得る。音楽総監督という仕事は、単なるオペラ指揮者ではなく、より芸術的に大きな責任を負うポジションだ。この地位に日本人が抜擢されることは極めて稀で、日本のみならず、ヨーロッパでの注目される人事だった。音楽的な才能もさることながら、語学や人事能力など、多彩な要求をされる音楽監督は、ヨーロッパでは大企業のトップの交代ぐらいに大きな話題なのだ。
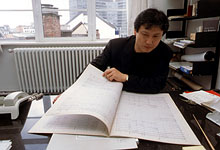 |
さらに大野が話題となったのがモネ劇場の音楽監督への就任だった。それまでのドイツ語圏ではなく、今度はフランス語やオランダ語の世界の歌劇場で、しかも前任者は現在ロンドン、コヴェントガーデンで活躍するアントニオ・パッパーノ。世評高き前任者の跡を襲って重責を担わなければならない。しかし、就任後2年で早くも大野はその前任者の記憶を過去のものにしようとしている。
大野のモネでの日常は多忙だ。世界中から送られる歌手の資料を見て、オーディションをする、何ヶ月もかかる新しい公演の練習、そしてオーケストラのコンサート。その他に、モネ劇場が重視する教育的プログラムにも関わる。これは劇場スタッフが学校に出かけていって、丸一日生徒たちとオペラに関わるイヴェントをするというもの。それ以外にも、大野はエクサンプロヴァンス音楽祭に客演するなど、ヨーロッパで多彩な活動を繰り広げている。オペラ指揮者としての快進撃はまだまだこれからも続くだろう。
|
| 文: |
片桐卓也(音楽ジャーナリスト) |
| 撮影: |
木之下晃 |
|

|
|
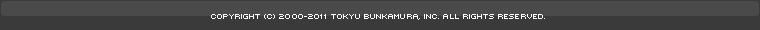 |
|