Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第32回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

木村紅美 著
『あなたに安全な人』
(2021年10月 河出書房新社刊)
| 選 考 | ロバート キャンベル |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計
副賞:100万円 |
| 授賞式 | 2022年10月17日(月) 於:Bunkamura |
授賞式のレポートはホームページで公開しています。
受賞者プロフィール

木村紅美(きむら くみ)
1976年兵庫県生まれ。小学校六年生から高校卒業まで宮城県仙台市で過ごし、現在岩手県盛岡市在住。明治学院大学文学部芸術学科卒。2006年に「風化する女」で文學界新人賞を受賞しデビュー。著書に『風化する女』『月食の日』『夜の隅のアトリエ』『まっぷたつの先生』『雪子さんの足音』等がある。

ロバート キャンベル(Robert Campbell)
ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。 主な編著に『日本古典と感染症』(編)、『井上陽水英訳詞集』、『東京百年物語』、『名場面で味わう日本文学60選』(飯田橋文学会編)等がある。YouTubeチャンネル「キャンベルの四の五のYOUチャンネル」配信中。
受賞の言葉
不穏さの裏側にある何か / 受賞者 木村紅美
八月のある夜、ロバートキャンベルさんがBunkamuraドゥマゴ文学賞に『あなたに安全な人』を選んでくださったと知らされ、跳びあがった。驚きと喜び、不思議さが混ざりあい、眠れなくなった。朝まで、蝉と鈴虫の声に耳を澄ませていた。
選評を読み、まっさきによみがえったのは、東日本大震災のひと月後、東京から初めて岩手の沿岸へボランティアに入ったときの記憶だ。古着の山を仕分けし、帰りのバスで坂口安吾『白痴』を読み返した。むしょうに、敗戦直後の日本の作家のものを読みたい気分だった。
小説に出てくる「焼跡」のイメージは津波の跡と重なってなまなましく変わった。生きる希望を失いながら東京大空襲下をぎりぎり生きのびる伊沢と女は、私の頭に棲みついた。そのあと、東北と縁の深い作家として、震災と向いあったものを書かなければ、と囚われすぎて躓き、没がつづいた時期があった。
宮沢賢治も読み返した。彼が生きていた頃に岩手は二回も大津波に遭っているけれど、それをじかに書いた小説はない。でも銀河鉄道に乗りこんでくる沈没船の死者たちは津波の死者とも重ねて読める。どうすればこんなふうに書けるんだろう。
震災後のこの国は、戦前へ近づいてゆく危うさが増したようで、尾崎翠『第七官界彷徨』を読み返したら、こちらも印象が変わった。執筆期間に起きた昭和恐慌、満州事変を意識すると、小野町子が奇妙でせつない下宿生活を送った「よほど遠い過去、」という出だしは、息をのむ不穏さで迫ってくる。翠は同時代の作家たちが戦争協力へ傾いてゆくまえに鳥取へ帰郷し、以降は小説を書かなかった。
選評にある「不穏としか言いようのないような感覚を理屈や説明抜きに」書こうと、私は、むかしから好きな作家たちに触発され新しい小説も読みながら、試行錯誤をくり返してきたように思う。「ポッド」で息を殺しあう妙と忍の「打算と孤独と生きる一種の才能」は、おそらく、あの日読んだ『白痴』から受け継いだ。ここまで来るのに、十年あまりかかった。いつも、プロットなし、一行さきの展開すら掴めない書き方で書きつづけてきて迷走も多いけれど、この書き方しかできない。いま、受賞に心底感謝し励まされている。
アイデアが最初に閃いたのは、新型コロナウイルスがあらわれるよりだいぶ早く、一八年十二月の沖縄だった。土砂投入が始まる直前に私は辺野古で座り込みをした。生まれて初めて、機動隊員に両手足を持ちあげられ運ばれながら、自分を痛めつける男の視点で小説を書きたくなった。晴天の海へ向って一日じゅう仁王立ちをしている警備員の姿も、それはそれで酷な仕事に思え眼に焼きついた。
沖縄が大好きで、沖縄の山を崩し戦時の遺骨まじりの土砂で海が埋め立てられるのが耐えられなくて抵抗運動に加わっても、私は本土の人間であり沖縄にとって加害側、という意識はつねに喉もとに絡まっている。私がいちばん、自分を重ね描いたのは忍だ。いっそ、即身仏になってしまえ、という思いが湧いた。これからは、「世界を覆う不均衡」にさらに耳を澄まし、よりくっきりと浮びあがらせ風穴をあけ揺さぶるものを書けるようになりたい。
沖縄へは、学生時代から、民謡に興味を持ち通い始めた。とくに八重山諸島に惹かれる。私はアイルランドの伝統音楽も好きだ。だんだん、歴史といい、沖縄(日本ではない)と通じるのでは、と気になってたまらなくなり、二十九歳の初夏、たしかめるためにひとり旅をした。
ゴールウェイ三泊、ダブリン一泊。下戸なのに毎晩、生演奏目当てでパブに入り浸った。泡盛とギネスの香り、リズムに合わせ踊りだす人たち、竹富島や黒島を歩いているとかならずだれかの三線が風に乗ってくるように、イニシュモア島では歌やフィドルが響いてきた。淡い緑の牧場風景は岩手とも似て、なつかしくなる国だった。私はヨーロッパはアイルランドしか行ったことがない。あの国が、キャンベルさんのルーツであることも不思議な縁に感じる。
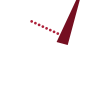















選評
見えないモノから身を守るポッド / 選考委員 ロバート キャンベル
イルカが小群を組み、波の上を勢いよく跳んでいる動画を見た。解説のテロップには“Pod”という文字が表れ、瞬時に、そういえば、イルカの群れのことを英語でポッドという、ということを頭に浮かべた。たいそう剛健そうな隊形の割に、可愛いらしいネイミングだなと感心した。
不均衡 に声と形を与えようとしている点において、ひとまず高い評価に値する作品であることは間違いない。日々、自分の体に刻まれる無数の小さな引っ掻き傷を、あたかもページをめくりながら指で確かめるごとき違和と、納得感を得た。読後感は、けっして爽やかなものではない。
妙 と三四歳になる忍は、偶然、それぞれの過去に起きた一件の辛い出来事によって引き寄せられるようにして出会った。周囲の目や声を遮断する独自の生活システムを編み出している。季節が一巡していくなかで、それぞれの観点で過去のトラウマを忠実になぞり、安全な場所で自分を守るのに必死である。
礫 が落ちてこないことを祈るような思いで読んでいた。
ポッドから連想するのは、えんどう豆の「サヤ」=podである。実を守り、育む役割を持ち合わせる自然界の機構である。育むこととはあまり関係ないが、ちょっと前まで人々はウイルス感染を避け、豆のサヤに似た隔離ポッドquarantine podというものを作りその中で過ごしていた。イルカの小群のように、目には見えないけれど、思わぬ方向から向かってくるかもしれない外敵から身を守る安定した圏域が出来上がるわけである。
『あなたに安全な人』の著者は、人々の心に巣喰う漠とした不安に向かおうとしている。まるでコテで塗り上げ乾燥させた、並列的で短く区切られた壁のような文章で書き切っている。読みながら、わたくしは長く続く言葉の壁に見入り、喉の奥でいがいがするものを覚えた。文学作品、つまり物語だから当然ともいえるけれど、不穏としか言いようのないような感覚を理屈や説明抜きにひしひしと畳み掛けてくる。世界を覆う
ストーリーは、互いの名前は知っているがそれを使わず心の中では「女」「男」と呼び合う二人の、東北の一隅に建つ女の方の実家で過ごすソフトな逃亡生活を描いている。自分たちの自由と健康を奪おうとする勢力がすぐ目の前に迫っているわけではない。罪を犯し、それが知られ、行方を晦まさざるを得ない状況にもなっていないようである。
四六歳の
漠とした不安と書いたけれど、妙も忍も、そもそも引き起こされた取り返しのつかない出来事について、責任を負わなければならないのか、曖昧な側面がある。妙は中学の国語教師であり、忍は警備員を務めていた。社会的な立ち位置が大きく異なる二人だが、それぞれの職場で一度だけ、仕事で要求される核心的な能力を問う場面で他者を傷つけ、本来守らなければならないその対象を死に至らしめたことの責めを負っている。物語は、ひととおり安定した日常が崩れ落ちたところから始まっている。
人々を守り、または育むことに失敗したことを地域という「世間」が批難し、疎外する。安定をもたらすべきポッドの中で「ひとごろし」という空耳かもしれない声が聞こえ、落書きを書きつけられ、不穏と閉塞感に満ちた日々を規則正しく二人で乗り切ろうとする。ある程度の静けさと均衡は獲得できる。これ以上、主人公の頭上に不幸な
小説を読みながら、わたくしは今生きなければならない社会のプレカリティ(precarity. 漠とした不安定さ)とも言える不穏な足どりがかいま見えた気がした。富める者も富めない者も、直面しなければならない社会の病理を基底から清潔に、かつ稠密に配置したフィクションの上から、指で触れ、感覚として追体験できる一冊である。けっして結ばれることのない他者同士の打算と孤独と生きる一種の才能は、行間にあふれ、混ざった色として目の前に現れるのであった。