Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners
- 受賞作品
- 受賞作品一覧
第20回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

朝吹真理子 著
『流跡』
(2009年9月 「新潮」10月号 新潮社刊)
| 選 考 | 堀江敏幸 |
|---|---|
| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計 副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |
| 授賞式 | 2010年11月1日(月) Bunkamura 第一部 受賞記念対談 16:00 オーチャードホール・ビュッフェ 第二部 贈呈式と小宴 17:30 「ドゥ マゴ パリ」テラス |
受賞者プロフィール

朝吹真理子(あさぶき まりこ)
1984年12月、東京生まれ。
慶應義塾大学前期博士課程在籍(国文学専攻)。
2009年、『流跡』(「新潮」10月号)で小説家デビュー。
他の作品に『家路』(「群像」2010年4月号)、『きことわ』(2010年9月号)がある。
新潮社 http://www.shinchosha.co.jp/book/328461/

堀江敏幸(ほりえ としゆき)
1964年、岐阜県生まれ。作家、フランス文学者。
主な著書として、『郊外へ』 (1995)、『おぱらばん』(1998)、『熊の敷石』(2001)、『雪沼とその周辺』 (2003)、『河岸忘日抄』(2005)、『正弦曲線』(2009)、訳書として、エルヴェ ・ギベール『幻のイマージュ』、ジャック・レダ『パリの廃墟』、フィリップ・ソレルス『神秘のモーツァルト』などがある。
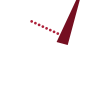















選評
「流れない水の光」/ 選考委員 堀江敏幸
読んだあとしばらくすると、書かれていたことをなにひとつ思い出せず、ただ読んだという漠然とした感覚しか残らない作品がある。この感覚には快不快のいずれもが含まれうるのだが、頭の片隅にいつまでも残ってかすかに明滅しつづけるのは、前者、すなわち快のほうだ。ただしそれは単なる心地よさではなく、得体の知れない何かを包み隠した言葉にだけ宿りうる心地よさであって、表面をただ滑らかに流れる軽やかな水の愉楽とはべつものだと言っていい。
朝吹真理子さんの「流跡」は、読後しばらくすると、不穏な心地よさが輪染みのように浮かびあがってくる不思議な言葉の群れだ。筋らしいものは、たしかにある。「ほんとうに愛した人がほしいから妻をつくった」という、どこか論理の、いや、倫理の順序をゆがめた男が、語り手のまなざしを背中に受けながら本を読む。文字ではなく「本を」目が追うのだ。紙は水になり、活字は魚になり、瞳はその水面を滑って、結局彼はなにも読むことができない。読むとはどういうことなのか、それすらわからなくなってくる。男の脳裡にあるのは純粋な「流れ」だけである。時間の、愛情の、言葉の流れ。その言葉は、雅楽器になり襲装束になり金魚になってぐるぐるまわりはじめ、映画の世界に入り込んだかと思うとスクリーンに浮かんだ風景の穴の向こうに出て、三途の川のようなところから小さな舟で自分という客を運ぶ。
あちらの世界と結ばれたイメージの連鎖は、茫漠として、しかも鮮やかだ。男は同僚の葬儀に出て、焼き場で時間を止める。子供の発話が遅れているかもしれないと案ずる妻とのあいだで、会話の流れをまた止める。それでも時間は流れ、水も姿を変えながら流れつづける。梅雨の雨、風呂の水、水たまりの水、土砂のように降る雨。水は最後に男女の性差を溶かし解かして、男は女になり女は男になり、黒々としたウナギの背と水に揺れる黒髪が無気味に絡み合う。
しかし「流跡」は、流れを描くのではなく、流れの跡を描いている。はっきりした水の動きも、雅語の杭の周囲にできた渦も、船酔いによる三半規管の異常も感じられるのに、胸に残るのはむしろ「跡」のほうなのだ。これは、あきらかな矛盾である。しかも、受け入れるべき矛盾である。言葉ぜんたいに責任を負う語り手が、しなる指先で流れに棹を差すように打ち込んだ、その結果として電子画面にあらわれる黒い文字から意味が奪われたとき、本当の意味で流れが止まる。「川というのが自由であるとは到底思えない」とあるとおり、言葉はここでついに痕跡でしかなくなる。
水が流れるためには高低差が必要なはずだが、「流跡」の水は平らな土地を平然と横に移動し、しかもあちこちに不吉なたまりをつくる。実際、読後「しばらくして」気づかされるかすかな光の質は、流れる水の表面よりも、動けない水の、たまりの表面に反射したものに近いのだ。油が浮いて七色の光を照り返してくる水たまりや、アスファルト舗装の粗雑さをあぶり出すような水たまりもある。「流跡」の言葉が事後的に作り出していく水たまりは、しかしそのいずれともちがっていて、映り込んだ風景も、ずっと先に現実として存在する光景も消さずに、ただ水たまりとして存在している。
前方に光るものに目を留めることなら、だれにでもできる。足を汚さないよう飛び石伝いに進んでいくその石を、前もって準備しておくことくらい、小賢しい書き手なら簡単にできる。けれど、後方に順次残されていく言葉のたまりとその表面に生じた光を、読者に前を向かせたまま感じさせるのはきわめて困難だ。朝吹真理子さんの「流跡」は、その困難なことを、結果として、つまり文字どおりの水たまりとして、「跡」として現前させてしまった。彼女の瑞々しい言葉は、これからも確実に前に流れながら、不穏な感情の「たまり」を私たちの胸に残してくれるだろう。