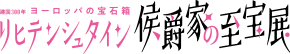2019.12.10 UP
【レポート】本展監修者・鈴田由紀夫氏による記念講演会:Part 2
2019年10月24日(木)、『建国300年 ヨーロッパの宝石箱リヒテンシュタイン 侯爵家の至宝展』の開催を記念して、本展監修者・鈴田由紀夫氏による記念講演会「磁器―西洋と東洋の出会い」が開催されました。その内容をダイジェストでご紹介いたします。
前回に引き続き、今回はPart 2をお届けいたします。
Part 1はこちら
「絵画」の中の磁器
「芙蓉手」のデザインと金具以外にもう一つ東洋と西洋を繋いだのは、「絵画」の登場です。絵画の中に焼き物はしっかりと描き込まれ、17世紀後半のヨーロッパの静物画、とりわけオランダはこの種の作品が多く制作されました。本展では、リヒテンシュタインの所蔵品の中から焼き物が描かれた静物画をなるべく多く借用しました。今回絵画全体に関する解説はリヒテンシュタインの担当者が行いましたが、画中の焼き物の部分は私が担当しました。なお、画中の磁器の大半は有田焼ではなく量で勝る中国磁器です。

ビンビ(本名バルトロメオ・デル・ビンボ) 《花と果物の静物とカケス》 制作年不詳、油彩・キャンヴァス
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
ビンビ(本名バルトロメオ・デル・ビンボ)による《花と果物の静物とカケス》では、割れた焼き物が描かれていますが、その真意は明らかにされていません。当時、磁器は東洋から西洋へ1年もかけて船で輸出されものを、貴族が相当な高値で購入していました。加えて、一時磁器は「白い黄金」と呼ばれ、金に匹敵するほど高価な代物でした。そのため、本作のようにテーブルコーディネートもせず、無造作に置かれると磁器のありがたみが感じられませんが、この当時の静物画の流行は鳥や果物などが雑然と配置される傾向にありました。割れた磁器の破片の模様に目を向けると、おおもとの器と同じものであることが分かります。このことから、これらの輸入された磁器が割れても捨てられずに大切にされていたことが、静物画の題材になったのかもしれません。

ピーテル・クラース 《饗宴の静物》 1652年、油彩・キャンヴァス
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
ピーテル・クラースの《饗宴の静物》を見ても、注目すべきなのは焼き物です。この焼き物は恐らく中国のものであると判断することができます。なぜならば、有田焼と比較して中国磁器は薄いのが特徴だからです。焼き物の研究に携わると、作品の年代を20~30年単位で特定することが可能です。1650年頃の制作ではないかと本作の年代の見当をつけると、絵画が1652年の制作とされており、画中の焼き物は絵画の年代特定にも役立つと言えるでしょう。
フェルメールの絵画に登場する焼き物を例に挙げると、有名な《牛乳を注ぐ女》の容器は有田焼でも中国陶磁でもなく、彼の出身地であるデルフト焼と考えられます。しかし、デルフトは東インド会社の重要な拠点であったことから、フェルメールは東洋からもたらされた焼き物を必ず見ていたはずですが、画中に描き込むことはありませんでした。

クラースの静物画に描かれた焼き物について言えば、模様がはっきりしていないためデルフト焼とも考えられますが、中国陶磁の可能性が高いでしょう。この焼き物の蓋の部分には銀製金具が付いており、中身に異物が混入しないための用途があったとされています。有田焼には蓋なしの注器がありますが、取っ手の部分に事前に穴をあけるようにと注文が当時入っており、その要望に応え出荷されていました。この穴は、つまみで蓋を持ち上げるとき金具がずれないよう固定するためにあけられたものです。この注器の傍に置かれたガラスの器に入っているのは恐らく白ワインですが、通常ワインジャグと呼ばれるこの注器からコップに注ぐと考えると、サイズが適当でないように思われます。また、このジャグにはスプーンの柄のようなものが差し込まれ、ワインにスプーンを用いるとは考えにくいため、何らかの調味料入れかもしれません。このように、静物画に描かれたモチーフに目を凝らすと、非常に興味深い発見があります。
西洋と東洋のコラボレーション
ワインジャグの金具に話を戻すと、この部分が西洋と東洋のコラボレーションであることが分かります。焼き物は中国の景徳鎮でつくられ、そして後からリヒテンシュタインで立派な金具が取り付けられています。そのことがよく分かる作品として、《染付花鳥文金具付水注》の借用を依頼し、本展で展示されることとなりました。

中国・景徳鎮窯 金属装飾:イギリスの金銀細工師 《染付花鳥文金具付水注》 磁器:万暦年間(1573-1620年)、金属装飾:1600年頃、磁器:青の下絵付、装飾:銀
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
本作の胴部には、芙蓉手の皿の周辺に描かれていた模様が描かれています。この水注は焼き物の部分だけでも十分にワインなどの液体を注ぐことができますが、金属の蓋、注ぎ口には鹿のような獣の金具、そして取っ手にはヨーロッパならではの装飾がなされています。日本にも龍をモチーフにした耳があり、このような装飾は東洋に影響されたのかもしれません。この取っ手を鑑賞することも、焼き物通の楽しみ方です。単なるシンプルなデザインのものもありますが、たいていは人、獣、龍、中には不気味な生き物がかたどられ、凝ったつくりです。本作の場合、外側を向いた獣と人間の横顔がモチーフとなっていますが、こういった金具に関しては、ヨーロッパの中でとりわけフランスのレベルが高いと言われています。金具の取り付けの歴史は古く、中国の元時代(14世紀頃)に焼き物がヨーロッパに輸出され、1700年頃フランスで金具が付けられた事例が残っています。本体のみであればワインを入れて口からとっくり式に注ぐだけですが、ヨーロッパでは水差しのようにおしゃれに用いたかったのでしょう。注ぎ口の部分に穴をあけ、美しい飾りを付け液体を注ぎ出すことがヨーロッパでは早い時代から行われてきましたが、硬い焼き物に穴をあける技術は日本ではあまり発達しませんでした。そのため、日本では木製のものと組み合わされることがありました。

ヨリス・ファン・ソン 《倒れた銀器のある豪華な静物》 1650年、油彩・キャンヴァス
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
ヨリス・ファン・ソンの《倒れた銀器のある豪華な静物》をご覧ください。こちらには、銀製のワインジャグが描かれています。焼き物で特殊なかたちというのは、銀器をコピーし焼き物に置き換えたものが多いです。蓋の部分を含め焼き物で作ることは難しいため、蓋なしのワインジャグを有田や中国に発注し、後から銀製の蓋をつけたのではないかと考えらます。しかし、もともとは一体化した銀製の注器が基本です。なお、この作品においてもワインジャグは倒され、全体的なテーブルセッティングはされず、取り乱された印象を受けます。このような構図が好まれたからなのか、多くの静物画はこの種のスタイルを踏襲しています。
ヤン・ダーフィツゾーン・デ・ヘームによる《陶器、銀器、果物のある静物》もまた画中に焼き物が描かれた静物画です。ワインジャグの模様から検討すると中国のものであると考えられます。先ほど述べた取っ手の部分に開いた穴は、時折金属の蓋を付けずにそのまま用いられることもありました。有田焼は穴の開いた焼き物を注文通りに生産し、納品することをとりわけ多く行っていました。
金工師、イグナーツ・ヨーゼフ・ヴェルトの装飾
今回展示されている金具付きの有田焼の中で最も優れ、リヒテンシュタイン侯爵家コレクションとしても重きが置かれているのは、《染付山水文金具付ポプリ蓋物》です。リヒテンシュタインの図録には有田焼という表記もあるが、東洋としか記されていない表記もあります。有田焼に間違いありませんが、その明らかな証拠は陶片であり、本作に関連した窯跡出土の陶片も見つかっています。通常金具の制作者は知られていない場合が多いのですが、この蓋物は有名な金工師で宝石の加工師であるイグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルト(1740-1792)という人物による装飾であることが判明しています。加えて、制作年代まで明らかとなっていることからも、本作のレベルの高さをうかがわせます。本来蓋の摘みには狛犬がついていましたが、現在では葉とベリーの装飾が施され加工されています。

日本・有田窯 金属装飾:イグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルト 《染付山水文金具付ポプリ蓋物》
磁器:1670-90年代 金属装飾:1775-85年 磁器:青の下絵付(染付) 装飾:鍍金されたブロンズ
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
用途に関しては、ヨーロッパに渡ってからはスープやシチューを入れた蓋物と考えられますが、解説にはポプリ壺と書かれています。つまり、本来食器として出荷された本作は、ポプリを入れるために作り直されているのです。ポプリの香りは、後から取り付けられた格子状の金具の隙間から漂う仕組みとなっています。このように蓋付きの鉢を改良して隙間をつくった焼き物は多数存在し、その当時大いに流行したことがうかがい知れます。ポプリ入れは新たな用途として興味深く、脚の部分にはアカンサス風の葉と、磁器本体の下端には月桂樹の葉のデザインが施されています。
ここでの疑問は、この蓋物自体が1680年頃有田で作られ、金具が1770年代に付けられたことから、100年ものインターバルがあることです。金具に関しては同時代に付けられたものもあれば、後の時代に付けられたものもあり、今後更なる調査が求められます。第二の疑問は、蓋の摘みに付けられた狛犬です。実物の作品を見てみると、あるはずの箇所に狛犬の頭部が見えないため、切り取られてしまった可能性があります。

日本・有田窯 金属装飾:イグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルト《青磁色絵鳳凰雲文金具付蓋物》
磁器:1690-1710年代 金属装飾:1775-85年 人物像後補 磁器:青磁、エナメルの上絵付、金彩 装飾:鍍金されたブロンズ
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
《青磁色絵鳳凰雲文金具付蓋物》も有田の焼き物に金具が付けられています。本作は青磁であり、緑青いガラスが釉薬となり鳳凰と雲が描かれています。本作の上部には穴が四ヵ所開けられており、香炉として出荷された焼き物に、優勝カップのような装飾を施したのでしょう。金属装飾を行ったイグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルトは、金細工師及び宝石細工師として活躍した人物でした。1769年に父の工房を継ぎ、1770年に父親が亡くなったことから、本作を制作するに至りました。この蓋物はリヒテンシュタインコレクションにある2点ある内の1点です。

中国・景徳鎮窯 金属装飾:イグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルト 《染付花鳥文金具付壺》
磁器:順治年間(1644-61年)または慶煕年間(1662-1723年) 金属装飾:1775-85年 磁器:青の下絵付 装飾:鍍金されたブロンズ
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

中国・景徳鎮窯 金属装飾:イグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルト 《染付庭園文金具付大皿》
磁器:乾隆年間(1736-95年) 金属装飾:1775-85年 磁器:青の下絵付 装飾:鍍金されたブロンズ
所蔵:リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna
中国の焼き物に金具を付けた作品もリヒテンシュタイン侯爵家コレクションには多く所蔵されており、《染付花鳥文金具付壺》はその一点です。この作品の用途は分かっていませんが、焼き物は1660年代頃に制作され、例に倣って金具の装飾は100年後に行われました。《染付庭園文金具付大皿》と比較すると、金具の部分はイグナーツ・ヨーゼフ・ヴュルトによるもので、両作品のデザインは非常に近似しています。従って、このような装飾を彼がこの時期に一貫して行ったことを意味しており、この流行がこれらの焼き物を作り変えることを彼に促したのです。
本作に見られる装飾は、割れやすい皿を保護するためのもののように見受けられますが、実用的とは言い難い。はじめは焼き物だけで食事用に用いられ、100年後使われなくなった後、金具の装飾が取り付けられた可能性があります。絵柄に関していえば、冬でも枯れない縁起物の竹は強い生命の象徴であり、ボタンは富貴の象徴です。大皿の周囲は、ギリシャ由来のヨーロッパ人に大いに好まれたアカンサス(日本でいう唐草模様)の金属装飾で囲まれています。豊かに伸びるこの植物は、ヨーロッパでは古典的に長きに渡って好まれてきたモチーフです。