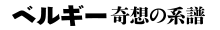2017.08.23 UP
辻惟雄氏×小池寿子氏によるスペシャル・トーク「中世と現代をつなぐ奇想の系譜」を開催しました!
去る7/17(月・祝)に、本展開幕トークイベントを開催いたしました。
美術史家の辻惟雄氏と國學院大學教授の小池寿子氏を迎え、モデレーターは美術ジャーナリストの藤原えりみ氏、というスペシャルなメンバー。

「奇想」ということばをキーワードに、発想の源泉や現代に受け継がれる奇想の表現について、洋の東西を超え縦横無尽に語っていただいたスペシャル・トークの様子を抜粋でお届けします。
 辻 惟雄(以下T):私がなぜここに招かれているのかと言いますと「奇想の系譜」という言葉に関連するからです。私が大変興味を持ちましたのはベルギーの中にも「奇想」と言える作品の系譜があって、かなり距離も離れていますが、私の『奇想の系譜』(美術出版社1970年/ちくま学芸文庫2004年)の前からの系譜であり、また内容的にも「奇想」という言葉が当てはまらないようなところもあります。私の「奇想」は江戸時代ですけれど、骸骨、おばけなどその扱いが少し違うということも後ほどお話しさせていただければと思います。較べてみれば面白いと楽しみにしています。
辻 惟雄(以下T):私がなぜここに招かれているのかと言いますと「奇想の系譜」という言葉に関連するからです。私が大変興味を持ちましたのはベルギーの中にも「奇想」と言える作品の系譜があって、かなり距離も離れていますが、私の『奇想の系譜』(美術出版社1970年/ちくま学芸文庫2004年)の前からの系譜であり、また内容的にも「奇想」という言葉が当てはまらないようなところもあります。私の「奇想」は江戸時代ですけれど、骸骨、おばけなどその扱いが少し違うということも後ほどお話しさせていただければと思います。較べてみれば面白いと楽しみにしています。
 小池寿子(以下K):ベルギーに留学をして15世紀のフランドル美術を専門に勉強した後、「死の舞踏」というそれこそ「奇想」を研究し続けています。今日は、ベルギーの15世紀、16世紀の「奇想」の原点に立ち返ってなぜベルギーに「奇想の系譜」がうまれたのかというお話ができればと思います。
小池寿子(以下K):ベルギーに留学をして15世紀のフランドル美術を専門に勉強した後、「死の舞踏」というそれこそ「奇想」を研究し続けています。今日は、ベルギーの15世紀、16世紀の「奇想」の原点に立ち返ってなぜベルギーに「奇想の系譜」がうまれたのかというお話ができればと思います。
K:まず「奇想」とは何かということを考えてみたいと思います。展覧会では「奇想」を「Fantastic」と表現していますが、これは「超自然的」という意味を持ち、「エンジェル」「デーモン」「フェアリー」「ウィッチ」などの超自然的な生き物が描かれている場合を「Fantastic」と呼んだり、魔術的なもの(「マジック」)や「エキセントリック」、あるいは「怪奇的な」と訳されるグロテスクも「ファンタスティック」の中に分類されます。このように「Fantastic」の中にはさまざまな意味が含まれ、そこには主流、中心に対しての亜流/傍流、周縁という対立関係が見られます。理性と感性、王道と邪道というように対比させてもよいかもしれません。
その当時南ネーデルラント美術の主流はやはり宗教画であり、揺るぎのない信仰心と写実性に捧げられた宗教美術の世界というのが南ネーデルラント美術の基本でした。この中から、偏執とも言うべきヒエロニムス・ボスが登場するわけです。
―――中略―――
 K:『トゥヌグダルスの幻視』はアイルランドの修道士が12世紀半ばに記した説話で、騎士、高利貸しでもあったトゥヌグダルスが3日間、臨死体験をするという物語です。ヒエロニムス・ボスの工房作である《トゥヌグダルスの幻視》では、七つの大罪が作品に描かれていますが、当時は「いつも大罪とともに四つの終わりについて考えなさい」と教会は教えていました。四つの終わりというのは、「臨終」のとき、「最後の審判」、「地獄」、「天国」です。この「四終」を心に留めて、日ごろは、大食、怠惰、邪淫、虚栄、憤怒、嫉妬、貪欲といった大罪を避けるように暮らさなければならないというのが当時の教えでした。
K:『トゥヌグダルスの幻視』はアイルランドの修道士が12世紀半ばに記した説話で、騎士、高利貸しでもあったトゥヌグダルスが3日間、臨死体験をするという物語です。ヒエロニムス・ボスの工房作である《トゥヌグダルスの幻視》では、七つの大罪が作品に描かれていますが、当時は「いつも大罪とともに四つの終わりについて考えなさい」と教会は教えていました。四つの終わりというのは、「臨終」のとき、「最後の審判」、「地獄」、「天国」です。この「四終」を心に留めて、日ごろは、大食、怠惰、邪淫、虚栄、憤怒、嫉妬、貪欲といった大罪を避けるように暮らさなければならないというのが当時の教えでした。

―――中略―――
 K:展覧会をご覧になった方は「聖アントニウスの誘惑」を主題にした作品がたくさん出品されていることにお気付きになったかと思いますが、リスボンの考古学博物館が所蔵しているボスの《聖アントニウスの誘惑》は、ボスの作品の中で、最も奇々怪々な動物が出てくるもので、いつまで見ていても飽きることない様々な動物が出てきます。このようなボスの奇々怪々な動物に触発され、16世紀のボス・リバイバルという風潮のなかで、盛んにボス風の絵が繰り返されました。今回出品されているヤン・マンデイン作《パノラマ風景の中の聖アントニウス》は、聖アントニウスが空中で悪魔に苛まれているという場面、火事、卵、奇怪な植物などのほとんどボスからの流用となっています。なぜアントニウスかということですが、12世紀から「アントニウス病」と呼ばれる病が蔓延しました。これは実は麦角中毒の症状で、最期には高熱を発し死に至るという病気だったのですが、聖アントニウスが悪魔から受けた激しい攻撃に似て苦痛だったともみなされていたためか、この聖人の骨を浸したワインを飲むと治るとされ、その病を治療する施設として聖アントニウス修道院が各地に作られました。やがて、麦角中毒を治す方法が見つかってきますと「聖アントニウス」の絵は病気の治療のためではなく、誘惑される男を楽しむという趣向に変わっていくのです。
K:展覧会をご覧になった方は「聖アントニウスの誘惑」を主題にした作品がたくさん出品されていることにお気付きになったかと思いますが、リスボンの考古学博物館が所蔵しているボスの《聖アントニウスの誘惑》は、ボスの作品の中で、最も奇々怪々な動物が出てくるもので、いつまで見ていても飽きることない様々な動物が出てきます。このようなボスの奇々怪々な動物に触発され、16世紀のボス・リバイバルという風潮のなかで、盛んにボス風の絵が繰り返されました。今回出品されているヤン・マンデイン作《パノラマ風景の中の聖アントニウス》は、聖アントニウスが空中で悪魔に苛まれているという場面、火事、卵、奇怪な植物などのほとんどボスからの流用となっています。なぜアントニウスかということですが、12世紀から「アントニウス病」と呼ばれる病が蔓延しました。これは実は麦角中毒の症状で、最期には高熱を発し死に至るという病気だったのですが、聖アントニウスが悪魔から受けた激しい攻撃に似て苦痛だったともみなされていたためか、この聖人の骨を浸したワインを飲むと治るとされ、その病を治療する施設として聖アントニウス修道院が各地に作られました。やがて、麦角中毒を治す方法が見つかってきますと「聖アントニウス」の絵は病気の治療のためではなく、誘惑される男を楽しむという趣向に変わっていくのです。
そして、16世紀に入って大航海時代を迎えると、聖アントニウスの主題は似たようなモティーフを用いながらも次第に聖クリストフォロスの主題へと変化していきます。クリストフォロスは旅の守護聖人でしたので、世界貿易港として栄えたアントウェルペンを有していたネーデルラントの地で好まれたのだろうと考えられます。機械仕掛けの船や女性の姿もシュルレアリスティックな効果を組み合わせて描かれています。
―――中略―――
 K:奇想が生まれた当時の歴史的背景にも目を向けてみましょう。
K:奇想が生まれた当時の歴史的背景にも目を向けてみましょう。
南ネーデルラントはブルゴーニュ公が統治をしていて、50年にわたり第三代フィリップ善良公が実権をにぎりました。実は当時の宮廷文化には宗教心を重んじる反面、大変世俗的で享楽的な一面があったといえます。第4代ブルゴーニュ公、シャルル突進公は、1477年に戦死し、残されたのが娘のマリーです。マリーの時代にブルゴーニュ公国は最大の享楽の時代を迎えたように思われます。
享楽的な宮廷生活の一方で人文主義も盛んになり、ストラスブール生まれのゼバスティアン・ブラントが『阿呆船』という本を書き、また、エラスムスも『痴愚神礼賛』という書物を著しボス、さらにはブリューゲルに影響を与えています。つまり宗教心、道徳心、人文主義という三本柱に支えられたのが南ネーデルラントだったのです。

K:実は、このようなブルゴーニュ公国で「死の舞踏」の上演記録があります。1回はブリュージュで1449年9月に上演され、もう1回がブザンソンです。「死の舞踏」が上演された記録はこの2つしかないのですが、いずれもブルゴーニュ公国にかかわる地で上演されています。19世紀以降も続く「奇想の系譜」を考えると、こうした享楽的な反面、常に終末や死後世界におびえていた民衆の心をつかんだのは、単なる信仰心ではなく、このような奇矯なそして風刺的な、死、エロスといったイメージだったのではないでしょうか。
―――中略―――
K:最後に、ブルゴーニュ公国の中であまり美術史では語られないのですが、アンドレアス・ヴェサリウスというブリュッセルで生まれ、イタリアのパドヴァで修業し、ヴェネツィアで本を出版した解剖学者についても触れておきます。今回、ペーテル・パウル・ルーベンスのエングレーヴィングが出品されていますが、画家たちはヴェサリウスの解剖図から学んで自分たちの造形に役立てていました。
―――中略―――
15世紀から16世紀にかけて南ネーデルラント、フランドル地方において、非常に突出したヒエロニムス・ボスという奇想の画家が登場したわけですが、その背景には宗教的な問題やブルゴーニュ公国の宮廷文化の土壌があり、この公国は医学の専門家も輩出したというところで、私のお話は終わりにさせていただきたいと思います。
 藤原えりみ(以下F):解剖図というと、辻先生の『奇想の系譜』に出てきます国芳ですよね。
藤原えりみ(以下F):解剖図というと、辻先生の『奇想の系譜』に出てきます国芳ですよね。
T:近いのは国芳ですかね。ただ一番の違いはネーデルラントの奇想は人間が主題ですね。日本の場合、国芳は例外ですが、伊藤若冲などは本当に「奇想」あふれる人物で、彼の描く植物などはただならぬ植物で奇妙な形をしています。又兵衛はあまりベルギーとは関係ないのですが、「官女観菊図」などの人物の顔はどこかエロチックな顔立ちで、雅なシーンの中に下品な人間くささを忍び込ませた作品です。それは、ボスが宗教画の中に人間の欲望を描いたものに類似するかもしれません。
F:曽我蕭白の「群仙図屏風」はまさに「エキセントリック」ですね。
T:「群仙図屏風」は「これしかない」としか言いようがないですね。この作品を見つけたときのショックが私の『奇想の系譜』の原点でもあります。この作品は色彩のえぐさというのも日本離れしていると思います。ボスのフォロワーに似た異様な雰囲気がありますね。
K:ヤン・マンデインの《聖クリストフォロス》に似たような感覚を覚えますね。

―――中略―――
 K:辻先生の一押しはどの作品ですか。
K:辻先生の一押しはどの作品ですか。
T:アンソールの骸骨ですね。特にあの足です。骸骨のいたずらっぽい目つきも面白いですね。
アンソールが生まれた翌年に国芳は亡くなっていて、ちょうど世代交代しているんですね。国芳の「相馬の古内裏に将門の姫君滝夜叉妖術を以って味方を集むる大宅太郎光国妖怪を試さんと爰に来り竟に是を亡ぼす」には妖怪と人間の一騎打ちが描かれています。骸骨の絵というと、解剖の本がオランダから入ってきて、それを見た国芳は骸骨を妖怪に見立てて描きました。アンソールが描いたのは骸骨ですかね?
F:死神ですね。ヨーロッパでは中世からありますね。
K:骸骨が死神として登場するのは15世紀末頃からですね。当時の死のシンボルは骸骨ではなく、腐りかけた死体で白骨化していませんでした。国芳は完全な白骨ですね。
T:骸骨が逆立ちしているような作品もありましたね。日本ではこういった発想はないですよね。


F:どこからこのような発想が出てくるんでしょうね。やはり、ベルギーの現代美術といえばヤン・ファーブルですね。タマムシなどの甲虫がびっしり貼り付けられた立体作品です。
K:《フランダースの戦士(絶望の戦士)》というタイトルですね。
F:一見、奇怪な作品なのですが、ベルギーの歴史や植民地支配など極めてクリティカルな目で作品を作っているんです。ですので、単に「エキセントリック」と言うよりは人間の愚行や過去の過ちなどを含めたテーマで構成されていると思います。
―――中略―――
 K:若冲を見ていると本当にヨーロッパには絶対にない絵だな、と思います。
K:若冲を見ていると本当にヨーロッパには絶対にない絵だな、と思います。
T:奇想にもレベルがあって、「純粋奇想」ですね。「不純奇想」というと奇を衒うというやつです。何か面白くしようと細工をする。
中国では鳥をどのように描いていたかということも若冲は学んでいたようですが、若冲はあまりにも引きこもりタイプでしたので、にわとりを庭に放ってスケッチしていたようです。植物、動物だけでなく昆虫も描いていますね。
K:若冲は「純粋奇想」ということになりますね。
F:ヨーロッパ人だと、そのような博物的な関心を持ったときに個別にリアルに描くと思うのですが、若冲はリアルな描写でありながら、全体の構図やモチーフ構成においては非現実な世界を出現させています。小池さんがおっしゃるように確かにヨーロッパの絵画にはない空間ですね。
★本イベントの様子は東京新聞(8/11付)にも一部掲載されました。
web版はこちら
※外部サイトにリンクします
《過去の講演会レポート》

◆【リポート】美術史家・森洋子先生による「ベルギ―奇想の系譜」展開催記念講演会
「ボスからブリューゲルの世界――あの世とこの世の奇想」はこちら
◆<スタッフレポート>鉛筆だけで描いた絵が飛び出す!3Dアーティスト永井秀幸氏によるワークショップはこちら