第1章 狂騒の時代 のパリ
Section 1Paris in the age of “Les Années folles”
1920年代パリ―それは戦争の惨禍を忘れるかのように、生きる喜びを謳歌した「狂騒の時代」。かつて平和と繁栄を享受していた戦前の古き「良き時代」への回帰を願いながら、一方で過去と決別し新たな歴史の創造へ向かったこの時代、キキ・ド・モンパルナス、ジョセフィン・ベイカーなど新しいスターたちに導かれるように、祝祭的、芸術的、知的興奮がモンマルトルからモンパルナスへと広がりました。
この熱気渦巻くパリに、確かな足跡を残した二人の女性がいました。マリー・ローランサンとココ・シャネルです。奇しくも1883年という同じ年に生まれ、美術とファッションという異なる分野に身を置きながら、互いに独自のスタイルを貫いた二人は、まさに1920年代のパリを象徴する存在でした。社交界に属する優美な女性たちの「女性性」を引き出す独特な色彩の肖像画で、瞬く間に人気画家に駆け上がったローランサン。一方、シャネルの服をまといマン・レイに撮影されることはひとつのステータス・シンボルとなっていきました。その写真の多くは後に『ヴォーグ』などの雑誌に掲載され、オートクチュールに身を包んだ女性たちは、時代のファッションを作り上げていくことになります。
ローランサンが描く
社交界の女性たち

マリー・ローランサン 《マドモアゼル・シャネルの肖像》 1923年 油彩/キャンヴァス オランジュリー美術館
Photo © RMN-Grand Palais
(musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

マリー・ローランサン 《ピンクのコートを着たグールゴー男爵夫人の肖像》 1923年頃 油彩/キャンヴァス パリ、ポンピドゥー・センター
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI / distributed by AMF

マリー・ローランサン 《黒いマンテラをかぶったグールゴー男爵夫人の肖像》 1923年頃 油彩/キャンヴァス パリ、ポンピドゥー・センター
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI / distributed by AMF

マリー・ローランサン 《ヴァランティーヌ・テシエの肖像》 1933年 油彩/キャンヴァス ポーラ美術館

マリー・ローランサン 《わたしの肖像》 1924年 油彩/キャンヴァス マリー・ローランサン美術館 © Musée Marie Laurencin


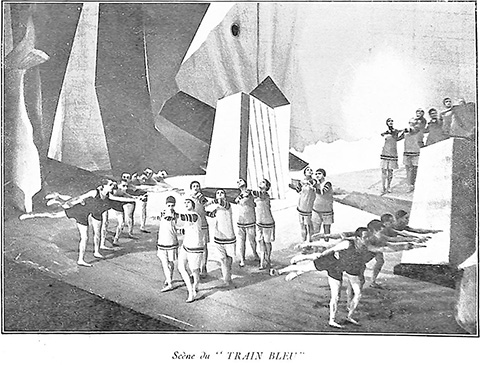











小さいとき、私は絹糸が好きでした、
真珠や、色のついた糸巻きなどを盗ったりしました。
そういうものをうまく隠しておけると思い込んで、
ひとりでこっそり眺めていたものです
マリー・ローランサン