SPECIAL[ スペシャリスト達が語る、
マン・レイの魅力 ]
遊び心や大胆さにあふれた独創的な作品の数々が世界中の人々を魅了してやまないマン・レイ。今もなお計り知れない影響とインスピレーションを与え続ける彼の作品の虜になった各界のスペシャリストたちに、マン・レイの魅力、そして、本展を通して、今この時代において感じてほしいと思うことを伺いました。
INTERVIEW1アートディレクター 田口英之氏
本展のビジュアルデザインを手がけたアートディレクターに聞く、ポスターデザインに込めた思いと本展を楽しむヒント

本展のポスターやチラシなどのビジュアルデザインを手がけたのは、アートディレクターの田口英之氏。近年では、「ミュシャ展」(2017年・国立新美術館)や「生誕300年記念 若冲展」(2016年・東京都美術館)などのほか、今年春にBunkamura ザ・ミュージアムで開催された「写真家ドアノー/音楽/パリ」のビジュアルデザインも田口氏が手掛けています。

本展開幕にあたり、ビジュアルデザインに込められた思いや、マン・レイという芸術家から感じる美学や哲学などについ田口氏に語っていただきました。
マン・レイの“レイ”(光線)のイメージから、“光の正体”を色に置き換えてみたことで、ビジュアルイメージが生まれた
本展のポスターやチラシなどのデザインは、これまでのマン・レイ展にはない新たなイメージと、Bunkamura ザ・ミュージアムらしい独自性を模索するところから始まりました。そこで、どんな風にコンセプトを考え、デザインに落とし込んでいったのかを田口氏に伺いました。
「マン・レイの写真作品は、時代的にモノクロだったので、ポスターなどのビジュアルもモノトーンの世界観で表現されることが圧倒的に多かったのです。そういった意味で、独自性、Bunkamura ザ・ミュージアムらしさを追求するにあたり色の考え方を重視しました。
『マン・レイ』って、絵画で言えば、雅号。本名は、エマニュエル・ラドニツキーなので、この謎めいた雅号は、ストレートに日本語に訳せば、「光男」「光線男」みたいな意味になります。ならば、その名前の持つ意味にちなんで、“光の正体”を色に置き換えてみたら面白いんじゃないの?というアイデアが湧いてきました。光をプリズムにかけると、虹のように、光の波長によって色調が分光されますが、それが物に反射したときにできるレインボーカラーを“光の正体”として、バックグラウンドにしてみよう、ということになりました。
プロトタイプをつくるうちに、光がにじんだような、ホログラフィックなレインボーになり、そこに柔らかさやエレガントさのある陰影感が加わって、だんだんフェミニンな色彩になっていきました。『マン・レイと女たち』という展覧会のテーマにふさわしいものになったのでは、と思っています。」
このビジュアルイメージに使われた写真は、本展にも展示されている《眠る女(ソラリゼーション)》という作品。「ソラリゼーション」とは、マン・レイが、写真を現像する際の失敗から偶発的に生まれた現象(写真の現像中に、露光が過多になることで部分的に白と黒が反転する効果)を、写真表現として用いるようになった技法です。
出来上がったビジュアルイメージは、まさに、“光”を捉えつつ、ソラリゼーションの表現性ともマッチさせています。
世界最古のファッション雑誌「ハーパース・バザー」の誌面で、「マン・レイ」に出会う
1867年にニューヨークで創刊された「ハーパース・バザー」は、世界最古のファッション雑誌で、1934年には、アレクセイ・ブロドヴィッチ(1898-1971)がアートディレクターに就任しました。
田口氏は、この世界的に有名な雑誌のアートディレクターであったアレクセイ・ブロドヴィッチに憧れて、若いころから写真集なども沢山購入し読みあさったといいます。
ブロドヴィッチは、それまでにはない、全く新しい手法やアイデアを誌面のレイアウトに取り込み、その卓越したセンスによって、ファッション性のみならず高いアート性を実現していました。現在にまで引き継がれる「ハーパース・バザー」のビジュアルの礎を作り、1940~50年代の同誌の黄金期といわれる時代を築き上げていった人物です。
田口氏は、ブロドヴィッチが、表紙や誌面にマン・レイの作品を起用していたことから、初めてマン・レイの存在を知ります。

「僕はこの時代に生きていたわけではないけれど、ブロドヴィッチのエレガントで革新的な表現に、すっかり魅了されていました。ブロドヴィッチとマン・レイのタッグは、画期的なグラフィックデザインと写真技法による素晴らしい表現で、今までの雑誌における概念を超越した最先端のものを創り上げていました。それは戦後においてファッション雑誌が一番輝いた瞬間でもありました。
また、ブロドヴィッチは、アートディレクターとして、多くの才能あるフォトグラファーを起用していましたが、当時同じくブロドヴィッチの元で活躍したフォトグラファーのアーウィン・ブルーメンフェルド(1897 -1969)など、『ハーパース・バザー』の中で、マン・レイの影響を色濃く受けて、ソラリゼーションの技法による作品を数多く残していたことも印象的でした。多くの写真家やクリエーターが、マン・レイから新たなインスピレーションを得ていたと思います。」
「女性を通して自分を模索して、それが、マン・レイの芸術として形になったものなのでは、と感じます。」
田口氏がマン・レイに感じる美学や哲学についてもお話を伺いました。
「マン・レイには、独特の美学やダンディズムがあり、それを自分の芸術表現として演出するだけでなくて、女性に対するオマージュがすごい!例えば、有名なキキ※1のアングルのヴァイオリン。誰もが目にしたことがあるのでは、と思う有名な写真ですが、自分が愛した女性は、キキやリー・ミラー※2、ジュリエット※3など、それぞれにその愛の形は違ったのだろうけれど、キキのしなやかな身体は、ヴァイオリンとしてフィギュア化し、リー・ミラーの麗しい唇は、巨大になって空に輝いています。彼女たちへの愛と彼女たちの美の秘密を突き詰めるべく分解し、デフォルメして、それが芸術としてひとつの形になったものなのでは、と感じます。
己の中に潜む美の真理を探究する上で、マン・レイにとって女性とは、ある意味、“自分という存在の一部”。めぐり逢ってきた女性たちひとりひとりを知ろうとする欲求自体や、まるで自分探しの旅のようなその過程が重要なのだと思います。そういう意味でも、今回の「マン・レイと女性たち」というテーマは、すごく意義深いですよね。」
と田口氏は語ります。
- ※1および※2:キキ・ド・モンパルナス(Kiki de Montparnasse)とリー・ミラー(Lee Miller)は、それぞれ本展、第2章で紹介される。マン・レイの元恋人であり、ミューズであった。
- ※3:ジュリエット・ブラウナー(Juliet Browner)は1946年10月にマン・レイと結婚し、生涯を共にする。本展、第3章で紹介される。
マン・レイの多才さは、ある種、アートの見本市。若い人たちにもその多才さに触れてみて欲しい
最後に、本展を楽しむヒントとなるメッセージをいただきました。
「マン・レイの多才さは、ある種、アートの見本市のよう。彫刻や写真など、ありとあらゆる手段と技法を駆使し、女性とのケミストリーの中で、自由に己の哲学を模索しながら作品づくりをしてきたのだと思います。そのマン・レイという芸術家の姿や作品は、若い人たちにとっても、一見難解に見えて、実は恋愛やファッションを通して、とても共感しやすい部分が多い作家ではないかと思います。ジャンルや表現に対する先入観を捨てて、まず感じたものに“食いついてみる余地が満載”(笑)の芸術家だと思いますので、ぜひこの展覧会で、若い人も含めて多くの人に、マン・レイの多彩な表現に触れてアートのあり方をもっと身近に感じてみていただきたいです。」
田口英之 プロフィール
アートディレクター。HANAE MORIでファッションビジネスに従事した後、独学でグラフィックデザインを学び独立、アートディレクターとしてのキャリアをスタート。美術展を中心に、ジャンル、メディアに囚われず、独特の世界観で数多くのプロジェクトを手掛ける。総合メディアプロダクションRAM代表。
取材・文 小林春日(アートアジェンダ) 撮影 大久保惠造
INTERVIEW2ファッションジャーナリスト 生駒芳子氏
圧倒的に自由な、枠にしばられない感覚で、
表現を追求してきた芸術家の世界を観てほしい

マン・レイは、“ファッション”の世界において、写真作品を中心に、現在に至るまで重要性の高い数々の名作を残しています。「Harper’s BAZAAR」や「VOGUE」などの名だたるファッション誌でも、鋭い感性と煌めくセンスで誌面を飾ったマン・レイの作品は、モード界を虜にしました。
本展では、マン・レイによる数々のファッション写真の傑作、当時のドレスやジュエリーなども多数展示しています。そこで、ファッションの世界におけるマン・レイの存在や彼が手がけた作品の魅力について、自らもマン・レイのファンだと語る、ファッション・ジャーナリストの生駒芳子さんにお話を伺いました。
マン・レイの世界観は、わたしにとっては、永遠で古びない
マン・レイについて、「ありとあらゆる形で撮られるファッション写真の一番の源流」と解釈している、と語る生駒芳子さん。
創刊の1998年から『ヴォーグ・ニッポン』、2002年から『エル・ジャポン』各誌で副編集長を歴任、2004年から『マリ・クレール日本版』編集長を務め、現在はファッションジャーナリストとして幅広く活躍を続ける生駒さんにとって、マン・レイは常にインスピレーションの源として存在していたそうです。
ファッション誌の誌面を形づくる表現を考えるときに、撮影に携わるカメラマンやスタイリストなどとともに、撮影の仕上がりイメージを共有するために引き合いに出す例えとして、「マン・レイ風に」とか「マン・レイのタッチで」というキーワードが繰り返し登場する、といいます。
「とにかくスタイリッシュで、完成度が高くて、とりわけ女性のポートレートやビューティーフォト、オブジェなどの撮影の時には、マン・レイの作品からインスピレーションを受けて、というキーワードは、繰り返し出てきます。今でも変わらず、マン・レイの世界観というのは、わたしにとっては、永遠で古びることがありません。
ファッションの世界では、『ファッション』と『スタイル』という二つの定義がありますが、『ファッション』は、時代が移り変わると古びて見えたり、過去のものになりがちですが、『スタイル』というのは永遠である、と定義づけられます。その点でいうと、マン・レイの写真には、確固たる『スタイル』があるので、永遠に古びないんです。」
ファッションもアートも今につながる流れのルーツは20世紀初頭にあった。メタフィジカルで、非日常的な、世界の扉が開いた時代
ファッション誌の撮影時に、具体的に、どんなマン・レイの作品が引き合いに出されるのかとお聞きしたところ、一番に挙げられたのが、今回の展覧会にもお目見えする《黒と白》という作品。この作品のモデルであるキキ・ド・モンパルナス※1の佇まいと、黒檀のアフリカン彫刻の頭部との明白なコントラストが印象的な作品です。
- ※1:キキ・ド・モンパルナス(Kiki de Montparnasse)は、本展、第2章で紹介される。マン・レイの元恋人であり、ミューズであった女性。
「これは、ポートレートという意味合いもあるし、ビューティーフォトを考える上でも参考にしたりします。マン・レイのように、オブジェのように人を捉えるポートレートの手法、美意識には、絶対的なものがあります。」
また、アフリカン彫刻は、ありとあらゆるアーティストにインスピレーションを与えてきた、と生駒さんは語ります。
「例えば、ピカソやキース・へリングの作品もアフリカンアートが源流と言われていますが、マン・レイもいち早くアフリカンアートにそそられて、こうした作品を撮っているのだと思います。こうした原始美術と取り合わせた表現は、非常に非日常的な、メタフィジカルな世界の表現ですよね。この時代、シュルレアリズムがでてきたり、ダダイズムがでてきたり、人間の空想の世界や、メタフィジカルな世界の扉が次々と開いた時代ではなかったでしょうか。」
目に見えているものだけが世界を構成するのではなく、目に見えない、本質的なもの、精神的なものや普遍的な真理が追求されはじめた時代の扉が開かれたのが、19世紀末から20世紀初頭。ファッションもアートも今につながる流れのルーツが、圧倒的にその時代にあった、と生駒さんは考えます。
「では、写真の世界ではどうかというと、とりわけ20世紀のファッション写真や、商業写真も含めて、やはりマン・レイがルーツだと、私は思うんですね。いまだにその流れが続いています。ファッションで言えば、20世紀初頭には、コルセットから女性を解放したポール・ポワレ(1879-1944)にはじまって、その後、ココ・シャネル(1883-1971)やエルザ・スキャパレリ(1890-1973)が登場しました。シャネルなどを見ていても、20世紀初頭に起こった流れが今なお続いていて、古びずに進化し続けていると感じられます。
写真というのは、現実世界を映すものであるはずですが、この時代にマン・レイは、ソラリゼーション※1やレイヨグラフ※2などの技法を用いて、非日常的・非物質的な世界を撮っていました。目に映る世界を超えて、目に見えない世界を、技術と表現で形にしていました。写真というメディアをつかって、ここまでの美意識と芸術性に到達できた人は、この時代には、マン・レイ以外にはいないと思います。」
- ※1:「ソラリゼーション」:マン・レイが、写真を現像する際の失敗から偶発的に生まれた現象を写真表現として用いるようになった技法。写真の現像時、露光が過多になり、モノクロ写真の白と黒が反転する。
- ※2:「レイヨグラフ」:ソラリゼーションと同様に、偶発的に生まれた技法で、カメラを用いずに、印画紙の上に直接物体を置いて感光させることで、物体の形を焼き付ける表現方法。
ジャンルを横断して、自由自在に表現するクリエイターの元祖、マン・レイの集大成が観られる展覧会
写真・絵画・彫刻・映画などの多方面の分野において、様々な形で独自の表現を試み、またアーティストのソサエティでも活躍したマン・レイ。1920年代のパリのカフェ・ソサエティで広いネットワークを持ち、キキ・ド・モンパルナスやリー・ミラーなど、ファム・ファタルを開拓する目利きでもあった。また、写真のみにおいても、芸術写真から商業写真まで、多彩な活動をしましたが、生駒さんは、現代のアートの領域にいる人たちについても、ジャンルの枠を軽く飛び越えて活躍しているアーティストが増えてきている、と実感しているそうです。
「草間彌生さん、奈良美智さん、村上隆さん、チームラボの猪子寿之さん、写真の世界でも、蜷川実花さん、荒木経惟さん、森山大道さんなど、ジャンル横断する表現を極めているアーティストが今は沢山います。
すでに100年前に、そういうスタイルを築いていたマン・レイは、ジャンルを横断して、自由自在に表現する現代のクリエイターたちのまさに元祖、といえるのではないでしょうか。」

さらに、マン・レイという芸術家は、ようやく今になって世界中で認識が持たれるようになってきた、ジェンダレス、エイジレス、ボーダレス、といった感覚をすでに持っていたことを、生駒さんは指摘します。当時から、既成概念や社会通念など、どんな枠にも囚われない自由な感性が、マン・レイの芸術表現の中に貫かれていました。
「いまの我々が考える最先端のスタイルが、マン・レイの作品にはちゃんと宿っている、というところも感じてほしいですね。今回の展覧会では、現代に通じるクリエイターの “元祖”がどんな人だったのか、マン・レイがどんな芸術表現を繰り広げていたのか、その集大成を観ることができるわけです。ひょっとしたら、現在、世界的に活躍されている多くの芸術家たちに負けないほど、皆が度肝を抜かれるくらいの世界が待っているかもしれません。なのでぜひ、この展覧会に足を運んでみてほしいですし、とくに若い方たちには、この貴重なチャンスを逃してほしくはないですね。会場で存分にマン・レイのインスピレーションのシャワーを浴びてほしい。創造のエネルギーももらえるし、驚きにも満ちているし、格好いい!と感じるでしょうし、“マン・レイを超えてみたい!!!”、と感じるくらいの感覚で見て欲しいですね。」
生駒芳子 プロフィール
兵庫県生まれ。東京外国語大学フランス語科卒業。フリーランスのライター、エディターとして雑誌や新聞においてファッション、アートについて執筆・編集。1998年より『ヴォーグ・ニッポン』、2002年より『エル・ジャポン』各誌で副編集長を歴任。2004年に『マリ・クレール日本版』編集長に就任。2008年に独立し、現在はフリーランスのジャーナリスト・プロデューサーとして活動。ファッション、アートを中心に、社会貢献、エコロジー、エシカル、女性の生き方まで幅広いテーマでの執筆、講演活動、プロジェクト設立・運営に携わる。2017年より、日本の伝統工芸をベースにしたファッションとジュエリーのブランド「HIRUME」をプロデュース。(https://www.hirume.jp) 日本エシカル推進協議会副会長、日本和文化振興プロジェクト理事、一般社団法人ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション(WEF)理事等を務める。
取材・文 小林春日(アートアジェンダ) 撮影 大久保惠造
COLUMN写真評論家 飯沢耕太郎氏
「歓び、遊び、愉しむこと」――マン・レイが撮影した女性たち
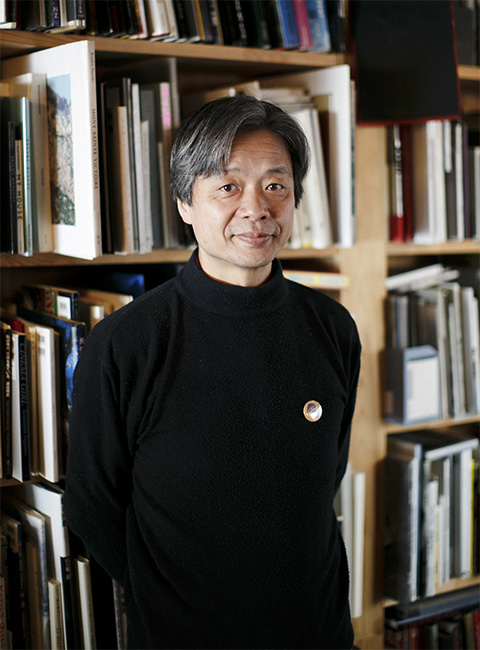
ニューヨーク時代からのマン・レイの盟友であり、お互いに強い影響を与え合ったアーティストのマルセル・デュシャンは、1959年にロンドンの現代美術研究所で開催されたマン・レイ展のカタログに寄せた文章に、次のように記した。
「マン・レイ:男性名詞。歓び、遊ぶこと、愉しむことと同義」
マン・レイの人物像を定義するのに、これほどふさわしい言葉はないだろう。彼はたしかに生涯にわたって、膨大な量の写真、絵画、オブジェなどの作品を「歓び、遊ぶこと、愉しむこと」を基本的なモチーフとして作り続けた。思いがけない発想を形にしていくことこそ、アーティスト、マン・レイの真骨頂であり、それは彼自身だけでなく、観客にも、惜しげもなく「歓び、遊ぶこと、愉しむこと」をもたらすものとなった。
ここで注目したいのは、デュシャンがさりげなく、だが的確に「男性名詞」という言葉を入れていることだ。マン・レイの作品は、明らかに「男性」によるものである。美しく魅力的な女性たちを愛し、彼女たちとの時間を心ゆくまで享受し、時には別れの痛みに心を震わせる、そんなヘテロセクシュアルな男性アーティストの視点が、どの作品にも貫かれているのだ。
フェミニズム的な見方をすれば、マン・レイの、女性の身体をオブジェに見立てたヌード写真やポートレートは、弾劾の対象になりかねないだろう。ところが、彼の作品を見ていると、そのことがあまり気にならなくなってくる。それは彼がモデルとなる女性たちを従属させ、支配しようとしているのではなく、対等、あるいはそれ以上の存在とみなし、彼女たちとの共同制作として作品を生み出していたからだろう。マン・レイが撮影した女性たち、特に彼と公私ともに関係が深かったキキ・ド・モンパルナス、リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、アディ・フィドラン、ジュリエット・ブラウナーらをモデルとした、輝くばかりの写真群を見ると、むしろマン・レイは彼女たちのこのようでありたい、このように成りたい、という欲望を素早く察知し、それを全身全霊で実現しているようにも思えてくる。
写真家・アーティストとモデルとの関係は、いまやとてもむずかしいものになりつつある。特に男性が女性を撮影したり、描いたりすることは、社会的な監視の対象になっているようにすら見える。別にマン・レイの時代をノスタルジックに回顧するわけではないが、彼がアーティストとして最も活動的だった1920〜50年代には、男女の創造的な共犯関係が成立していたのではないだろうか。それはダダイストやシュルレアリストなどの集団内での、やや特異な関係のあり方かもしれないが、その自由さはちょっとうらやましいほどだ。「マン・レイと女性たち」に焦点を当てた今回の展覧会は、そのことをもう一度考えさせるきっかけになるかもしれない。
飯沢耕太郎 プロフィール
写真評論家。1954年、宮城県生まれ。1977年、日本大学芸術学部写真学科卒業。1984年、筑波大学大学院芸術学研究科博士課程修了。『写真美術館へようこそ』(講談社現代新書1996、サントリー学芸賞受賞)、『写真的思考』(河出書房新社 2009)、『キーワードで読む現代日本写真』(フィルムアート社 2017)など著書多数。執筆活動のほか、写真展覧会の審査、企画等も手がける。
