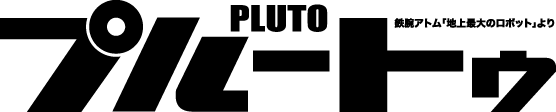2015.03.09 UP
プロダクションノートVol.5公開!
クリエイター・インタビュー
映像・装置:上田大樹さん
7つのパネル、6つのボックス、1対のフレーム、大きなスクリーン、といった装置と、映像の見事なコラボレーション。双方を手がけたのは、映像作家で、演劇作品での活躍も多い上田大樹さん。装置まで手がけるとは知らなかったけれど、
「初めてです。映像をどう映すか図面だと想像がつかなかったので、とりあえず、パネル以外のぜんぶの模型を作ってラルビに見せたんです。そうしたら、そのまま流れでやることになっちゃって(笑)
ラルビが最初に考えていたのは、本をモチーフにした装置でした。コマ割りを使うのはこちらのアイデアですけど、(コマ割りによって7つに分けた)パネルは、最後に出てきた派生物だったんです。これも模型を作っていったら、ラルビがいろいろ動かし始めてああいう使い方になったんですが、まさかあそこまで複雑なものにするとは、思ってもみなかったですね。ラルビにへんなおもちゃ与えちゃったなぁ、と思いました(笑)。あれは装置そのものには技術はそんなに使われていなくて、ただただ、ダンサーの力によるものです」
壁、テーブル、階段、墓石、電話ボックスなどさまざまに姿を変える7つのパネルの組み合わせパターンは、30種類以上におよぶ。パネルの裏側には、持ち手を兼ねたコマ割りデザインが施されていて、時には、その1つのパネル内を細かく仕切った、コマの1つ1つに合わせた映像が映しだされることもある。ラルビも細かいけれど、上田さんも、負けずに相当細かい。
ラルビとは、『TeZukA』に続いて2度目のタッグ。今回もまた「大樹なしには、この作品は成立しない」と、その仕事ぶりを絶賛されている。
「まず原作の漫画と台本を読んで、この作品の中にある、悲しみ、憎しみ、喜びといった、感情の種類を拾い上げてパターンを作り、悲しみはオルガ、憎しみは僕、という風に感情ごとに担当を割り振りました。西洋楽器は、伝統的にハーモニーの要素が強いので、コード進行や和音を多用した音作りはオルガに任せて、僕は、ちょっとプリミティブな音を使うことに努めました。
太鼓や能管と歌は、僕と阿部好江さんの2人で演奏し、後は電子音楽ソフトの音源を使って音を作っています。ふだんは、楽器の皮と湿度のバランスをみたり、竹を削って音を調節したりする世界にいるんですが、今回初めて、ソフトを揃えてパソコンで音楽を作りました。前半はロボットらしさを出すために、機械的に作った感じを残しておき、後半の、ボラーが出てくるあたりからは、ほとんど電子音を入れずに、生演奏のようにテンポが揺れる感じを生かしたりして、人間味を出そうと努めました。一辺倒でない感情を作品から感じていたので、わかりやすいだけでなく、ちょっとひねりたいところもあったんですが、なかなか難しかったですね」
『BABEL』をはじめ、ラルビとの仕事はこれが4作目になる。その基本姿勢に共感しながら、多大な影響を受けているという。
「僕は民族芸能を研究してきたので、ダンスと音楽を分けて考えること自体、ナンセンスだと思っているんです。芸能は祈りから始まって、歌や踊りが一体になったもの。それが時代によって、細分化・分業化されていっただけなんです。動きが奏で、音楽が踊る。ラルビはこの本質を、的確にとらえていると思います。しかも細かく分析したうえで、俯瞰して両者を一緒にする。その分析と俯瞰の往復を何度も何度も繰り返してゆくんです。それはもう、怖ろしいくらいに。生半可な先入観でダンスや音楽をとらえていると、ついて行けなくなります。コンテンポラリーダンス云々という次元ではなく、”人間”のおもしろさをどうコラージュしていくかということに、ラルビの関心はあるのだと思います。美術的にも優れているし、総合芸術の創り手の先輩として、ものすごく刺激を受けています」
いつのまにか装置まで手がけることになった上田さんと、パソコンで電子音楽を作ることを体得した吉井さん。二人とも、類い希な才能をラルビに見込まれ、自身の能力の幅を、どんどん広げている。
文:演劇ジャーナリスト 伊達なつめ 撮影:小林由恵