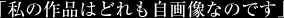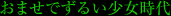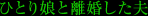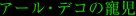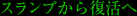美しき挑発 レンピッカ展
2010年3月6日(土)−5月9日(日)
Bunkamura ザ・ミュージアム
展覧会紹介
強烈な個性を放つ女性画家として、タマラ・ド・レンピッカは今最も注目されている画家の一人である。誰の脳裏にも焼き付いて離れないのは、画面からはみ出さんばかりの圧倒的な存在感を持つ女性像。筆跡のない金属的な光沢を放つ肉体は、まるで大型のモーターバイクのように官能的だ。人を挑発する鋭いまなざしも、レンピッカの描く人物の特徴である。たしかにそこには彼女自身が投影されている。20世紀を代表する肖像画家の一人であるタマラ・ド・レンピッカとは、一体どんな画家なのだろう。
本人は1898年にワルシャワで生まれたと豪語するが、実際にはその前年にモスクワで生まれたという説がある(歳をごまかしている?)。家は裕福で、スイス、ローザンヌの中学校に通ったが退屈だったという。そのころ彼女は仮病を使って、祖母に療養と称してイタリア旅行に連れて行ってもらう。そこではルネサンスの爛熟期のマニエリスム絵画に熱中した。レンピッカ特有の緊張感ある不自然なポーズや顔の表情の原点は、ここにあるのかもしれない。
その後18歳でポーランドの貴族タデウシュ・ド・レンピッキ伯爵と結婚し、サンクトペテルブルクに住まう。しかし1918年ロシア革命の混乱を逃れてパリに逃れてきたとき、二十歳そこそこの彼女はまだ画家ではなかった。きっかけは、弁護士だった夫が働こうとしないため、生活のために画家となって自立しようと決心したことだった。師事していたのはナビ派のモーリス・ドニと後期キュビスムの画家アンドレ・ロート。量感を強調し、金属パイプを意識させるキュビスム的なレンピッカの造形的特徴は、通奏低音として作品に宿ることになる。こうして、意欲もさることながら才能も手伝って、2年後には展覧会に出品するまでになる。
画家として本格的な活動を始めた1920年代。両大戦間の束の間の平穏をむさぼるかのように文化が花開き、大胆な風俗が現われ、都会のライフスタイルが確立し、女性が社会に進出しはじめた。レンピッカはまさにその実践者であり、肖像画家として自らの様式を確立し、30年代半ばまでの10数年間に、強烈な個性が光る多くの傑作を世に送り出した。
モデルとなった人物の中には社交界を賑わす有名貴族、アンドレ・ジッド等の文人、そして売れっ子画家に肖像画を注文する富豪たちに加え、キャバレーの人気歌手シュジー・ソリドールもいた。かつてランヴァンのモデルだったこの歌手は、両性具有的なルックスと低い歌声で人々を悩殺する魔性の女性だった。当時多くの有名画家がその肖像を描いたが、レンピッカの場合は特別だった。彼女の愛人だったのである。同性愛はある意味でこの時代の自由度の象徴でもあったが、もうひとり、イーラ・Pもレンピッカの愛人となった女性である。円熟期にあった1930年、レンピッカはその肖像を描く。優雅なポーズ、均整のとれた官能的な肉体。作品には時代に支持された画家としての自信がみなぎっている。この特徴はさらにのちの1932年、イギリス生まれでパリのキャバレーで活躍していたグラマラスな歌手マルジョリー・フェリーを描いた肖像では完璧の域に達し、その女性像は女神としか言いようのないカリスマ性を持つに至っている。
娘のキゼットもレンピッカのお気に入りのモデルだった。少女から大人になる不安定な心が見事に表現された作品《ピンクの服をきたキゼット》は、ナブコフの小説「ロリータ」の表紙にも使われ、観る者を誘惑する視線を投げつける。それに比べて、《緑の服を着た娘》ではキゼットにはもはや少女の面影はない。美しい肉体をもち、優雅にして意気揚々とした姿で描かれた大人の女性が、鋭い視線で男を、そして女を挑発する。レンピッカは娘の姿に、若い頃の自分の姿を投影しているのだ。
レンピッカは男性像も多く残している。そのうちのひとつ夫タデウシュの肖像は、いかにも彼女好みの美丈夫として表現されている。レンピッカが愛したこの男は、それでも夫というよりは非家庭的なアマン(情夫)の魅力と危なさとを併せ持っている。結婚指輪をはめた左手が完成していないのは、描いている途中で離婚することになったためだが、そこには奔放な生活をエンジョイしていたはずの彼女の心の闇が、見え隠れする。
レンピッカの仕事に最も脂がのっていた時代、アール・デコと呼ばれる幾何学的で機能美を意識した骨太の様式が装飾美術やファッションを席巻していた。しかしレンピッカの芸術をアール・デコの文脈で語るには慎重さが要求される。彼女はアール・デコに触発されてその様式を確立したのではなく、その発信のひとつであったと同時に、互いに影響しあって自分たちの時代に最も相応しい造形美を追究していたのだ。
そのひとつがニューヨークの摩天楼に対する美意識である。時代の象徴というよりは、自らの感性に合う造形美として、レンピッカは作品の背景に積極的に取り入れている。またこれらの造形は、キュビスム的な量感を持つ形態の模索の延長線上にあると考えることもできる。一般的にアール・デコは純粋な絵画芸術を語る際にはあまり用いられない概念だが、レンピッカという画家を登場させることにより、絵画史におけるその空白が埋められると言っても過言ではないだろう。
逆に当時のファッションに完全に触発された例もある。《サン・モリッツ》という作品に描かれたスキー姿の女性像は、当時のポスターをもとに制作されたが、結果的には彼女のオリジナルと言えるほどの完成度を獲得しているのである。
「最大のクライアントと結婚してしまった」。冗談交じりにこう語るレンピッカは、1933年クフナー男爵と再婚するが、ナチスの台頭でアメリカへ逃れる。華やかな生活が続き、当時有名だった映画関係者をハリウッドの自宅に招いていた。そして世の中に戦争の暗雲が立ち込めはじめた1935年ごろから、身近な世界を描くことをやめてしまう。鬱病に苦しめられながらも、絵筆を捨てたわけではなかったこの時期。描かれた作品は、かつての妖艶さとは異質の、宗教的なテーマや社会問題を扱ったものが多かった。中でも出色の作品として《修道院長》がある。当時のレンピッカの心の苦悩を知らないものが見ても感動を与える年配の女性像。派手さを払拭したその純粋な肖像画は、逆にかつての華やかな人物像に改めて接したくなるような奥行きを具えている。
その後、1941年ニューヨークとロサンゼルスで個展を開き成功を収まるが、大戦の影響は否定できなかった。1950年以降、彼女は完全に忘れられた存在となり、ヨーロッパではムッソリーニ時代を思い出させるとして拒絶された。それでも静物画を描いたり抽象画も試みたりするのだが、必ずしも成功したわけではなかった。
再評価は1972年の回顧展が契機だった。ようやくの栄光を手にしたレンピッカだったが、1980年、その波乱万丈の生涯を閉じる。
激動の時代を駆け抜けた女性画家タマラ・ド・レンピッカ。なりたいと思った画家になり、自由奔放に生きたひとりの女性。逸話は有り余るほどある。だが、まずは作品と対面しよう。全てはその画面のなかに込められている。ナマの作品のもつ迫力。展覧会でしか得られない興奮と感動。これは今時にしてはちょっと硬派の、パワー・エギジビションなのである。
Bunkamuraザ・ミュージアム 宮澤政男