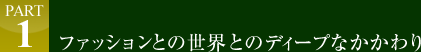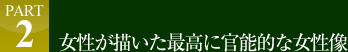美しき挑発 レンピッカ展
2010年3月6日(土)−5月9日(日)
Bunkamura ザ・ミュージアム
学芸員によるコラム
レンピッカの生きた20世紀前半、女性解放が進展するなか、女性の身体を窮屈なコルセットから開放したのはファッションデザイナーの草分け、ポール・ポワレで、1910年のことであった。サンクトペテルブルクで少女時代を過ごしていたレンピッカは、母や叔母がパリから取り寄せたポワレのドレスに夢中になっていた。もっとも女性ナチュラルなボディーラインの再発見につながるポワレの偉業といわれても、幼い彼女には難しすぎただろうが、自分自身が将来作品のなかでそれを追究することになるわけである。
パリに出てきた20年代、ファッションはシャネルの時代になっていた。女性の服装は男性服の生地を応用したりして、装飾を削ぎ落としたものが一世を風靡し、レンピッカの描く女性の服にもそれはよく表れている。シャネルは友人だったが、もっと仲がよかったのはそのライバルであるスキャパレリだった。スキャパレリはギャルソンヌ・ルックに対抗して、ダリのシュルレアリスムなど前衛芸術を自身のデザインに取り入れていったデザイナーである。
そんな中で、レンピッカの世界に一番近いともいえるデザイナーが登場する。マダム・グレである。もともと彫刻家になりたかったこのデザイナーは、美しいドレープやプリーツを駆使した芸術的なドレスで社交界の女性たちを魅了した。レンピッカは女性の身体が美しく見えるグレの古代ギリシア風ドレスが大のお気に入りで、1930年代初頭の絵画作品に盛んに描かれている。
デザイナーたちとの付き合いの仲で、レンピッカは有名デザイナーからただでドレスをもらうようになっていた。フォトジェニックな美貌の持ち主であったレンピッカは、いわば歩く広告塔とみなされたのである。
そして今回、久々の日本展をきっかけにデザイナーの桂由美がレンピッカの作品をモチーフにドレスをデザインし2010年1月にパリで発表される。《カラーの花束》というレンピッカ作品に注目し、彼女が描く官能的な女性を彷彿とさせるこの花がどうドレスに組み入れられるのか、興味の尽きないところである。
Bunkamuraザ・ミュージアム 宮澤政男
流行のドレスをまとうグラマラスな女性たち。挑発の、あるいは恍惚のまなざし、そして肉感的としか表現できないような身体。しかもそのドレスは、乳首や臍まで、身体のラインを容赦なく浮き出させる。レンピッカという女性画家における典型的な美の世界である。
二つの世界大戦に挟まれた時代、それは狂乱の時代とも呼ばれ、人々が束の間の平和をむさぼるように謳歌した時代でもある。レンピッカはそんな時代の寵児として、自らの本能のままを生き、その美学にかたちを与えていった。では彼女の本能とは何か。その一つは紛れもなく同性愛であった。女性解放が進んだ時代、レズビアンは流行の中にまぎれながらも、少しずつ表に出てきていた。子供もいたレンピッカの場合はバイセクシュアルというべきかもしれないが、男たちの視線を釘付けにするような女性像は、女性の肉体に性的魅力を感じたレンピッカならではの芸術なのだ。その傑作の一つ《イーラ・Pの肖像》のモデルは彼女の愛人であった。少年のようなルックスで、低い声でレズビアンの恋を歌い上げた人気歌手シュジー・ソリドールとも肉体関係を重ねたが、その肖像画はソリドールからの注文で、レンピッカはヌードで描くという条件で承諾したという。
官能的な女性像のベースには、レンピッカのこうした志向と共に、独自の造形言語がある。その源泉の一つが、幼い頃に見たイタリアルネサンス、とくにマニエリスムの絵画である。少し身体をくねらせ、不思議な緊張感と迫力を持つ人物像はそこから来ている。後期キュビスムの画家アンドレ・ロートに師事した点も重要である。人体を円柱や円錐などの単純な立体で構築するような傾向があるのはそのためである。また、つるんとした肌の感じは、彼女が愛した古典主義の画家アングルの裸婦を思い出させる。レンピッカという画家は、思いのほか美術史の本流にいた芸術家なのである。
一世を風靡した画家タマラ・ド・レンピッカ。久々の日本展でとりこになるのは、男性だろうか、それとも女性だろうか。
Bunkamuraザ・ミュージアム 宮澤政男