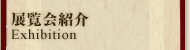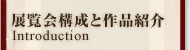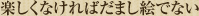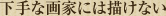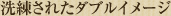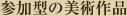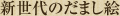美術ファンでなくても これだけは見逃せない!
だまし絵展と聞いただけで、なにかおもしろい体験ができるのではないかと期待しないだろうか。日本美術や現代美術も含めた古今東西の力作を一堂に会する本展は、その期待を裏切らない。そこには芸術家が凝らした様々な仕掛けが繰り広げられている。だまされるか、だまされないか。実はそれはあまり重要ではない。むしろこれらの仕掛けや工夫を通じて、古の画家の熱い思いに直接触れ、作る側と観る側との緊張感を味わうことができるところに、この展覧会の楽しさがある。それが現代作家なら、お手並み拝見と言ったところである。 |
 |
壁のシミがいくら顔に見えても、それは偶然のいたずらであってだまし絵ではない。だまし絵とは芸術家が生み出す作品であり、しかも作者の思惑が幾重にも積み重なった創作なのだ。壁のシミも、室内を描いた作品の中に取り込んでしまえば、隠し絵という形式のだまし絵になる可能性がある。しかしそれが「可能性」に過ぎないのは、画家の技量が問われるからに他ならない。だまし絵はアイデアではなく、実践なのだ。
そもそも絵画そのものがだまし絵的な性質をもっている。古来、画家は本物そっくりに描くことに情熱をそそいできた。遠近法の導入はそれに拍車をかけることとなり、奥行きや影をつけて立体感を持たせて描くことに努力が向けられた。そして細密描写はその基本だった。だが本物と間違われるためには、さらにプラスアルファの工夫が必要だった。こんどは画家がイニシアティブをとって、観る側に積極的に仕掛ける番となったのである。だまし絵の楽しさと緊張感はここから生まれてくる。

おそらく人類は早い時点から、小石や木の実を使って人の顔を地べたに作っていたに違いない。あるものを別のものに見せるというダブルイメージを、洗練の極致にまで高めたのが16世紀のイタリアの画家ジュゼッペ・アルチンボルドである。
ハプスブルク家に仕えたこの宮廷画家は、宮廷の儀式を取り仕切り、世界中の美術品や珍品奇品、珍獣や希少植物を収集することも仕事とし、その高い教養と博物学的知識を元に、数々の奇怪な胸像を世に送り出した。中でも、ルドルフ2世の肖像は、アルチンボルド晩年の最高傑作と言われている。皇帝を四季折々の野菜や果物を用いて豊穣の神ウェルトゥムヌスの姿に仕立て、すべてを支配する皇帝と帝国の繁栄を祝福しているのである。ただし、ルドルフ2世は政治を顧みず、ひたすら学問や芸術を奨励し、とりわけ錬金術に没頭し、そこにはまさに「奇想の王国」が築き上げられた。

だまし絵は「遊び」という側面を強く持っている。一見したところ何が描かれているのか分からないものが、ある一定の見方をすると何だか分かってくるというのがアナモルフォーズと呼ばれる歪曲像である。これは遠近法の技術を応用して作成された。特別な見方をして初めて分かるこのような図像は、時の権力者に対する批判や、卑猥なイメージを表すために用いられることもあった。
比較的早い作例は、遠近法の研究者で画家のデューラーの弟子であった16世紀のドイツの画家エアハルト・シェーンの「判じ絵」にみられる。また、円筒を用いたアナモルフォーズもよく知られている。中央に円筒形の鏡を置くと像が結ばれるというもので、ドーナツのような作品自体は、なにが描かれているのか全く分からない。本展には日本のアナモルフォーズである鞘絵も展示される。これは刀の鞘に映して正像を見るという粋な発想である。

17世紀、オランダでは静物画が発達する。それは新教国ではストレートに宗教的な主題でないものが好まれたという背景がある。特にヴァニタス(はかなさ)をテーマにしたものが多く、頭蓋骨を描くことでこの世のはかなさ、人生の無常を示す直接的なもののほかに、盛り花や華奢なグラスなどによって代弁させることも行われた。このような状況の中で、あたかもそこに本当に戸棚があるように、本物の手紙がはさまれているように、つまり実体のないイリュージョンを描くことでヴァニタスのテーマを表現する画家も現われた。のちにトロンプルイユ(目だまし)と呼ばれるようになるこれらの絵画は、静物画の兄弟だったのだ。
トロンプルイユを制作するには、それが掛かっている同じ壁面で展開しているように設定し、実物大で本物そっくりに描く必要がある。つまり画家としての力量が問われるわけである。この大家として名高いのが、ヘイスブレヒツである。生涯については不明な点も多いが、17世紀の画家で、主にオランダで活躍し、デンマーク王室に仕えたことが知られている。
トロンプルイユにはもはや静物画という範疇で語ることが出来ないものもある。その典型が、額の外に人物がはみ出して描かれる作品群である。肖像画における遊び的な作品が多い中で、スペインの画家ボレル・デル・カソの描く少年像は、真に迫った迫力があり、この分野の傑作である。
だまし絵は19世紀後半のアメリカでも盛んに制作された。大西洋を渡っていったトロンプルイユには、オランダにおけるような教訓的なものを求めるよりも、遊びの要素が強いという点が、国民性と合致したのだろう。ここではハーネットやピート等が名人芸を繰り広げている。

日本ではヨーロッパとは一線を画しただまし絵が発達した。特に「寄せ絵」と呼ばれるものは、いわば日本版アルチンボルドとも言うべきもので、代表的な絵師に歌川国芳がいる。舶来の文物で知ったのか、それとも独自の発想なのか、はっきりしたことは分かっていない。作者は滑稽さを狙っており、顔を構成する人物のしぐさも、ひとつひとつがおもしろい。
掛軸の世界でもだまし絵は独自の発達を遂げ、琳派の絵師を中心に江戸時代末期から明治にかけて流行した。これは描表装(かきびょうそう)と呼ばれるもので、通常は織物の掛軸の柄をあえて手描きにし意表をついたもの。描表装は次第にエスカレートし、河鍋暁斎の《幽霊図》のように、モチーフが表装部にはみ出すような大胆なものまで出現する。描表装が画期的なのは、油彩による写実性を追究した西洋絵画とは全く異なる次元でだまし絵を実践している点である。掛軸の中の世界という設定は、淡白な日本的絵画表現の限界を超越し、西洋のだまし絵の迫真性に匹敵するイリュージョンを生み出している。
ダリとマグリット。スペインとベルギーが生んだ二人の巨匠の作品は、本展のハイライトのひとつ。両者の傾向を表わす超現実主義(シュルレアリスム)という言葉通り、二人とも現実にはありえない世界を、まことしやかに提示する。ダリはその描写力にものを言わせ、ダブルイメージを出現させることで自身の超現実世界を演出。これに対してマグリットは、「描かれたイメージ」自体の虚構性を告発しながら、極めて知的な遊戯性を具えただまし絵を展開した。
この時代、独自の地位を獲得した芸術家にエッシャーがいる。その全ての作品がだまし絵と言うわけではないが、優れた細密描写がそのアイデアを具現化したという点では、それまでのだまし絵の集大成のひとつと言えるだろう。
そして21世紀。今日、だまし絵を論ずること自体可能なのかというほど、芸術表現は多様化した。写真や映像はもとより、CGによるヴァーチャル・リアリティは、かつて画家たちが本物らしく描くことに腐心したことを微笑ましく思わせるほどの完成度を獲得しつつある。しかしあくまでも芸術という枠にこだわるとき、21世紀の芸術家は、むしろ人間の視覚という限られた枠を意識的に取り上げることで、機械・コンピューター時代における人間の復権に寄与しているのである。
古今東西のさまざまなだまし絵を前にし、まずは肩の力を抜いて、楽しんでみてはどうだろうか。
Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男