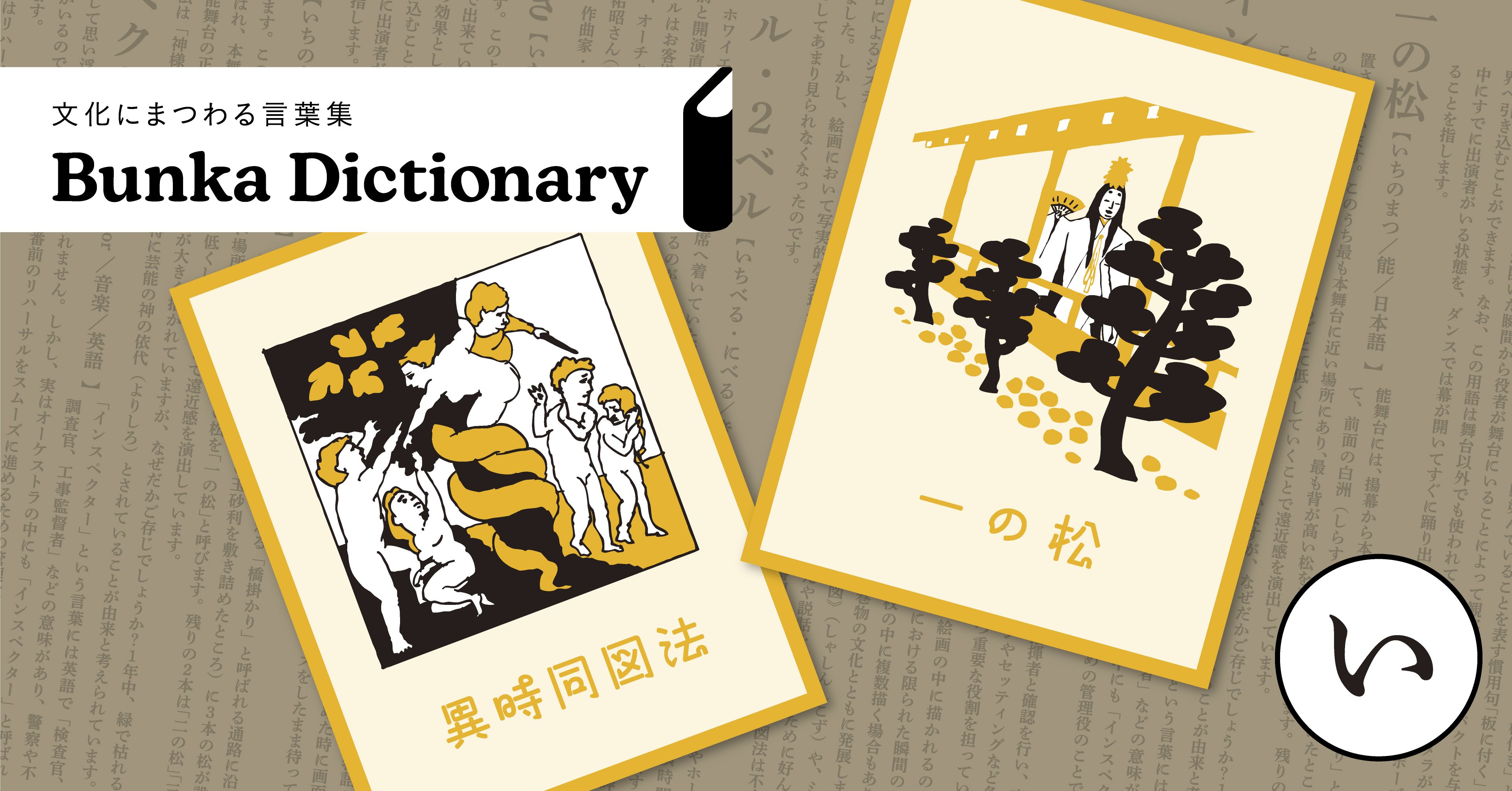
第2回「い」
クラシック音楽、演劇、アートなどには独特の専門用語が使われていて、知っておくと文化芸術をもっと楽しめるようになるものがたくさんあります。そうした用語の数々を、誰かに話したくなるようなトリビアを交えて解説する「Bunka Dictionary Bunka辞典」。第2回は「い」です。
【異時同図法】いじどうずほう/アート/日本語
一般的に1枚の絵画の中に描かれるのは、特定のシチュエーションにおける限られた瞬間のみ。それに対して、コマ割りで展開を表現する漫画のように、同一人物の異なる瞬間の所作を1枚の中に複数描く場合もあります。こうした“時間の経過”を表す手法は「異時同図法」と呼ばれ、横方向に読み進める絵巻物の文化とともに発展しました。 異時同図法の有名な例として、法隆寺に所蔵されている7世紀の仏壇画《捨身飼虎図》(しゃしんしこず)や、ミケランジェロによるシスティーナ礼拝堂の天井画《原罪と楽園追放》などがあり、宗教の教えや説話を表現するために好んで用いられました。しかし、絵画において写実的な表現が確立されるようになると、異なる時間が混在する異時同図法は不自然なものとしてあまり見られなくなりました。

【1ベル・2ベル】いちべる・にべる/音楽・演劇・ミュージカル/日本
劇場やホールで公演の開演時間が迫ると、ホワイエなどにいるお客様に座席へ着いていただく“客入れ”の合図として、ブザーや鐘の音が鳴らされます。開演5分前と開演直前の合計2度鳴らされるのが一般的で、前者を「1ベル」、後者を「2ベル」または「本ベル」と呼びます。1ベルはお客様に着席を促すとともに、「もうすぐ始まるぞ」という公演への期待感をあおる役割もあります。 なお、オーチャードホールで流れる1ベルは、1989年の開館当時ヤマハに在籍されていた音プロデュースの第一人者・井出祐昭さん(現・井出 音 研究所 所長)が制作したもの。2014年に開催した『オーチャードホール25周年ガラ ~伝説の一夜』では、作曲家・鈴木優人氏が特製の開演ベルを作曲してくださいました。
オーチャードホール 1ベル
【板付き】いたつき/演劇、映画/日本語
演劇や歌舞伎で開演と共に幕が上がると、役者が舞台袖から登場するのではなく、ステージ上の立ち位置でスタンバイしていることがあります。このように、幕が開いた時に役者がすでに舞台に出ている状態を舞台用語で「板付き」と言います。ステージの床が板で出来ていることがその名の由来で、役者が舞台に馴染んでいることを表す慣用句「板に付く」の「板」と同じ由来です。 板付きの効果として、幕が開いた瞬間から役者が舞台にいることによって観客に強いインパクトを与え、たちまち物語の世界へ引き込むことができます。なお、この用語は舞台以外でも使われていて、映像業界ではカメラが回り始めた時に画面の中にすでに出演者がいる状態を、ダンスでは幕が開いてすぐに踊り出せるようダンサーがじっとポーズをしたまま待っていることを指します。
【一の松】いちのまつ/能/日本語
能舞台には、揚幕から本舞台へとつながる「橋掛かり」と呼ばれる通路に沿って、前面の白洲(しらす。白い玉砂利を敷き詰めたところ)に3本の松が設置されています。このうち最も本舞台に近い場所にあり、最も背が高い松を「一の松」と呼びます。残りの2本は「二の松」「三の松」と呼ばれ、本舞台から遠ざかるごとに低くしていくことで遠近感を演出しています。 ところで、能舞台の正面奥にある鏡板にも松が大きく描かれていますが、なぜだかご存じでしょうか? 1年中、緑で枯れることのない松は「神様が宿る木」といわれ、特に芸能の神の依代(よりしろ)とされていることが由来と考えられています。

【インスペクター】Inspector/音楽/英語
「インスペクター」という言葉には英語で「検査官、調査官、工事監督者」などの意味があり、警察や不動産の職業として思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、実はオーケストラの中にも「インスペクター」と呼ばれる役割の人物がいるのです。指揮者を交えた本番前のリハーサルをスムーズに進めるための管理役のことで、主に楽団員の中から選ばれます。 インスペクターはリハーサルの開始時刻、終了時刻、練習の曲順や時間配分について指揮者と確認を行い、事前に楽団員に伝えます。リハーサル中の時間管理もインスペクターの役割で、さらにライブラリアンやセッティングなど各係とのやり取りも行います。このように、インスペクターは指揮者や裏方と楽団員との間を取り持つ重要な役割を担っているのです。



