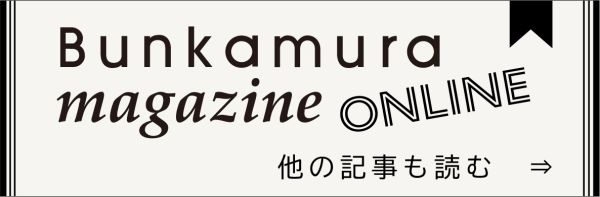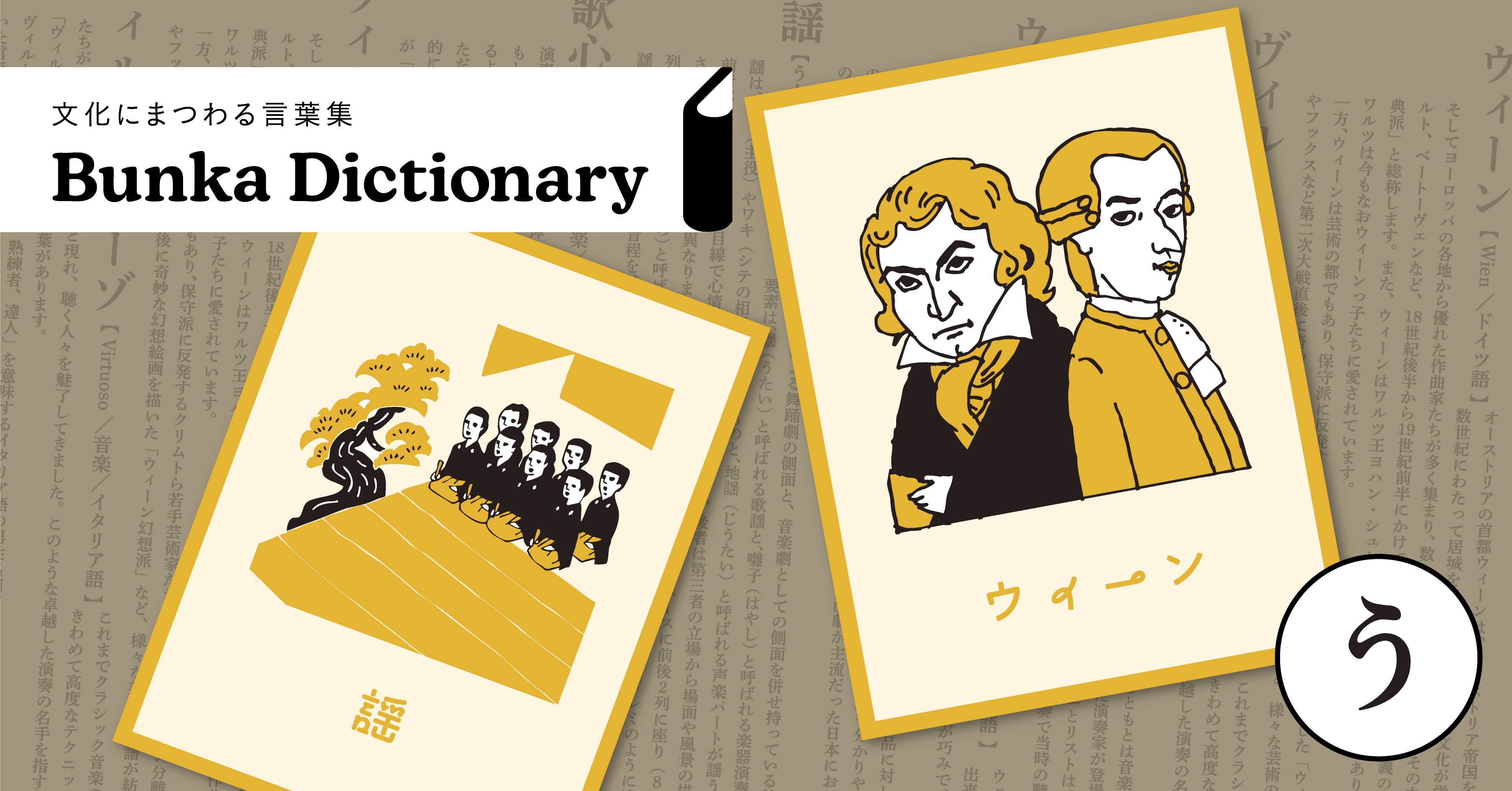
第3回「う」
クラシック音楽、演劇、アートなどには独特の専門用語が使われていて、知っておくと文化芸術をもっと楽しめるようになるものがたくさんあります。そうした用語の数々を、誰かに話したくなるようなトリビアを交えて解説する「Bunka Dictionary Bunka辞典」。第3回は「う」です。
【ウィーン】Wien/ドイツ語
オーストリアの首都ウィーンは、オーストリア帝国を統治したハプスブルク家が数世紀にわたって居城を置いたことから貴族文化が栄え、音楽の都として発展。そしてヨーロッパの各地から優れた作曲家たちが多く集まり、数々の名曲を創造しました。その中でも、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど、18世紀後半から19世紀前半にかけてウィーンを中心に活動した古典主義の作曲家たちを「ウィーン古典派」と総称します。また、ウィーンはワルツ王ヨハン・シュトラウス2世の活動拠点でもあり、彼が作曲したウィンナ・ワルツは今もなおウィーンっ子たちに愛されています。 一方、ウィーンは芸術の都でもあり、保守派に反発するクリムトら若手芸術家たちが結成した「ウィーン分離派」、ハウズナーやフックスなど第二次大戦直後に奇妙な幻想絵画を描いた「ウィーン幻想派」など、様々な芸術の系譜が紡がれました。
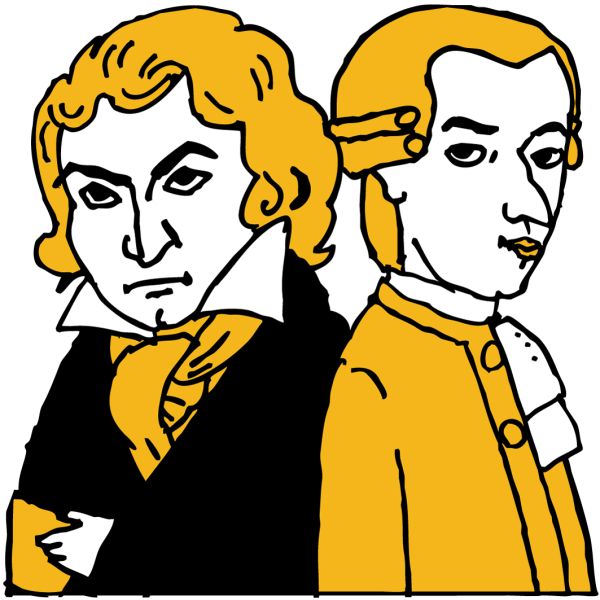
【ヴィルトゥオーゾ】Virtuoso/音楽/イタリア語
これまでクラシック音楽の歴史において、きわめて高度なテクニックを持つ演奏家たちが洋の東西を問わず次々と現れ、聴く人々を魅了してきました。このような卓越した演奏の名手を指す音楽用語として「ヴィルトゥオーゾ」という言葉があります。 ヴィルトゥオーゾとは「博識、熟練者、達人」を意味するイタリア語の男性名詞。もともとは音楽以外の分野でも使われていた言葉ですが、19世紀にピアノなどの楽器の発達に伴って類まれな表現技術を持った演奏家が登場すると、ヴィルトゥオーゾが演奏の名手を指す言葉として定着しました。なお、作曲家として有名なパガニーニとリストは、それぞれヴァイオリンとピアノのヴィルトゥオーゾとしても知られ、圧倒的な超越技巧によるスリリングな演奏で当時の聴衆を熱狂させました。
【ウェルメイド・プレイ】Well-Made Play/演劇/英語
ウェルメイド・プレイとは、出来や構成が良いという意味の「ウェルメイド」と、演劇を表す「プレイ」が合わさった演劇用語。脚本や作品の構成が巧みで、物語が論理的にもしっかりしていてストーリー展開を楽しむことができる劇を指します。 もともとは、19世紀フランスの劇作家スクリーブが芸術性よりも娯楽性を追求して書いた作品に対して、「筋が良くできているだけで中身がない芝居」という皮肉を込めて名づけられたものでした。しかし、演劇を分かりやすく気軽に楽しめるものとした意味でウェルメイド・プレイの功績は大きく、古典芸能や難解な演劇が主流だった日本においても演劇を身近なものにする役割を果たしました。
【謡】うたい/能楽/日本語
身体表現による舞踊劇の側面と、音楽劇としての側面を併せ持っている能楽。このうち音楽の要素は、謡(うたい)と呼ばれる歌謡と、囃子(はやし)と呼ばれる楽器演奏で成り立っています。 謡は、シテ(主役)やワキ(シテの相手役)が謡うものと、地謡(じうたい)と呼ばれる声楽パートが謡うものに分けられます。前者が登場人物の一人称目線で心情を語るものであるのに対し、後者は第三者の立場から場面や風景の描写を行って劇を進行させるという点で役割が異なります。地謡は舞台上の地謡座と呼ばれるスペースに前後2列に座り(8人構成が一般的)、後列中央部の地頭(じがしら)と呼ばれる謡い手が中心的な役割を果たします。なお、謡にはドレミのように決まった音階がなく、謡本に書かれた相対的な音程を基に、シテや地頭が自由に考えています。
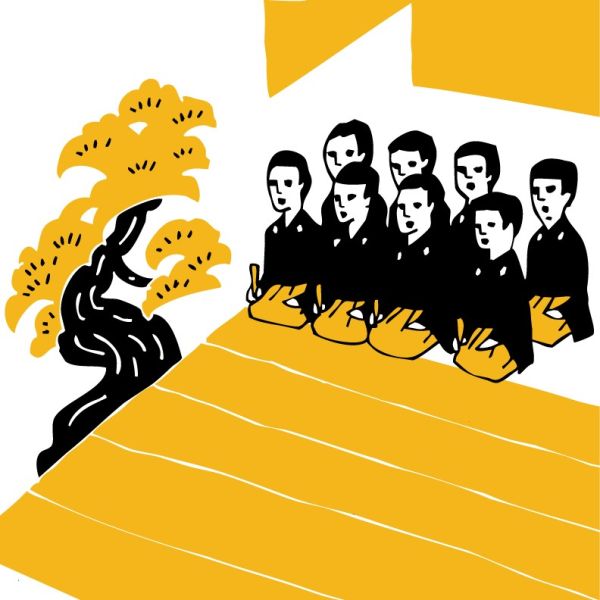
【歌心】うたごころ/音楽/日本語
本来「歌心」とは、和歌を詠もうとする心持ちや和歌への素養を指す言葉。クラシック音楽においても、フレーズの1音1音に込められた情感を詩情豊かに表現した演奏に対して「この人が弾くピアノは歌心がある」と評されることがあります。楽器なのに歌?と不思議に思う方もいるかもしれませんが、音楽の発想に関する標語として「カンタービレ(イタリア語で「歌うように」の意味)」という用語があるように、聴衆の心を揺さぶる演奏を実現するには「歌心」は切っても切り離せないものなのです。