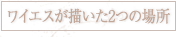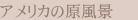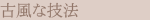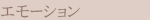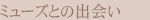展覧会紹介

|
この画家が描く荒涼とした自然に、あるいは切妻屋根のカントリーハウスに、そして人々の素朴なまなざしに、アメリカの原風景のようなものを感じる人も多いだろう。ワイエスは生涯のほぼ全ての時期を、アメリカ東部、生まれ故郷のペンシルヴェニア州チャッズ・フォードの丘陵か、夏の別荘があった北部メーン州の海辺で送り、絵を描いた。どちらもこれといった特徴のない、平凡な田舎なのだが、この国の殆んど土地がそうであるような「何もない素晴らしさ」を、日常の一こまを、見過ごしがちな部屋の一角を、肯定的にあるがままに描いたのだ。それら心にしみる物静かな情景は、かつて開拓民であったアメリカ人の心を捉えた。そしてそれは私たち日本人の琴線にも触れ、多くの根強いファンを生み出したのである。
一九一七年生まれのアンドリューは、五人兄弟の末っ子として生まれ、父ニューウェル・コンヴァース(通称NC)・ワイエスは挿絵画家だった。幼い頃から病弱だったアンドリューは、学校には行かず、家庭教師から勉強を教わり、父からは絵の手ほどきを受けた。息子を立派な画家にすることは父の夢でもあった。というのも、父はたしかに『宝島』や『ロビンフッド』といった少年向けの冒険物語などの挿絵で生計を立てる職業画家であったが、純粋な芸術家ではないという劣等感がその背景にあったといわれている。しかしその夢は現実となった。12歳にして早くも出版社から挿絵の依頼を受けるという早熟ぶりを示したアンドリューは、20歳でニューヨークの画廊で水彩画の初の個展を開き、全作品完売という大成功を収めるのである。あの驚嘆すべき描写力は、いわば天性のものであった。
翌年21歳のとき、アンドリュー・ワイエスは義兄であり父の弟子ピーター・ハードからテンペラ画法の手ほどきを受ける。この技法はワイエスが影響を受けたというイタリア・ルネサンスの画家ピエロ・デラ・フランチェスカも用いているが、手間がかかるため15世紀に油彩が登場してからは廃れていった。原理としては鉱物を粉にした顔料に、固着材として卵黄を加え、それを水でのばしていく。ワイエスは水彩の軽やかさ、自由さを好み、逆に油絵具の重い感じにはなじめなかったというが、テンペラによって得られる軽やかな色の乾いた質感は、彼の好むところであった。事実、心にしみるような寂寥感を表現するのには、極めて適した技法といえる。もっとも、その効果を得るためには、半透明の絵具を何度も薄く塗り重ねるという忍耐が要求される。しかも卵を使うために普通はその日に使う分の絵具を計算して毎日調合しなければならない。また、構図などの変更もできないため、多くの試作、習作を重ねた上で取り掛かる必要がある。

|
逆に言えば、画家の沸き起こった感情(エモーション)を直接投影しているのは、テンペラの完成までに制作されるあまたの素描や水彩画なのである。そしてそのなかには、注目すべき作品も数多く存在し、高い完成度を示す作品もある。
まず鉛筆による素描についてワイエスは、非常に情緒的で、非常に素早く、まったく予想もつかないという。「とても素晴らしい黒の鉛筆の芯を強く押しつける。そうすると、芯が折れることがある。そうやって、対象との間に起こる私の強い印象を表現するのだ」。そして鉛筆は「物の本質をつかむのを助けてくれる」のである。
そして次の段階で水彩が登場する。水彩の長所は「その時感じたことをそのまま素早く描くことができる」点であると言う。水彩画家として出発したワイエスは、結局生涯水彩画家でありつづけた。そしてこの素材を完全に使いこなすすべを知っていた。その最たるものがドライブラッシュといわれる技法である。ワイエスは語る。「私は対象にたいして気持ちが深く浸透しているとき、ドライブラッシュを使う。小さめの筆を絵具に浸し、筆先を広げ大部分の水分と絵具を指を使って絞り出す。そうすると、本当にわずかな絵具だけが残る。ドライブラッシュは織物のような作業だ。水彩を幅広く薄塗りしてドライブラッシュの層を織り合わせていく」。これはドイツのアルブレヒト・デューラーの作品の研究からワイエスが学んだ技法で、テンペラほどは忍耐を要求されないが、普通の水彩とは別物であり、テンペラのように細部まではっきりと表現することができる。
しかしこのように技法を使いこなせるだけでは、真の大画家にはなれなかっただろう。きっかけは最も影響を受けた画家である父の死であった。一九四五年秋、アンドリューが28歳のとき、父と2歳の甥を乗せた自動車が踏み切りで立ち往生し、列車にはねられてしまうのである。それは衝撃的な訃報であった。そしてワイエスは「父の死をきっかけに、私は器用な水彩画家をやめ、人生を戯画化するのではなく正面から取り組むようになった」という。実際、絵の中に独特の哀愁や人間の運命といったものを表現するワイエス独自の世界が生まれるのはこのときからであった。それはまた、思うような芸術家になれなかった父を超えて、真の芸術家としてのアンドリュー・ワイエスの誕生であった。
そんなワイエスが大画家になるには、インスピレーションの源との出会いも重要であった。それがメーン州の海辺の小村で出会ったクリスティーナ・オルソンという女性だった。子供のころかかった病気のために体が不自由だった彼女は、内向的な弟と二人で暮らしていたが、ワイエスはこの二人をモデルに、そして彼らの住んでいた切妻屋根の家の内外を主題に、30年間に渡って描き続けるのである。一九四八年に描かれた《クリスティーナの世界》はその中でもよく知られた作品だが、本展にはそのテンペラ画制作のために描かれた素描や水彩画が出品されている。またオルソン家の部屋を舞台にした《幻影》というテンペラ作品とその水彩や鉛筆による数点の習作も出品される。オルソン家には長い間閉じられた部屋があり、ワイエスがドアを開けるとそこには男が立っていた―。実はこれは古びた鏡に映った自分自身の姿なのだが、水彩や鉛筆の素描には彼自身の驚きが大胆なタッチで表現されている。一方、テンペラには熟考の末に獲得された、幻想的な世界が描かれている。なお、展覧会にはこの他、画家が若い頃の非常に珍しい他の自画像も数点出品されており、ひとつの章を形成している。
素描や水彩には、完成されたテンペラに比べて、画家の激しい感情のほとばしりや、対象への関心のありようや意識の動きが直接反映されている。制作過程で生まれた作品の比較を通して、画家の関心の変化をたどることも可能であり、その変化に応じた描き方の多様さを知ることもできる。そしてそれは結局、ワイエスという画家の素晴らしさを改めて実感することでもある。「創造への道程」に触れるこの展覧会は、ワイエスの世界にまさにどっぷりと浸かることのできる、またとないチャンスなのである。