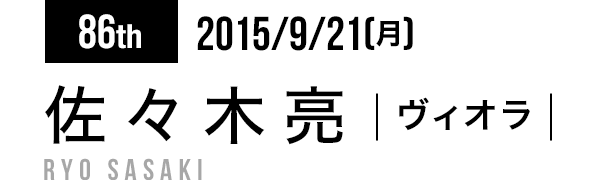今回の楽員インタビューは、2004年に入団、2008年からヴィオラの首席という重責を担う佐々木亮(ささき りょう)さん。音楽に一番大切なことは、フルトヴェングラーから学んだと言います。そのあたりのエピソードからお聞きしましょう。

フルトヴェングラーに影響を受けたそうですね。
「中学校一年生の時に、LPレコードのジャケットを見て『この人、面白そうだな』と思って買いました。初めて聴いたシンフォニー(ブラームスの1番)でしたが、第1楽章の20分間があっという間でした。『クラシック音楽とは、こういうものだったんだ』と最初に教えてもらいました。一つ一つの音符が、次の音を予感させるように音を紡いでいきます。 細かい音符が、常に全体を見て演奏されます。まるで、一つの物語を話すように。」
佐々木さんの音楽の「原点」と言えそうですね。
「はい。何度も何度も繰り返しレコードが擦り切れるほど聴きましたが、毎日違って聴こえて新しい発見があるんです。部分が全体を構築する。音のディレクション、方向性をはっきりさせる。この時得た体験は、今でも音楽に取り組む上で一番大切なものです。」
ヴァイオリンを一生懸命練習するようになったのも、あるレコードがきっかけとか。
「8歳からヴァイオリンを始めましたが、最初は練習が苦痛で。ところが、10歳の頃、たまたま家にあったレオニード・コーガンというヴァイオリニストの小品集を聴きました。この人の顔が、学校にあった怖い本、フランケンシュタインにそっくりで。面白いなあ、と思ったのが練習に励むようになったきっかけです。ここから、先ほどのフルトヴェングラーまで、突き進んでいくのです。」
ニューヨークのジュリアードに留学されます。
「ある音楽雑誌に、ドロシー・ディレイの弟子でクリスティアン・アルテンブルガーというヴァイオリニストのインタビューが載っていて、ヴァイオリンの技術が最も進んでいるのはアメリカだと。その頃、ちょっと技術的なことで悩んでいたのでアメリカに行って、ディレイ先生に教えていただいたメソッドのお蔭で、問題がクリアに整理されました。」
ヴィオラとの出会いは。
「ニューヨークで、川崎雅夫先生に、『ヴィオラの仕事があるので弾いてきて』と言われて、 慌てて楽器屋さんに行って、初めてヴィオラを手にしました。プレッセンダというイタリアの銘器です。一音弾いた瞬間、もうこれは一生弾いていく楽器だと確信しました。自分でも全く予期していない展開でした。」
オーケストラにおけるヴィオラとは。
「サンドウィッチの中味でしょうか。目立たないけど、なければ味わいがない。そんな具のような存在です。ヴァイオリンよりも(ヴィブラートを)ゆったりと、温かみがある音ですね。ヴァイオリンを下から支える面白さ、楽しさはうまくいくと快感でもあります。そんなヴィオラの理想の音を、自分一人一人で見つけ、確立することが必要です。」
冒頭、フルトヴェングラーの話題が出ましたが、同時代を生きるマエストロというと。
「ブロムシュテットさんですね。楽譜の読み方、書いてなくてもそこにある当たり前の真実を教えていただきました。もう、言われてみれば当たり前なんですが、気付いていなかった時期があります。一度教われば全てに応用できます。法則を理解すること。大事なことは、"一を聞いて十を知る"ということでしょう。」
9月のオーチャード定期が楽しみですね。
「ブロムシュテットさんは、ドイツものが得意ですから、きっと素晴らしい演奏になるでしょう。それに、マエストロは絶対に妥協しませんから。」
オーチャードホールについて。
「ピンカス・ズッカーマンのリサイタルを聴きました。こんなに上手い人がいるんだ。腰が抜けるくらい衝撃的でした。」
ありがとうございました。
※10月には、パーヴォ・ヤルヴィ首席指揮者就任記念、R.シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でチェロのトルルス・モルクとソロを努めます。佐々木さんのサンチョ・パンサ、今から大いに楽しみです。