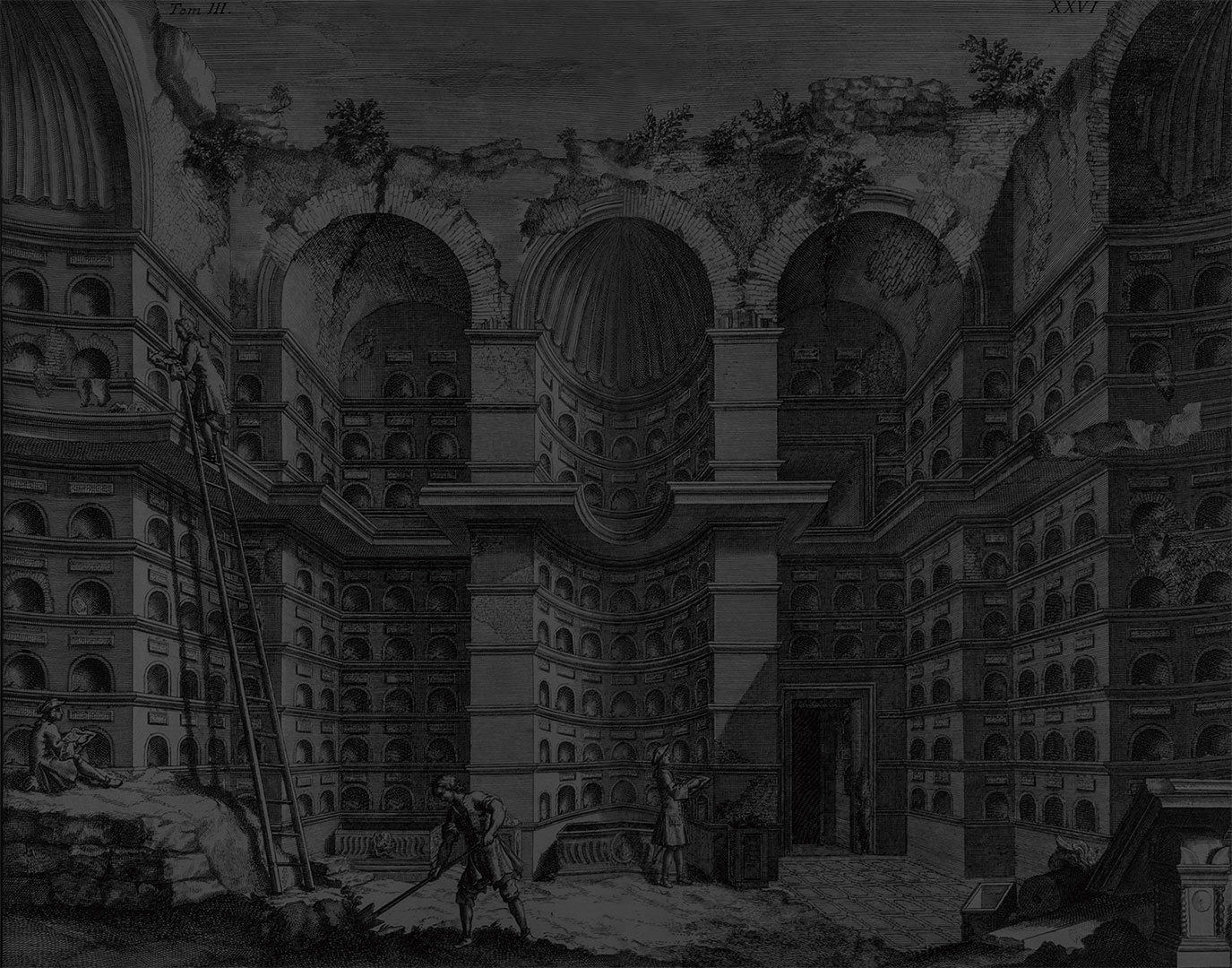TOPICSトピックス
2025.01.20 UP
【特別対談】「モーツァルトとオペラの宇宙」で手を組む~高砂熱学とBCJ~小島和人・高砂熱学社長と指揮者・鈴木優人、「ドン・ジョヴァンニ」を語り合う~

小島(以下K)弊社がオペラ公演を本格的に協賛するのは初めてです。1923年の創立から数えて101年目、第2世紀のスタートにこのような機会をいただき、光栄に思います。私たちはこれまでの100年間、空気調和設備の分野で、高層ビルや商業施設、工場、そして音楽ホールなど様々な建物用途における、お客様の建物価値、そして企業価値向上のために技術研鑽を重ねてまいりました。私たちの役割は黒子と申しますか、目に見えない空気の温度や湿度、気流や清浄度などをコントロールしている存在であるということもあり、これまで、文化やスポーツ協賛でメインスポンサーとなることは多くありませんでした。
鈴木(以下S)黒子という点では、オペラ上演におけるオーケストラも同じです。ピット(舞台手前の掘り込み)の暗闇にいて、舞台の引き立て役に徹します。
K 昨今では、社員の採用、働く社員のエンゲージメント向上などあらゆるシーンにおいてブランディングの必要性を痛感し、100周年を迎えた2023年10月から強化しています。CM制作や放映をはじめ、様々な取り組みをするなかで今回、Bunkamuraさんからのオペラ協賛のお話をお受けしたのです。私自身、2年前に《トスカ》、昨年《トゥーランドット》とオペラを立て続けに拝見しましたが、本当に楽しくて、すっかり魅了されました。私たちの社員にもこうした文化を体験してほしい、と願ったのが発端です。
S 小島社長は「あまり表に出ない」と謙遜されますが、高砂熱学の名前は過去にも色々な公演で目にしてきました。ご協賛をいただき、改めてどんなことをされている会社かと興味を覚えましたが、熱学という名前から想像する以上に幅広い業容なのですね。
K 2020年に当時の菅首相が「カーボンニュートラル」を宣言されて以降、建物のエネルギーの約50%と多くを占める空調エネルギーをどう下げるかといった「建物環境のカーボントランジション」だけでなく、培ってきた知見や技術をもとに「地球環境のカーボンニュートラル」に我々も貢献していく必要があると感じました。省エネだけでなく、皆さんよくご存知の太陽光、バイオマスなどの再生可能なエネルギーや水素などの次世代エネルギーの利活用を通じ、地球環境が抱える課題を解決していくことが私たちの使命だと思っています。
S 熱学という言葉を比喩的に捉えると音楽も心に熱を帯び、伝播していくものです。歌手の声が生み出す個の力の一方、指揮者はオーケストラの熱を高めたり、高まり過ぎたらちょっと調整したり、さらにその調和を作っていく立場なのかもしれません。私はこうした音楽、あるいは空気のコラボレーションにワクワクします。
K 私は残念ながらうかがえなかったのですが、バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)とBunkamuraのモーツァルトシリーズ第1作、《魔笛》(2024年2月・めぐろパーシモンホール)を観に行った知人がおりまして「音楽だけでなく舞台があったり、衣装があったり、美術があったり…ともう、様々なことが楽しかったよ」と言っておりました。それも今回、第2作《ドン・ジョヴァンニ》の協賛につながったきっかけの一つです。

S そうでしたか!指揮者には、本当に物理的な熱を帯びる場合がありまして、オーケストラのメンバーは「空調が寒い」と言っているのに「僕はとても暑いのだ」と。やはり音楽に燃えていると、ついつい熱を帯びてしまいます。歌手も終わったらもう、汗だくですからね。本当に体温も上がっていて、舞台に立つ側は全てのエネルギーを投じて打ち込み、演奏します。その熱が小島社長のお知り合いにも伝わっていた、と聞くだけですごく嬉しいです。
K あともう1点。オペラは大勢、様々なセクションの方々がいらっしゃって、それを指揮者がまとめられていますが、建設業においても建物の躯体を作る建築会社や、電気設備、水廻りの衛生設備、そして私たち空調設備分野など様々な業種・企業が一堂に集結して1つのビルを造ります。「チームビルディング」と言いましょうか、オペラを観た知人も何か相通じるところがあって、感動が倍加したのではないかと推測しています。
S 組織マネジメントという観点からも、オペラは面白いのではないでしょうか?音楽家の側をまとめるのは指揮者ですが、舞台監督という別の黒子が存在します。この方は安全面、例えば地震発生時に上演を止めるか否かとか、舞台セリの動きとか、物理的に人命とかかわる状況にまで目を光らせるチーフです。さらに演出家という演技や視覚の部分を担う専門家もいらして、パワーバランスはプロダクションによっても変わります。今回の《ドン・ジョヴァンニ》は杉本博司さんが美術家として加わり、大きくスポットライトが当たるでしょう。まさにチームビルディングであり、非常に独特な21世紀型のオペラプロジェクトだと思います。
K 私たちは、創立100周年を機に社員から色々な想いやワードを募集し、パーパス「環境革新で、地球の未来をきりひらく。」、ビジョン「環境クリエイターⓇ」を打ち出しました。建物環境の枠を超え、地球の未来を担う環境クリエイターⓇとして、高砂熱学は文化や芸術の一端も体現できるのだという発信のスタートが、《ドン・ジョヴァンニ》です。もちろん、「私たちはこのように素晴らしい芸術の現場の空調を提供できるのだ」という自負もあります。私自身、1990年代に開館した都内のあるホール空調をエンジニアとして手がけた際、室内環境を整える過程で内外の演奏家と接する機会をいただき、技術系の方とは異なる感性に触れました。
S 結構(繊細な空気環境は楽器にとって)大事なのですよ。私たちBCJは作曲当時(ピリオド)の楽器、あるいはそれに近いレプリカ(複製品)を使って演奏します。例えば弦楽器の弦はスチールではなく、ガットといって羊など動物の内臓を乾燥させたものを使うので、筐体の木材ともども、ちょっとした湿度の変化を受けやすいのです。空調に関してかなり敏感な奏者も多いのですが、日本にはかなり快適なホールが多く、助かっています。
K 環境クリエイターとして建物環境以外にも貢献しようとする上で、参考になる話です。社員が《ドン・ジョヴァンニ》に接して得るものも大きいのではないかと期待します。
S 主人公は放蕩の限りを尽くした最後に地獄へ堕ちます。「道楽をするな」と社長さんが言葉で訓示するのとは違って、非常にユーモラスで受け入れやすいものとして心に入ってくるのが音楽の機能で、より強く、実行力を伴う形で届くのではないかと思います。

K (オペラといったものについて)私はちょっと、勘違いをしていました。クラシック音楽は過去の作品の再演と考えていたのですが、実際には再発見と再創造(リクリエイト)の連続なのですね。
弊社は創立当初から「ないものは自分たちで創る」というマインドがあったんですが、近年「ないものはみんなで創ろう」というマインドに変えたんです。
S 古い楽器や楽譜を使っていても、演奏する環境は日本においても、どんどん変わっていきます。30年前とは一変した環境の中で、いかにして自分たちの音楽を再発見しながら創造していくかが私たちの本当の課題です。こうして様々な業種の皆さんとお話をさせていただくたび、ヒントをいただける感じはあります。
K 弊社社員にも、《ドン・ジョヴァンニ》の鑑賞通じてアートから何かヒントを得てもらえればと思っています。NEXT(次代)の空調技術や環境革新技術を考えるきっかけにもなるのではないかと期待しています。
S オペラの「アリア」の語源はエア、空気ですから、ご縁は元からありましたね!
s.jpg)
(2024年11月25日、東京・東新宿の高砂熱学工業(株)本社で)
コーディネート&編集執筆=池田卓夫=音楽ジャーナリスト@いけたく本舗®︎
Photo by Yoshitsugu Enomoto
特別対談のダイジェスト動画はこちら
(Bunkamura公式YouTubeチャンネルへリンクします)