 |
|
|
 |
 |
 |
 |
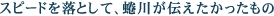 |
 |
熱とスピードで駆け抜けるのが、蜷川幸雄の得意技だ。人を愛する喜びも、誰かを憎む気持ちも妬みの心も、火柱のように強く立ち上げ、あっという間に観ている側に飛び火させる。観客は自分も業火の一部になった快感に酔いながら、一緒に物語を疾走する。
この『あわれ彼女は娼婦』でも、きっとその得意技が披露されると思っていた。なぜなら『あわれ──』は、近親相姦に陥った兄と妹を中心にした物語であり、いびつながら激しいその愛は、蜷川の“炎の演出”にぴったりだと考えたからだ。だが幕が下り、客席を立つ時に胸を満たしていたのは、すべてを焼き尽くしたカタルシスというより、焼け跡の静寂に感じる切なさだった。 |
 |
 |
 |
 |
その理由はおそらく、近親相姦の主役である兄ジョヴァンニ(三上博史)と妹アナベラ(深津絵里)を、自分達で率先して“常識の外側”に行こうとするアナーキーな恋人達ではなく、周囲に追い詰められて“常識の外側”に出ていくことを余儀なくされた、イノセントなふたりとして描いた点にある。
周囲の人間は、連鎖的にふたりを追い詰めていく。兄妹の父親(中丸新将)は、愛情にくるんだ金銭欲で、娘を裕福な貴族ソランゾ(谷原章介)と結婚させる。ソランゾは「これ」と思った女性を手に入れるまでがすべてであり、その女性と“生活”することができず、アナベラを持て余す(たとえアナベラがジョヴァンニの子供を妊娠していなくても、妻という存在が疎ましくなり、ソランゾは不倫か家庭内暴力に走ったのではないか)。 |
唯ひとり、ジョヴァンニとアナベラに苦しみを打ち明けられた善良な修道士(瑳川哲朗)も、「近親相姦は地獄に堕ちる」などの宗教語でしか彼らと会話できない。では宗教が助けになるかといえば、身分の高い聖職者である枢機卿(妹尾正文)は、身内の不祥事は殺人すら平気でもみ消す腐り方だ。兄妹が信じられる人、尊敬できるもの、安らげる場所は、次々と失われ、だからふたりはますます孤立し、お互いに相手しかいなくなる。
孤立が深まり、すべての出口を失った時、ジョヴァンニはアナベラに、また、ソランゾや彼の誕生日パーティに集まった権力者達に対して、行動を起こす。気迫にあふれたその姿は、まさに炎を背負った阿修羅なのだが、そこから先の手触りがいつもの蜷川作品と違う。自分に深手を負わせたソランゾの召し使いヴァスケス(石田太郎)に、ジョヴァンニが感謝の言葉を告げる、淡々とした様子の悲しさ。彼の休息はそこでしか得られなかったものなのだ。また、損得や世間体や虚栄心ではなく、純粋に人を愛したバーゲット(高橋洋)が幸せを目前に死んでいくシーンの存在も大きい。この作品で蜷川は、敗れた人間の息遣いを丁寧に、スピードを落とした舞台の上に定着させた。演出のテクニックとしての緩急とは違う、優しさと悲しさが入り混じったその視線が、これまで知らなかった蜷川の一面を感じさせた。
それができたのは、真の孤独の表現を託せた三上、何があっても傷つかない強さと汚れない気品を持つ深津、初めてプライドを傷つけられた男の地獄を全身で演じた谷原らの存在によることは言うまでもない。そして、戯曲上の一貫性のなさを、大人のずるさや気まぐれのようにぬるりと演じてほころびに見せなかった石田、梅沢昌代の奮闘も忘れがたい。
Texts:徳永京子(演劇ライター)
Photos:谷古宇正彦 |
|
|
| |
| |
 |
|
|
 |
 |
|