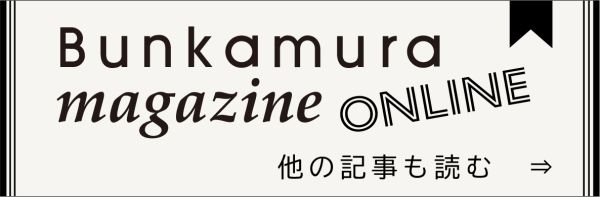小林海都(ピアニスト)
“文化の継承者”として次世代を担う気鋭のアーティストたちが登場し、それぞれの文化芸術にかける情熱や未来について語る「Bunka Baton」。今回は、若手ピアニストの登竜門として知られるリーズ国際ピアノコンクールで46年ぶりに日本人歴代最高位の第2位に輝き、一躍脚光を浴びた小林海都さんにインタビュー。繊細かつ精度の高さに定評のある小林さんのピアノ演奏を形作った留学体験や、演奏で大切にしている楽曲との向き合い方などを語っていただきました。
ベルギーへのピアノ留学で学んだ
音楽を通した聴衆とのコミュニケーション
小林さんにとっての音楽のルーツは1歳ごろのこと。お姉さんが習っていた合唱団に混ざり、ほかの人と一緒に歌ってアンサンブルをすることに親しんでいきました。そして4歳ごろ、お姉さんが新たに習い始めたピアノ教室に自分も通うようになったといいます。
「姉と同じことをやりたいという気持ちで始めたんだと思います。習い始めの頃、姉が弾いていたブルグミュラーの『アラベスク』を聴いて自分も弾きたくなり、レッスンで習う前に最初の数小節をひたすら弾いていた記憶が残っています。その後も、課題曲が難しくなればなるほどやりがいを感じ、いろんな曲を演奏していくいくことを楽しんでいました」
小林さんが幼い頃に憧れたピアニストはピョートル・アンデルシェフスキ氏。中学生の時にリサイタルで演奏を聴き、繊細な弱音によって作られる世界観に感銘を受けたそうです。当時の感動を「音によって人の意識を惹きつけるアンデルシェフスキ氏の演奏への憧れは、現在の自分の演奏へのこだわりにもつながっています。彼の演奏は今でも好きです」と振り返ってくれました。
ピアノが上達するごとにさらなる高みを目指していった小林さんは、クラシック音楽のルーツであるヨーロッパで学ぶ必要性を感じつつ、留学先を決めかねていました。そんな中、高校2年生の時に世界的な名手マリア・ジョアン・ピリス氏と出会い、彼女が在籍するベルギーのエリザベート王妃音楽院へ高校卒業後に留学しました。
「ピリス先生からは大切なことをたくさん教わりました。たとえば、演奏会の舞台上で演奏を聴かせていただいたり一緒に連弾しながら、ライブ空間でしか感じられない音楽作りを学ばせていただきました。ただ自分の世界だけに入って演奏するのではなく、聴衆の方にも意識を向け、音楽を通したコミュニケーションを意識するようになったんです。コロナ禍の間に無観客の会場で演奏する機会がありましたが、聴衆がいる緊張感の中で紡がれていく“一期一会の音楽”が存在することを改めて実感しました」
ピリス氏のほかにも多くのピアニストに師事する中で、小林さんの演奏の土台として大きな糧になった教え。それは、楽曲との向き合い方でした。
「どの先生もアプローチは異なるものの共通した部分として、曲の良さを十分に引き出すためには、作品と誠実に向き合う姿勢が大切であることを教わりました。自分よりも作品が引き立つこと第一に考え、演奏することを今も心がけています」
自分の個性や技術力をアピールするのではなく、あくまでも楽曲の魅力を伝えることに徹する──。そうした誠実さが小林さんの演奏家としての個性と言えるでしょう。

ヨーロッパへの留学で得られた貴重な経験として小林さんが挙げたのは“教会の響き”。「教会で演奏されるオーケストラの響きが、まるで天に昇っていくような余韻が感じられ、コンサートホールとは全然印象が違うものでした。教会の響きというイメージがあることによって、特にバロック音楽や古典派の作品に取り組む上で大きなインスピレーションとなっています。」
自然体で臨んだリーズ国際ピアノコンクール
普段の演奏での心がけは「素材の良さを生かすこと」
小林さんはピアノの研鑽を重ねる一方、演奏家としてのキャリアを確固たるものとするため国際コンクールにも積極的に挑戦。そして2021年にリーズ国際ピアノコンクールで46年ぶりに日本人歴代最高位の第2位に輝くという偉業を達成しました。さぞかし特別な意気込みと準備とともに臨んだのかと思いきや、実はその逆だったそうです。
「偉大なコンクールということを十分理解していたので、入賞しようという欲は正直ありませんでした。2次予選から現地で演奏したのですが、演奏できるだけでも十分ありがたい機会だと思い、これまで勉強したことを出せることを一番に考えていつも通りに臨みました」
このように大舞台で気負わず伸び伸びと演奏することによって得た栄誉は、小林さんにとって大きなプラスの変化をもたらしました。
「コンクールを通じて多くの方々とのつながりが生まれ、演奏会の機会をより多くいただけるようになりました。また、それまで演奏会の前はレッスンで先生に演奏を見てもらっていたのですが、演奏会が多くなると毎回見てもらうわけにもいかず、自分の力で一から曲を作り上げていくことが増えました。先生に頼らず自らの決断で音楽作りをしていく、いい機会になったと思います」
そんな小林さんに普段の演奏で心がけていることを尋ねたところ、前述の「楽曲への誠実な向き合い方」にも通じる姿勢を挙げてくれました。
「お客様には作品の良さを純粋に感じ取っていただきたいと思っています。僕は食べることが好きで、シェフの姿勢として『素材にこだわり、その素材を生かす調理』に惹かれます。音楽で言うと作品が素材にあたるわけですが、調理の仕方を間違えてしまうとその良さが出ないと思うんです。たとえばテンポ一つ取っても『曲の魅力が出ているかどうか』を優先し、曲をしっかり生かすことをいつも考えながらアプローチしています。その判断が僕の主観になってしまうのは避けられないのですが、ああしようこうしようと余分な物を足さないよう心がけています」
小林さんのレパートリーはバロック、古典、ロマン派、近代と幅広く、近年はソロだけでなく室内楽にも積極的に取り組んでいます。これから意欲的に取り組みたいジャンルを尋ねたところ、「贅沢な話かもしれませんが、すべて満遍なくやっていきたい」と答えてくれました。
「室内楽は共演者と一緒に音楽を作り上げていく喜びを感じられるし、近年演奏の機会を多くいただくようになったコンチェルトも、オーケストラとしかできない音楽作りを楽しんでいます。一方、ソロは一人で音楽をすべて成立させないといけないプレッシャーはありますが、自分自身を見つめ、一人で演奏するからこそ出てくる音楽というものもあると思っています」
小林さんの「すべて満遍なくやっていきたい」という意欲は、各ジャンルの醍醐味を味わうだけでなく、演奏家としての表現の幅の広がりも目指したものです。
「室内楽での音のバランスなどにおける共演者との関係性は、オーケストラでも通用するかというと必ずしもそうではありません。逆に、室内楽で得たアンサンブルの感覚は、ソロの演奏において両手で別々の役割を果たす時に生きることがあります。つまり、すべて満遍なくやることは、自分の演奏のバランス感覚を培うために欠かせないものだと思っています」

これまでの演奏会でターニングポイントになった印象深いものとして、2016年のエフゲニー・ボジャノフ氏との共演を挙げてくれました。「彼の音楽づくりは本当に自由で、リハーサルでも本番でも通しで演奏するたびに全然違う弾き方をするんです。それまでの僕はつい安全な方向に行きがちな面がありましたが、彼との共演によってそうした固定概念が大きく変わりました」
モーツァルトのピアノ・コンチェルトは
“隠れた遊び心”が聴きどころ
小林さんに今後演奏していきたい作曲家を尋ねたところ、かつて師事したピリス氏が得意とするシューベルトを挙げてくれました。
「シューベルトの楽曲は流れに身を任せるような自然体が大きな特長で、その魅力は演奏の中から自然と湧き上がり伝わってくるものです。シューベルトのピアノ・ソナタはたくさんあるので、今後新しくレパートリーに加えていきたいですね。またコンチェルトでは、モーツァルトのレパートリーを広げていきたいと考えています」
11月2日開催のN響オーチャード定期第134回では、モーツァルトのピアノ・コンチェルトの中でも特に人気が高いピアノ協奏曲第21番を演奏する小林さん。その聴きどころとして興味深いポイントを教えてくれました。
「モーツァルトのピアノ協奏曲第21番といえば特に第2楽章の美しさが有名ですが、実はモーツァルトならではの遊び心が随所に仕掛けられています。たとえば、第1楽章の第2主題の直前に普通では考えられないような転調の挿入句が入っていたり、第1楽章の序奏もきれいにフレーズをまとめるのではなく、しつこく畳みかけるような部分が目立ちます。そうした仕掛けを通じて表現されるドラマティックさに聴衆が驚き、さらにその驚く姿をモーツァルトが見て楽しんでいるような、遊び心みたいなものも演奏で出せるといいなと思っています。また、ピアニストとして憧れのある作品なので、今回演奏できることを楽しみにしています」
これからの目標として「室内楽が好きで今後もいろいろな方と一緒に演奏していきたいのですが、欲を言えば室内楽とソロの作品を織り交ぜた演奏会を開きたいですね」と目を輝かせながら語ってくれた小林さん。彼が作り出す音楽の世界が、今後ますます広がっていくことを期待しましょう!

N響オーチャード定期第134回で指揮を務めるマエストロ・広上淳一氏とは今回が3度目の共演。2019年の仙台国際音楽コンクールでベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番を演奏したのが最初の共演で「マエストロとの素晴らしい演奏に感動したのを今でも覚えています」と振り返ってくれました。
取材・文:上村真徹

〈プロフィール〉
1995年生まれ。幼少より合唱と声楽を学び、4歳からピアノを演奏。ヤマハマスタークラス特別コースに在籍。上野学園高等学校音楽科演奏家コース(特待生)卒業。2014年から16年までエリザベート王妃音楽院に在籍してマリア・ジョアン・ピリスに師事し、2016年からバーゼル音楽院に在学しクラウディオ・マルティネス・メーナーに師事。2021年にリーズ国際ピアノコンクールで第2位&ヤルタ・メニューイン賞(最優秀室内楽演奏賞)に輝き、2024年には浜松国際ピアノコンクールで第3位入賞。NHK交響楽団、ベルギー国立管弦楽団、バーゼル交響楽団、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団など国内外の多数のオーケストラと共演している。
X @kaito5884
YouTube
Instagram @quaitaux5884
Facebook
公式HP

〈公演情報〉
N響オーチャード定期2025/2026
東横シリーズ 渋谷⇔横浜
<魅惑の映画音楽>
第134回
2025/11/2(日)15:30開演
Bunkamuraオーチャードホール