|
一柳:
私がニューヨークに最初に行ったのは1954年から61年の7年間なんです。私にとってはこの時期が一番面白かったですね。50年代のニューヨーク、アメリカというのは芸術が一番発展している、黄金期だったと言われていますけども、その時期に居合わせることが出来て本当に刺激を受けましたね。芸術というとそれまではもちろんヨーロッパが中心で、アメリカは後進国だったわけですけども、それが戦後になって、むしろアメリカが主導になるぐらい立場が逆転した時期なんですね。ですからアメリカから発信する新しい芸術が一番エキサイトした時期でしたね。
ジョン・ケージと出会ったのが1957年ですけども、この時にケージの演奏会が行われたのは、ダウンタウンのグリニッチ・ビレッジの中にあるビレッジゲイトという、普段はジャズが行われている場所なんですね。決して場末のマイナーな所ではなくて、そういうところで新しい音楽、催しが行われていたんです。それで、すぐ翌日の新聞にそのケージのコンサートが非常にインパクトのあるものとして大きく取り上げられたりしてね。そういう状況があったんですね。普通に考えるとコンサートというとコンサートホールとかオペラ劇場とか、そういう場所になると思うんですが、そういう風にいろんな人が自分が本当にやりたいと思う場所で自分の活動をやっていたということも当時のニューヨークの面白いところでしたよね。
 横尾: 僕がニューヨークに来てとにかく驚いたのは、グリニッチ・ビレッジで目撃した、今でいうヒッピーですね。その様子を初めて肌で感じたことが衝撃的でしたね。ちょうどその頃ニューヨークはサイケデリック・ムーブメントの真っ只中で、何かがものすごく大きく変わろうとしている時だったんです。みんなマリファナやLSDをやっていて、聴覚・視覚・触覚、五感が開放されてすごく鋭敏になるっていうんですよ。そういうドラッグによって作られた音楽やビジュアルがサイケデリック・ロックであり、サイケデリック・アートである、というようなことを教わるわけです。当時ニューヨークにはいろんなところにディスコがあって、アンディ・ウォーホルが関わったベルベット・アンダーグラウンドなんかがライブをやっていたわけです。そこでは今まで見たことも聞いたこともないような、音や映像が流れていて、みんな狂ったみたいに踊ってるわけです。そういう所へ一人で行って、いっぺんにハマってしまったんですね。それから毎日、毎晩行くようになった。それと同時に一方では一柳さんとほとんど毎日のように会って、日本に帰ったらああしようこうしようとか、いろいろ芸術論から文化論から話しましたね。確か1ドル何セントかの安いステーキを一緒に食べた記憶があるんですが、それ覚えてますかね? 横尾: 僕がニューヨークに来てとにかく驚いたのは、グリニッチ・ビレッジで目撃した、今でいうヒッピーですね。その様子を初めて肌で感じたことが衝撃的でしたね。ちょうどその頃ニューヨークはサイケデリック・ムーブメントの真っ只中で、何かがものすごく大きく変わろうとしている時だったんです。みんなマリファナやLSDをやっていて、聴覚・視覚・触覚、五感が開放されてすごく鋭敏になるっていうんですよ。そういうドラッグによって作られた音楽やビジュアルがサイケデリック・ロックであり、サイケデリック・アートである、というようなことを教わるわけです。当時ニューヨークにはいろんなところにディスコがあって、アンディ・ウォーホルが関わったベルベット・アンダーグラウンドなんかがライブをやっていたわけです。そこでは今まで見たことも聞いたこともないような、音や映像が流れていて、みんな狂ったみたいに踊ってるわけです。そういう所へ一人で行って、いっぺんにハマってしまったんですね。それから毎日、毎晩行くようになった。それと同時に一方では一柳さんとほとんど毎日のように会って、日本に帰ったらああしようこうしようとか、いろいろ芸術論から文化論から話しましたね。確か1ドル何セントかの安いステーキを一緒に食べた記憶があるんですが、それ覚えてますかね?
一柳: 私が覚えてるのはね、二人ともお酒を飲まないもんですから、毎晩のようにアイスクリームを食べたことですね(笑)。
横尾: そうでしたね。アイスクリーム食べてました(笑)。そういう毎日が本当に魅力的で、ここで自分を変えないともうこれは変えるチャンスがないという気がして、20日の予定だったのが気が付いたら4ヶ月そこにいたんです(笑)。幸い展覧会でポスターがよく売れたんで、日本から送って、また展覧会やって、それで食いつないでいましたね。
一柳: ディスコに行って毎晩のように踊られてるというので、私もそれにかなり影響を受けて、あやうくこちらの道を踏み外す寸前までいったんですよね(笑)。しかし、当時のサイケデリックな環境というのはそのぐらい魅力的だったわけです。例えば私が親しくしていたサム・フランシスという画家がいるんですけど、彼がフランク・ザッパというミュージシャンがサイケデリック・ディスコでやるライト・ショウですね、つまり音だけじゃなくてロックのリズムに合わせて照明も動くっていう、その担当になったりして。いわゆるアーティスト達もそういうロックの世界に影響受けた時期でしたね。
あの頃が楽しかったのは、例えば職業とか身分とか貧富の差とか、そういうものが全く関係なくて、ある意味で個人の尊厳みたいなものがきちんと根底にあって、自分がやりたいと思うことをそれぞれの人が徹底してやっていて、そのことに対して誰も干渉しないという、そういう自由さがあったところですね。そういうところがあの時代のニューヨークの一番の魅力だったと思いますね。
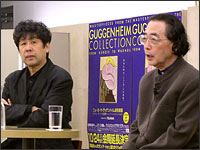 横尾: その頃の例えば、現代音楽や現代美術、映画ではヌーヴェル・ヴァーグ、文学ではヌーヴォー・ロマン、そういうものがバラバラに存在してるんじゃなくて、何か無意識の領域で全部繋がっていたような気もしますね。ただ僕がやっているグラフィックの世界だけが何かモダニズムでですね、面白くなかったんですよね。だから僕はグラフィックから逆行した方向を向いてたと思います。僕が興味あるのはやはり新しい芸術の動向といいますかね、そういうものですね。だからまずニューヨークに行って一番会いたかったのがアンディ・ウォーホルだったんですよね。当時アンディ・ウォーホルがアトリエにしていた有名な“ファクトリー”というところへ行ったんですが、中に入るとなぜか天井とか壁に銀紙がいっぱいはっつけてあって、鉄のエレベーターのドアが開くとそこがすぐスタジオという感じで、薄暗くて、若い男の子がその辺でたむろしているんです。で、そんな暗いところでアンディ・ウォーホルがかなり黒っぽいサングラスをかけてシルクスクリーンを刷っているんですね。こんな暗いところでサングラスかけて色なんかわかるのかなあ、と思ったんですが、もしかしたら彼はすべてサングラスを通して世界の色を見ていて、そこで彼がチョイスした色を我々はサングラス抜きで見ていたのかな、という気が未だにしますね。 横尾: その頃の例えば、現代音楽や現代美術、映画ではヌーヴェル・ヴァーグ、文学ではヌーヴォー・ロマン、そういうものがバラバラに存在してるんじゃなくて、何か無意識の領域で全部繋がっていたような気もしますね。ただ僕がやっているグラフィックの世界だけが何かモダニズムでですね、面白くなかったんですよね。だから僕はグラフィックから逆行した方向を向いてたと思います。僕が興味あるのはやはり新しい芸術の動向といいますかね、そういうものですね。だからまずニューヨークに行って一番会いたかったのがアンディ・ウォーホルだったんですよね。当時アンディ・ウォーホルがアトリエにしていた有名な“ファクトリー”というところへ行ったんですが、中に入るとなぜか天井とか壁に銀紙がいっぱいはっつけてあって、鉄のエレベーターのドアが開くとそこがすぐスタジオという感じで、薄暗くて、若い男の子がその辺でたむろしているんです。で、そんな暗いところでアンディ・ウォーホルがかなり黒っぽいサングラスをかけてシルクスクリーンを刷っているんですね。こんな暗いところでサングラスかけて色なんかわかるのかなあ、と思ったんですが、もしかしたら彼はすべてサングラスを通して世界の色を見ていて、そこで彼がチョイスした色を我々はサングラス抜きで見ていたのかな、という気が未だにしますね。
その時のエピソードでひとつ面白いのがあるんです。アンディ・ウォーホルが細長い大きな作品を作ろうとしていた時に、アシスタントがそのキャンバスを引きずりながら持ってきて、ウォーホルのチェックを受けていたんですね。その時にその若いアシスタントが、「ウォーホル、あなたはこうしろと言うけど、僕はそうではなくてこういう風にした方がいいと思う」、という感じでウォーホルに自分の考えを述べているんですよ。その時にウォーホルはどうするのかな、と思ったら、彼はどこかをボーっと見ながら、「ああそう、君がそう言うならそうしたらいいじゃない」、見たいな感じで言うんですね。なるほど、ウォーホルというのはこういう人か、と。人の能力、才能というものをこういう形で活用して利用して、それで作品を作るんだなと。こうせねばならないという、自我が非常に希薄な人だと、そこは非常に東洋的だと思って、僕はそれをものすごく感動したことあるんです。
でも数年後にあらためてウォーホルを訪ねたらファクトリーの場所も中身も全部違っていて、何か大きな企業を訪ねているみたいでした。入り口にちゃんとした受付嬢がいてね。で、しばらく待たされて中に入るとウォーホルがテーブルの上に腰掛けて足組んでるんですよ。白いシャツにジーンズを履いて、新聞を片手に電話を掛けながらコーヒーを飲んで。これってまるでアメリカのビジネスマンにそっくりのスタイルですよね。その時は、ここ数年でウォーホルも随分変わってしまったな、という感じを受けました。
|