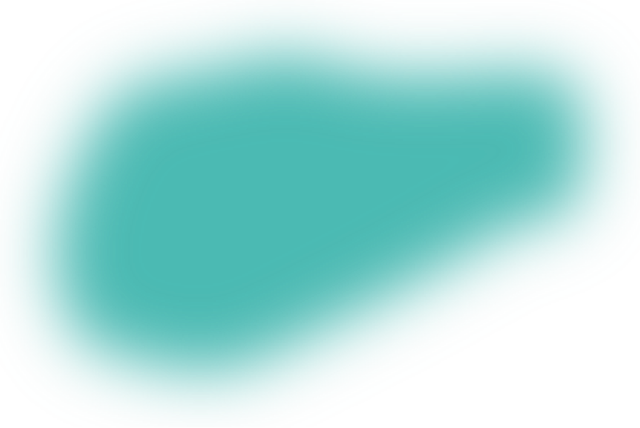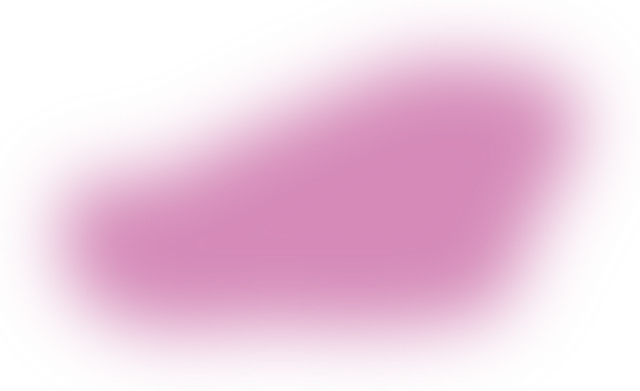TOPICSトピックス
2024.09.13 UP
『A Number─数』『What If If Only─もしも もしせめて』開幕レポート&舞台写真を公開
キラキラと乱反射する鏡の世界を覗いてみたら、「人間」の姿がそこにはあった。
取り返しようのない過去の時間を取り戻そうともがく孤独な男たちは、過去の自分を悔い、でもそれ以外にやりようがなかったのだと時に自分を正当化したかと思うと、いややっぱり悪いのは自分だったのかとまた自問し、ループしながら過去の時間をさまよっている。「いま」という現実になかなか向き合えない彼らの身に起きることを、私たちは覗き見する。その先の「未来」がどうなるのか、スリリングで一瞬たりとも目が離せない。

コンパクトにして贅沢な二本立てだ。
休憩を含めても上演時間は二本で約2時間。一本目の『What If If Only─もしも もしせめて』に至っては20分強という超短篇だが、二本目の『A Number─数』ともども、作品の短さと観劇の充足感は比例しない。それぞれ削ぎ落とされた中に凝縮された旨味の濃度が高く、まさに“一粒で二度美味しい”状態なのである。
イギリス現代演劇を代表する劇作家キャリル・チャーチルの、別々の時期に書かれた二つの作品(つまり本来は無関係な作品同士)に共通項を見出した演出家ジョナサン・マンビィが、チャーチル本人に直談判して実現したという今回の二本立て。「併せて上演したら面白いのではないか」という演出家の嗅覚は、掛け合わせの妙を堪能できる相乗効果をもたらした。

両作品に共通する「世界」は、いくつもの鏡のキューブが吊り下がる空間だ(美術・衣裳:ポール・ウィルス)。広大な宇宙に浮かぶ無数の惑星のように、その一つ一つのキューブの中では、時も場所もそれぞれ全く違う、けれどもどこかで繋がっている「人間」たちの営みが行われている。
『What If If Only─もしも もしせめて』に登場するのは、大切なパートナーを亡くした某氏(大東駿介)。「君」がいつも座っていた椅子に向かって、「せめて一目でも会いたい」と切々と訴える。と、湿っぽい観念劇になるかと思いきや、マジカルな展開が待っていて、「君」とは似ても似つかない(でもどことなく似ているかもしれない??)「未来」の亡霊なるものが現れるのだ。この「未来」と、のちに登場する「現在」の亡霊を演じる浅野和之が、場の空気を文字通り一変させる。ヘンテコだけどすこぶるキュートで押しが強く、某氏の逡巡を見透かし、「起きなかった未来」を「起こりうる未来」にすべきだと迫る「未来」、「いま」こそが全てだと現実を見据えさせる、クールでダンディな「現在」。こんな素敵な亡霊たちが現れたら個人的にはぜひとも仲良くなりたいものだが(お盆に先祖の霊を普通に迎える日本人にとっては亡霊もそれほど恐れるべき存在ではないように思う)、愛する人を強く想い、過去を悔いる某氏が混乱し、恐怖を覚えるのも無理はない。「起きたことにしてほしい未来たち」が大挙押し寄せる場面では、視覚・聴覚ともに幻惑される仕掛けが待っていた。やがて起きようとする「幼き未来」が、かすかな希望の光“のようなもの”を感じさせて幕となる。大東の真摯さ、浅野の変幻自在さが際立つ珠玉の小品となった。



休憩後の『A Number─数』では、キューブの中にクローン人間が存在する近未来の空間が現れる。と言ってもSF感は全くなく、あくまでリアルな台詞劇として展開していく。登場するのは、父親(堤真一)と息子(瀬戸康史)。ただし息子の方は、“本物”のほか、彼から作られたクローンが二人。つまり、一人の父親と三人の息子(顔は同じだけど全く別人)の物語だ。なぜそんなことになったのか。三組の“親子”の会話から徐々に事の次第が明らかになっていく巧みな構成に惹きつけられつつ、こんな事態を引き起こした肝心の父親の言うことが曖昧で、真実がどこにあるのかなかなかわからない。思い通りに育たなかった息子の代わりにクローンを作って出直そうという発想は、あまりに短絡的で身勝手じゃないか?というもどかしさと違和感を抱えたまま物語は進んでいくのだが、会話の中から思わぬ事実が浮かぶことの連続で、神経を集中させて二人の対話に聴き入ることになる。父親なりに過去を悔い、「過去をやり直したい」と考える気持ちは尊いが、その間違ったベクトルに翻弄される子供の胸中には思いを馳せることができなかったのだろう。
そんな父親を堤が演じることで、子供の内面には無関心で自己中心的な親というよりも、悪い人間ではないが罪の大きさを自覚できない自己認識の甘さが招いた不幸、という側面が強く感じられる。それまでの人生を突然根底から覆され、自分が何者かがわからなくなった“新しい息子”の混乱、父から捨てられた“本来の息子”の絶望と怒り、そんな彼らを尻目に、自分の出生に全くこだわりなく充実した人生を謳歌する“第三の息子”(彼と父親とのやり取りが噛み合わなさすぎていちいち可笑しい)。三人三様の息子の佇まいを自然に演じ分ける瀬戸のシリアスさと軽やかさの匙加減で、親子のパワーバランスが鮮やかに変化していくのがスリリングだ。
息子のクローンは二人だけではなく、実はかなりの「数」がいて──という厳然たる事実にこれから父親がどう対峙していくのか。過去を省みることも必要だが、「現在」から目を逸らさず「未来」を見据えることが、人間として生きることの意味ではないのか。ようやくそのことに気づいた父親の背中を、私たちは「ある光景」と共に見つめることになる。
いま生きている自分は、過去の選択の積み重ねの上にある。その過去を変えることはできないけれど、現在を真摯に生きる先に、未来へ続く道はある。キューブの中で繰り広げられる二本の作品は互いに響き合いながら、私たちの心の奥深くを揺さぶるのだ。




文:市川安紀
撮影:細野晋司