No 32石に秘められた芸術と愛の真理
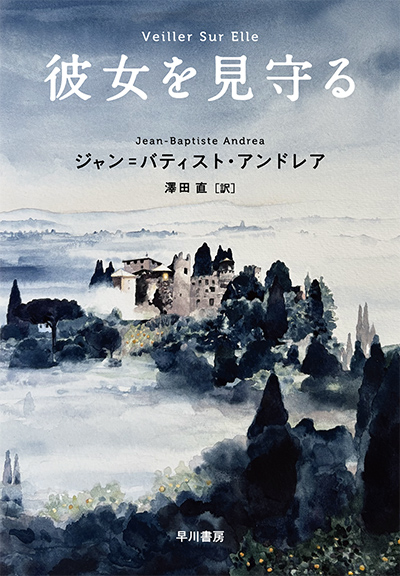
20世紀前半激動のイタリアを生きた若者たちと歴史絵巻
この作品を取り上げるために読む時間をいわゆる夏休みの期間にしました。仕事はずっとあるにしても少し気分も余裕も違う8月にしたのは、あまり細切れに読書をしたくなかったのと、わずかな紹介文を読んで知ったこの作品の雰囲気に夏休みのような時間の空間がふさわしいような気がしたからです。つまり少し楽しんで読みたいという気持ちがあったのです。
実際、2023年度の「ゴンクール賞」、2024年度「日本の学生が選ぶゴンクール賞」を受賞していること、前評判の良さなどから、そして(疲れていたので)私が前回扱った作品のもつ過酷な現実ではない、美術とイタリアという背景に勝手に期待していたのでしょう。結果的に作品を楽しむという意味では大正解でした。ただ内容はかなり想像を超えたものでした。邦訳は500ページの分厚さで、とても多くのエピソードや史実が語られていますが、立ち止まったり後戻りすることもなく読み進められる作品です。訳文も実に読みやすく、原文とそれは変わりません。本当に夏休みの読書にはピッタリ!というのが私の印象です。(今時すでに遅しですが)そのような前置きはともかくとして、作品そのものに話を移しましょう。
この作品の枠組は、主人公ミモの生年1904年から没年1986年までです。そして実際に描かれているのは前半分のそれも1914年(第一次世界大戦初年)から1946年まで(第二次世界大戦の終戦翌年)です。残りの半分の40年は主人公が修道院の奥深くに身を潜めたので語られていません。作品冒頭に死を前にした主人公の描写があり、その後すぐに彼の(一人称の)声が自らの一生を物語り始めます。彼とはミケランジェロ・ヴィタリアーニ、イタリア人の父母がフランスに移ってから生まれたのだけれど、本人は12歳の時に戻ったイタリアを「我が祖国」と呼んでいます。母から彼をあずけられた石の彫刻家「アルベルトおじ」は仕事を求めて、子どもをつれてリグーリア地方にあるピエトラ・ダルバという村に定住します。そこから全てが始ります。
登場人物
主人公
ミモ(ミケランジェロ・ヴィタリアーニ):生まれつき身長が140cmどまりというハンディキャップをもちながら、それ以上に稀なる石像の彫刻家としての才能をもつ天才。生まれが貧しく、引き取られた(血縁ではない)「アルベルトおじ」に虐待をうけながら仕事の手伝いもして育つ。
ミモの身近な人々
ミモの母(アントネッラ):息子が12歳の時に、息子を父親と同じく彫刻家にするために彼をイタリアに送りだす。
アルベルトおじ:ミモの祖父の知り合いの息子。ミモをお金と一緒にあずかって、美しい教会とオルシーニ家の城館があるピエトラ・ダルバで仕事を始める。
ヴィットーリオ:ミモより3歳年上で、アルベルトおじがアトリエを買い取った時に付録として引き取らねばならなくなった少年。とりたてた才能はないが心根の優しいよい家具職人となる。ミモの親友。
エマヌエーレ:ヴィットーリオの双子の弟。重大な身体障害があるので兄しか言葉を理解できない。制服マニアで郵便配達が大好き。
オルシー二家の人々
ピエトラ・ダルバの領主、オルシーニ侯爵夫妻:広大な領地におけるオレンジと檸檬の栽培で富をえている。
ステーファノ・オルシー二(次男):長男亡き後、家督をつぐ。保守的で乱暴。
フランチェスコ・オルシー二(三男):若くして僧籍にはいる秀才。妹にある程度の理解を示し、度々助ける。ミモとも親しくなる。
ヴィオラ・オルシー二(一人娘):幼いころから本を読み、知能が非常に高く、あらゆることに興味を示すが、とくに空を飛ぶための機械を隠れて作製している。ミモと自分が(生年月日が同じと聞いて)「宇宙双生児」だと信じている。
その他の主な登場人物
フィリッポ・メッティ:フィレンツェでミモを雇う親方。
リナルド・カンパーナ:ヴィオラと結婚する成金弁護士。
ピッツァーロ:フィレンツェのサーカスの座長。暗黒街にミモを導く。
500ページという長さの小説で、さまざまなエピソードと多くの登場人物が現れるにも関わらず、実際にストーリーの流れの中で絶えず表れる人物はこれだけというのも珍しいことです。そのせいか、読者は基本的に主要なストーリーから迷子になることがありません。登場人物の名がわからなくなることもないのです(日本人の読者にはありがたいことと思います)。
ストーリー
1986年の秋の日、サクラ・ディ・サン・ミケーレ修道院では、修道士ではない82歳のひとりの老人が臨終の時を迎えようとしている。彼の存在は40年間に亘って彼の最後の作品、”ピエタ”(聖母子像)とともに世間から隠されていた。
ミモと名乗るミケランジェロ・ヴィタリアーニは1916年12歳の時、アルベルトおじとともにピエトラ・ダルバで生活しはじめ、ヴィットーリオとエマヌエーレという友人を得る。ある日偶然の事故で侯爵の屋敷の一人娘ヴィオラの部屋に飛び込んでしまう。彼女はすぐにミモを受け入れ友人となる。二人は屋敷の外の森の中の墓地で夜中に隠れて出会うようになる。ヴィオラはミモに沢山の本をこっそり貸して、ミモはその本を読んで知識を得る。その内に、ヴィオラは自ら空を飛ぶための機械を密に研究してミモとヴィットーリオとともに制作を始める。16歳になるとヴィオラはある貴族の息子と婚約させられることになるが、その婚約発表の日に飛行機で飛び立つことを決行する。その後のヴィオラとミモの運命やいかに…
ここまで一気に読んでしまいましたが、ちょうど全体の最初の3分の1を読み終えています。このはじめの部分の作品の印象は、まさに、冒険小説、おとぎ話、そして教養小説です。まだ12歳の一人の少年と一人の少女(二人の間には庶民と貴族という身分差があります)、少女は非常に理知的であり、少年は教養がないという違いがありながら、他の人とは全く違うという自覚は共通です。周りの大人たちには秘密にしている行動で二人は結ばれ、大人たちには魔法のように思われることもできる。恐らくハリー・ポッターを読む感覚に近いのではないでしょうか。背景の大きな城館と森、熊に変身する少女はおとぎ話を、20世紀初頭の大金持ちと搾取される子どもというシチュエーションも教養小説を想起させます。誰でもが引き込まれる物語の世界です。
1920年を境にその次に始まるのは、世界の歴史を背景にしている小説です。詳しい内容をここで語ってしまうことはできませんので、この先のストーリーの構成のみをご紹介しましょう。ここでヴィオラとミモは引き離されます。ミモはフィレンツェの別のアトリエにあずけられます。親方の名はフィリッポ・メッティ。彼こそがミモの初めての本当の親方といえる存在となります。ミモはそこで大人の世界に飛び込みます。「フィレンツェ、暗黒時代。誰かが私の伝記を書くなら、素晴らしい見出しになるだろう」とミモは語ります。しかし、主人公の彫刻家見習いはその地で真の芸術というものに触れ、彫刻家が果たす仕事の真意を学び、同時に無垢な心は人間の暗く悍ましい面をも知ることとなります。1918年に第一次世界大戦は終わり、戦後の混乱、ファシスムの台頭という社会の歴史的変化も見え隠れします。2年を花の都で過ごした後、その後はフランチェスコの導きで一度ピエトラ・ダルバに戻りながらも、ヴィオラとの再会は果たされぬまま他の地に奔走します。
これ以降のミモは、もはやかつての“みにくいアヒルの子”ではなく、比類のない才能をもつ芸術家として社会に存在を認められます。彼の業績と名声がどのようにして築かれていくかというのも、とても興味深いものです。そのことについてのミモの考え方は、意外と思えるほど短絡的ですが、その点については最後まで読み進める必要があります。
テーマ
愛と友情
登場人物たちの繋がりは、血縁、身分、職業とさまざまでありながら、基本的には彼らの間になにかしらの親和力があるようです。もちろん家族でありながらもなんの絆も感じられないこともあります。ミモとヴィオラには、他の人たちとは違うという生まれ持っての自覚があり、それをどのように生きていくかという孤独な状況が、より一層二人を結びつけることになりました。ただ別々にその問題を生きて行かなければならない時があることをも受け止めながら、二人はお互いを求め、助け合い、ともに前に進むことをあきらめません。この愛は、ある時に一目惚れとして現れる情念とは違います。だからこそ彼らの愛は苦しい努力を必要とする友情であったり、他には見ることがない絆となりながら体は離れていても心が離れることはありません。ミモと他の人物たちの間に見られる友情も、非常にシンプルなものであったり、時には条件付きであったりはしますが、相手を信じることを基本とし、裏切りは重大な危機を招きます。イタリアを舞台とする小説なので、また宗教的な主題をあつかう彫刻の芸術家の物語であるせいか、自然と愛の概念にキリスト教の発想があるようにも思えます。例えば裏切りという行為は、聖ぺテロのイエスに対する裏切りを喚起します。信頼と裏切りがとても重要で複雑な問題であるということを改めて認識させられました。
ジェンダーと差別
最近はこのジェンダーの問題が人類始まって以来の解決されることがない問題として文学作品に散見します。確かに、男女という基本的性別が存在するので、社会でも宗教でもその二つの性を基本としてさまざまなルールが築かれてきました。ヴィオラは少女の時からこの差別に理不尽を感じ、異を唱えます。その後の彼女の成長は物語を読んでいただくことにしましょう。ミモについては最初は身分の低さと、特に、身長が成長と比例しないという(140cm止まり)目立った特徴のために差別を受けます。彼はその比類のない才能と不屈の精神によってこの問題を跳ねのけていきますが、彼自身恐らく社会にある限り最後までそのコンプレックスを完全に無くすことはなかったことでしょう。なぜ主人公がこのような特徴を持つ必要があるのかということへのコメントはまだ見つけてはいませんが、多分、20世紀初頭が舞台の小説の演出としての効果と、何かしら身分だけでなく生まれつきのハンディキャップがあるということが、才能の異常さとのコントラストを生む効果になるのではないかと思います。またそれがミモに不屈の意志と生命力を与えたのでしょう。一方で、自分たちと違う人に対する人々の差別意識が常に存在することを読者が忘れないようにという作者の意図があったのかも知れません。
自然と都市
この作品の中でもうひとつ大きな役割を果たしているのが、石と水と風と大地、そして自然災害です。オルシーニ家と隣人の水争いは両者の富と名声、権力を決定するもので、そこに政治がからんできます。物語の背景となるのはフィレンツェやローマのような都でもあれば、地方の貴族の領地(農地)でもあり、それぞれの美しさを知る読者には非常にノスタルジックなイメージを喚起するのではないでしょうか。オレンジと檸檬の輝く大地と、煌びやかな歴史的都市の(暗黒の部分も含めて)芸術にも劣らない美しさがこの作品に息を吹き込む魅力でもあるはずです。
芸術家と芸術
この小説には、主人公のミモ以外にも、何人もの彫刻職人が登場します。まず、ミモの実の父親、アルベルトおじ、フィリッポ・メッティとその工房の職人たち、そうでなければかのミケランジェロ・ブオナローティ(ピエタの作者として)、そして絵画ではフィレンツェのフラ・アンジェリコ(受胎告知)…実に天才芸術家からアトリエのそこそこの腕のベテランまでの作品と仕事が語られています。当時の彫刻とは注文されたものを制作していました。しかしミモは自分の才能の意味となすべきことに疑問をいだき始めます。
そして"サスペンス"
この作品のタイトルは「彼女を見守る」ですが、原タイトル(フランス語でVeiller Sur Elle)の忠実な和訳です。彼女とはだれか。見守るというのはなにを意味するのか。この疑問は読書の初めから終わりまで読者につきまといます。表現としても美しいこのタイトルは、作品を読み始める時から、作品に密やかで音のない、静謐なまさに修道院の奥深くを思わせるイメージを与えます。それこそが実際にはこの作品がかなりドラマチックで奇想天外な物語であることと不思議なコントラストを成すと同時に、重要なメッセージを秘めていることも予想させるのです。ですからとてもうまいタイトルだなと感心させられました。この作品が、1916年から1946年までの短い間の、ローカルでしかもミモとヴィオラという主人公たちだけの生涯に関わるものでありながら、ひとつの歴史絵巻として読ませる力があるのは、作者の力量によるものでしょう。作品の終盤は圧巻ですが、冒頭に予告されたミモの臨終間際の修道院の描写は、作品の構成の円環性を予告し奥深さを暗示しています。*
作者ジャン=バティスト・アンドレアについて
1971年、フランスのパリ郊外で生まれました。祖母の一人がイタリア人、父の両親はアルジェリアに入植したフランス人、それ以外にもスペイン、ギリシャの流れをくむ多様な文化環境で育ちました。大学はフランスでもトップの教育機関であるパリ政治学院とパリ高等商業学校を卒業した秀才でありながら、上級国家公務員や企業家にもならず、映画の制作の仕事に身を投じます。制作に関わった作品では2003年にホラー映画Dead End (邦題『-less (レス)』)で高評価を得、いくつもの他の作品にも関わりましたが、映画界での20年のキャリアの後2017年初めての小説を発表します。理由は、映画というのは資金はもとより大変多くの拘束の中で大勢と一緒に作らなければならないが、作家はそのしがらみが何もないので、自分が本当に作りたいものを作れるからということのようです。(以前に他にも同じ理由で小説家になった映画畑出身の作家を紹介しました。『三つ編み』のレティシア・コロンバニです) 第1作Ma reine 『私の女王』(未翻訳)を発表した後も2作の小説を発表し、この『彼女を見守る』は4作目です。おりしも彼は52歳、かなり遅咲きと言われましたが、本人自身は自分が本当にやりたかったことができているし、小説は自分の表現方法としてぴったりだと喜んでいます。確かにゴンクール賞を受賞したのですから、彼の判断は間違っていなかったのでしょう。『彼女を見守る』の中にもりこまれたすべての要素の多彩さと構成の確かさ、テーマの独創性、伝統的側面、なによりも作者が子どものころから大好きだった「強い女の子/女性」のモチーフは、彼の言うとおり、「自分がやりたいことをやりたかった」というのにふさわしい作品です。インタビューで「ヴィクトル・ユゴーとアレクサンドル・デュマだったらどちら」**という問いに迷わず「デュマ」と答えたのが微笑ましかったです。そして、2013年ゴンクール賞受賞作家のピエール・ルメートルとともに、大衆文学によるゴンクール賞受賞達成を果たしたと言われています。
このような作品を戦後80年を記念した報道が沢山でた2025年の日本で、その暗黒の歴史ともいえる時代を重ね合わせながら読むことは、私にとって非常に印象深いことでした。特にイタリアはかつての"同盟国"でありながら、その歴史の細部をよく知らずに過ごしていたからです。
さらに考えさせられたのは、ちょうど8月下旬にBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下で始まった『パルテノペ ナポリの宝石』というパオロ・ソレンティーノ監督のイタリア映画を見て、すなわちイタリアの世界観を改めて見ることによって気づいたことでした。確かに文字で書かれ、表現されているイタリアを美しいと想像できるとしても、(もちろん多くの読者や翻訳者の方が)実際にその場でみたイタリアを知らずにこの作品の世界を想い描くのはかなり難しいと思います(この小説の舞台が主に北イタリアで、映画はナポリという大きな違いはありますが)。人、自然、美、言葉、そして歴史、宗教が日本とは全く違った世界、その体感と体験がなければ作品独自の味わいが完全には伝わらない、というのはどうしようもないことなのでしょう。文学を読むとさらに遠くまで行きたくなるのはそのせいでしょうか。それも文学の醍醐味だなと思うのは私の個人的な感想です。皆さんはどうでしょうか。