No 26社会への問いかけを秘めた“超”個⼈的記録
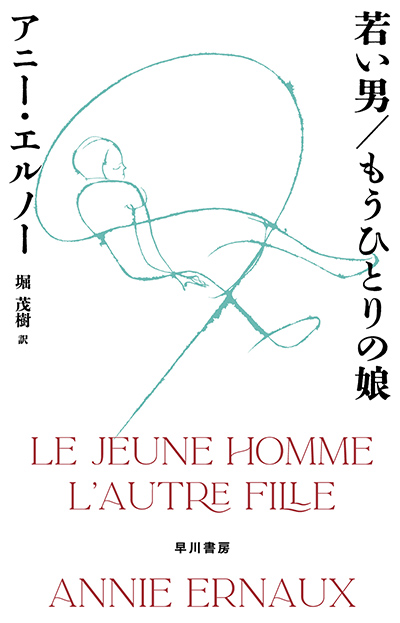
ノーベル賞作家自身の語りの中にある普遍性
読書にはなかなか根気が続かないほど厳しい暑さの夏でしたが、今回はあっという間に読める短編2作を収めた新刊、アニー・エルノー作の邦訳本『若い男/もうひとりの娘』をご紹介します。アニー・エルノーはご存じのように、2022年ノーベル文学賞を受賞したフランス人女性初の作家です。今年の夏はパリ・オリンピックの開催があり、日本でも普段より少しフランスへの人々の注目度が上がったような雰囲気があります。開会式、競技会場、閉会式でも、さすがと思わせるフランスのこのようなイベントにおける演出力が惜しげもなく発揮されました。皆さんも、見る人、競う人すべてが公平な立場にいて、協力して未来にむけてがんばる姿に感動したことでしょう。一方で、もっと個人的な作業である読書によって、そのフランスの少し前の時代の人々の姿を知ることも、フランスをより深く知り、理解する手がかりになるのではと思わせるような作品が今回の2作です。
『若い男』
長い作品をどうまとめてご紹介するかということで苦労することはよくありますが、非常に短い作品の紹介に今回はとても悩みました。最初にご紹介する『若い男』は原文でわずか28ページ(邦訳35ページ)の作品で、筋もシンプルで、登場人物もわずかです。ですからいつものような、多くの人物が登場し、複雑なストーリーが絡み合い、そこに見るべきさまざまなテーマがいくつも存在する作品を紹介するのとは全く違った難しさを感じる作品でした。とにかく速く読みおえることはできたとしても、結局は何度も読み返し、さまざまなことを発見し、深く考えさせられる作品です。そこには、私の生活した90年代のフランスの社会が描かれているということも、ある程度関係があるかも知れません。
ストーリー
『若い男』は作者(語り手)が54歳の時に起きた30歳年下の男性との恋愛の5年間を語っています。原書が単独作品で刊行されたのが、2022年5月であり、エルノーが2022年10月にノーベル文学賞を受賞した時点では最新作でした
ストーリーの展開する場所は、恐らく作者が90年代に住んでいたパリの近郊と、その若い男(Aと作中では呼ばれています)の住んでいたパリから北西に位置するルーアン市。Aは一年もの間語り手に手紙を書き送った末(その内容は語られていません)、彼女との逢瀬にこぎつけます。最初はぎこちなかった二人も、やがて単なるデートを重ねるのではなく、本来の恋愛関係に陥ります。その後5年の間、彼らはカップルであり続けます。その経過がこの作品の骨子です。名のついた登場人物はこの二人のみという、非常にコンパクトな作品です。
付き合い始めるとやがて彼は若い同棲相手の彼女と別れ、語り手はルーアンの彼のところに毎週末通うようになり、日常の生活を分かち合うようになります。語り手はその日常を、つまり二人の日常とAの日常を細かく語ります。彼のアパルトマンが偶然、語り手が学生時代に入院した病院(その出来事はエルノーの他の作品『事件 L´Evénement』に描かれています)のあった場所に面していて、その「驚くべき符号」に語り手は「ひとつの不思議な出会いと生きてみるべきひとつの物語のしるし」を見出します。このアパルトマンでの生活は彼女を、学生結婚したころの彼女が過ごした「簡素すぎて不便な住環境」に再び遭遇させます。そして、彼の出入りのカフェや好きな音楽やテレビ番組の話の後、彼の食生活、ひいては食事の際にみせる癖さえも事細かに描きます。その彼は、彼女がかつて人生で出会ったことがないほどの情熱で、いわば信仰の対象のように彼女を熱愛しているのです。それに対して語り手にとってAは誰なのか。彼の情熱に応える愛はそこにあるのでしょうか。貧乏な学生であるAが作家としてすでに名をなしていた50代半ばの彼女(作中では職業や家庭環境は明かされていませんが)にのめりこむのは、彼女が彼にあたえるもの、旅行や「文学、演劇、ブルジョワ社会の作法」といったもののせいでもあり、年長で資力のある彼女と若く貧乏なAの間の支配関係も恐らく彼にとって居心地の悪いものではなかったのでしょう。このような二人の関係は、そこに新しい世界を垣間見る若い男にとっては、それが決して普通なら手の届かないものを与えたのであり、彼女にとっては実は30年前の彼女の生活を再び、場所も同じという状況で生き直すというまれなる経験であったのです。ということは、彼女はAとともに新しい人生を生きたかったわけではないということなのでしょうか。なぜそのような関係があり得たのかということを、この作品は描いています。
フランスの階層社会
まさにそこにこそ、アニー・エルノーの作品の最も特徴的な要素が現れています。この作品を読んで、奇しくも私自身が生きた90年代のフランスでうけた非常に強い印象、しかもフランス人に問いかけることができなかったひとつの謎が解かれたような気がしました。それは現代の日本人の読者にとって、ちぐはぐな、あるいはピンとこない内容であるかも知れませんが、このようなことです。外国で家族も知り合いもなく身一つで生活し始めると、言葉だけでなく、さまざま試練が毎日のように降りかかります。例えば、全く違う食習慣の文化におけるテーブルでのマナー。誰かの家に招かれ泊めてもらったりすると、一挙手一投足に気を遣い気が休まりません。なぜなら、なにげない言動、身のふるまい方がすべて彼らに判断されているように感じる時があったからです。私に直接何か言うわけでなく、誰か別の人(フランス人でも)のことを話している時にそれがわかりました。そして、この作品を読んでそのことがはっきりしました。つまり“社会階層”を知るための観察であったのです。当時は日本ではもうそれを問題にする人はあまりいなくなっていたのに対して、フランスではまだ、いうなれば“階層意識”というものが人々の中に染み付いていた時代だったということです。その社会では、人々の間で階層が違えば付き合いはありません。交わらないのです。ところで、「庶民(le peuple)」という言葉がエルノーの作品にはよく見られます。その「庶民」とは、誰のことでしょうか。私はずっと、特別な家柄でない限り、みんな庶民だと無邪気に思っていました。ずいぶん昔ですが、日本ではある時期、大変多くの人が“中の上”に自分は位置していると思っているという調査結果が報じられたことがありました。日仏のこの感覚の違いは、その社会に住まないと、例え住んでもなかなか良くわからないものです。フランスでは、まず特権階級(革命のあった国ですが、いまだにそうよばれる人々がいます)があり、その下にいるのが「ブルジョワジー」です。そして、さらに下の庶民とは当時の彼らの呼び方では“労働者”ということになり、“労働者”は比率的に国民の大多数でした。私はフランスにいる間、外国人という社会の部外者の立場にあって、彼らの社会における位置(階層)に対する意識の高さに驚かされることがよくありましたが、ブルジョワを名のる人々が誇らしげであるのは知っていても、庶民といわれる大勢の人々が庶民であることを恥じているとは想像していませんでした。でも、この動くことがあまりない階層の境界を越えていく第一の手段こそが、“教育”であることはわかりました。エルノー自身がその例の一人です。大学やグランゼコール1)に入り、高いディプロム(資格)を取得してエリートの一員になることで、階層を超えることは万人にあたえられたチャンスでした。ただ、一度超えたら後戻りはしません。次の世代がさらに高いディプロムを得ることに一家の望みをかけます。移民の中の多くの人にとって、これしか手段がないようでした。
うすうすわかってきていたこれらの事情をフランス人の友人に問いただす勇気がなくて、時には随分卒直な人たちだなあと思うにとどめていたことが、この作品によってこれほど、ほとんどはっきりと書かれていることに私は非常に驚きました。エルノーの代表作品『場所』を読んだ時には、ここまでストレートに感じることがなかったからかもしれません。フランス人読者の理屈ではなく、素直な感想を知りたいと今思います。 2)
不釣り合いなカップル
当時のフランスでまだかなりタブーであったこと、『若い男』のもうひとつのテーマは、年齢が非常に違うカップルです。それも女性の方が男性よりも年上である場合です。もちろんフランスでは現大統領夫妻の例もありますので、時代の流れとしても人々の感覚は変わってきているでしょう。でもこの話は30年前のことです。フランスは自由の国とはいいつつ、この点ではかなり偏見があったと思います。このテーマについては、それぞれの読者が自由に考えていただくのが良いと思い、これ以上のコメントは控えます。
『もうひとりの娘』
二つめの作品も邦訳版ほぼ100ページ(原書フォリオ版訳70ページ)のむしろとても短いものです。初版が刊行されたのが、2011年であり、『若い男』の約10年前ですが、執筆についてはきっかけとなる事情がありました。2007年9月21日付のNiL出版社の編集者クレール・ドゥブリュのエルノー宛の手紙が、同社の「解放された人々」叢書の最初の一冊として執筆を依頼しているのです。その企画により、同作は「任意の誰かに宛てて『これまでに一度も書いたことのない手紙』」 3)として書かれました。そして、エルノーは、1938年にジフテリアに罹患して6歳で亡くなっていた姉、ジネットに宛てた手紙を書いたのです。とはいえ、エルノーはその姉の存在さえも誰かに知らされたことはなく、全くの偶然から、(本人は知らずに)母親自身の口から盗み聞いていたのでした。この作品は、ある家のひとり娘だった女性が知らされずに育った夭折した姉の存在を、会ったこともおしゃべりをしたことも写真さえも見ることがなく育った姉のことを、どう自分の中に影として抱えてきたかをその姉に向かって語っているような内容となっています。
ストーリー / 内容
ストーリーと呼ぶような時系列なできごとの連なりははっきりとは見えず、ただ作品の冒頭の方に、「私」が10歳の1950年の夏のある日に「物語のその情景が現れた」と記されています。両親が営んでいたカフェ兼食料品店に来たある女性客に母親が話し始めたことを盗み聞きした「私」が、かつて自分が生まれる前にもう一人の女の子がいて、自分の生まれる二年前に6歳で亡くなっていたことを初めて知るのです。それだけでなく、母親が語る物語の最後の言葉が、「私」の胸に突き刺さります。
「最後に彼女は、あなたについて言う。"あの娘はね、この娘よりいい子だった"
この娘とは、私のことだ。」(57)4)
ある瞬間に、それまでの世界がすっかり変わったものになる、違って見えるようになるという経験を、特に子ども時代に誰しもがしたことがあるでしょう。私にもあります。そしてその経験はその後の人生の生き方に決定的な意味を与えることがあることも知っています。子どもは、その経験をどう生きるのか。それは、事情によってはそれぞれの子どもが知らず知らずに知恵とか、信じ込むということによって心の中にしまいこみ、長い年月がたってからやっと思い出して考え直すことであるのかも知れません。5)
物語では、この1950年の夏の出来事に続いて、「私」の記憶にもとづく親戚との思い出、両親の思い出、そして姉の存在を知らなければ気づかれることもなかったかも知れない生活のそこかしこに残る姉の存在のしるしが、掘り起こされていきます。知ることのなかった「姉」、同じ時に何も共有することがなかった、肉体としても触れることがなかった、ただ親戚や特に両親の意識に“常に”存在した「姉」が、いわば謎解きやパズルのように「私」によって描かれていくのです。恐らくそれは、「私」にとって長い間の習慣にも似たひとつの脅迫観念、妄想のようになっていて、だからこそこの手紙が書かれることが両親の亡き後「私」にとって必要となったのではないでしょうか。
アニー・エルノーの文体の簡素さは、最初の作品の時から特徴として際立ったものですが、簡素でありながらも文章の描写力、喚起力には大変な力があります。例えば、同じように重病(姉はジフテリア、妹は破傷風)を患いながら、ワクチンが間に合わず亡くなってしまった姉と聖水のおかげで奇跡的に生きながらえた「私」について(78-79)や、ジャン=マルク・レゼールの漫画の一つについて(86)であったり、昔の日記の中に見つけた子供のころの記憶と人生の本質についての記述(96)というような。すなわち、対象から受け取るイメージや象徴的な意味あいを描写する、またすべてのことを見逃さず、自分の感覚であれ客観的にとらえた事象であれ、そこにある意味合いに目をむけ、さらにそれを言葉にして描きだす能力はエルノーならではのものです。そしてそれこそが彼女のエクリチュール(書くもの、書いたもの)の最大の特徴である、個人の記憶に所属するものでありながら社会的な抑圧や不平等な条件という普遍的な意味をもつことがらを明らかにすることを可能にしているのです。6)今回は、そこで明らかにされることについては読者自身におまかせしましょう。
『もう一人の娘」には多くの登場人物が現れます。本当に「私」の環境に現実にいた人だけでなく、それぞれのエピソードに関わった人々です。場所についても、エルノーが生きた場所のそれぞれが実名で現れます。エルノーによると彼女の作品にはフィクションはないとのことです。それが読者にこの作品における社会の現実性を確認させるという役割を果たしているのでしょう。
アニー・エルノーと作品
アニー・エルノーは、1950年に生まれ、1974年に初めての作品、『空っぽの箪笥 Les Armoires vides』(邦訳なし)を上梓し、以降3作品が出版された後、1983年に発表した『場所 La Place』でルノードー賞を受賞した時から著名な作家となりました。この作品は、工場労働者であった父が母とともにカフェ兼食料品店を営みながら優秀な生徒であるひとり娘の学業を応援し、成功した娘はその後両親の世界を去りますが、父の葬式に際して彼の人生に思いを馳せるという内容です。その前作、『凍りついた女 La Femme gelée』(1981年)以降の7作が80、90年代に日本でも続けて翻訳出版され、今年の春ほぼ20年ぶりに『若い男 Le Jeune homme』/『もうひとりの娘 L´Autre fille』の邦訳が刊行されました。エルノーは、しばしば自伝的小説作家と紹介されることがありましたが、本人は自分の作品は自伝的小説ではなく、普遍的な「私」の語りによるむしろ文学と社会学と歴史の間にある作品であると主張しています。20世紀後半に現れたフランスの女性作家としては、デュラスに続く、社会的行為としての著述を特徴とする作家といえるでしょう。
とはいえアニー・エルノーの今回の作品を読み、前々回に扱ったモアメド・ムブガル・サールの作品『人類の深奥に秘められた記憶』を思い浮かべると、やはり前者には円熟さを、そして後者には言うに言われぬ新鮮さを感じるのは私の偏見でしょうか。エルノーも40年前には新しい文学の旗手とみなされたのですから、文学が月日の流れとともに新しい才能を輩出し進化していくことも応援し、新旧ともに今後の活躍を見守っていきたいと思います。