No 25家庭料理が芸術に昇華していくまで
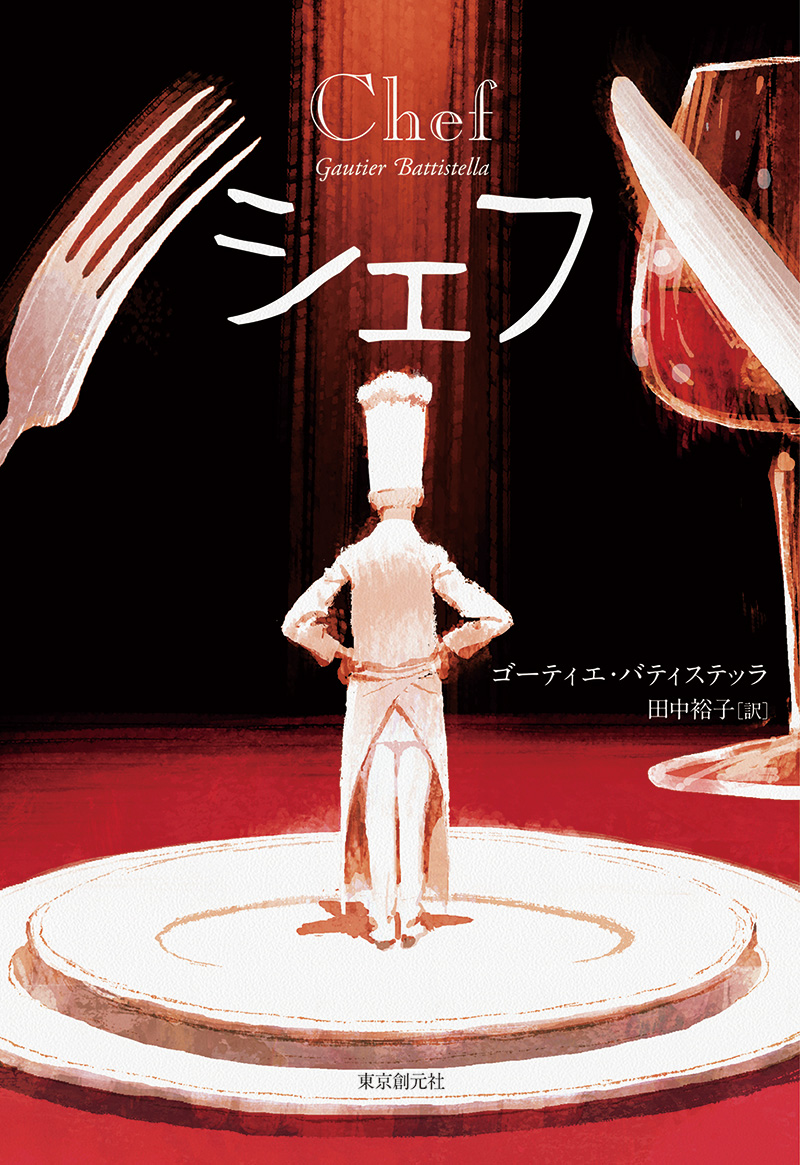
きらびやかなフランス料理現代史の舞台裏を描く小説
前回はかなり「フランス文学」に親しい読者向けの作品だったかも知れません。今回はむしろ「フランス料理・ガストロノミー」ファンの方たちにより訴えかける作品と思います。
さて、みなさんはフランス料理というと、どんなイメージをお持ちでしょうか。実際よく食べるという方はどれくらいいらっしゃるでしょう。戦後40年の1980年代から日本でも本格的にフランス料理が紹介されはじめ、都市部ではフランス料理のレストランもどんどん増えたように覚えています。テレビでもフランス料理を紹介する番組が人気を博し、食べたことはなくても見たことくらいはある…という感じだったでしょうか。一般的には、私たちがイメージするフランス料理とは、オート・ガストロノミー(最高級料理)と呼ばれるものです。写真やテレビで見るばかりで、本当に味わうことはめったにありませんでした。しかし80年代後半に、東京の小さな映画館で公開された『バベットの晩餐会』というデンマーク映画が、19世紀のフランス料理の準備から豪華な食卓までの一連の工程を映して、意外なヒット作となったのです。今でもフランス料理を扱った名作映画の筆頭にあがる作品です。昨年末には、Bunkamuraル・シネマで『ポトフ 美食家と料理人』という作品が公開され、大評判になりました。19世紀末のフランスのある美食家とそのパートナーの女性料理人の話ですが、リアルな調理シーンを描くその洗練された映像と音響で、また料理を愛する人々の一途な思いを繊細に描いたストーリーで、感動的な作品でした。その一方で、料理というのは、まず見て(聞いて、匂いを嗅いで)味わうものですから、この画像がないと、外国の料理というのは思い描くことが簡単ではないとつくづく思いました。
ところが、今回とりあげた『シェフ』(2022年)という作品は、今まで映像で見て知っていたフランス料理の一面だけでなく、フランス料理の、特にオート・ガストロノミーの料理人の世界をもっと深く、映像では描ききれない部分までを描いているのです。すべてが、登場人物と語り手によって言葉で伝えられていて、料理の描写とともに登場人物の心理描写の喚起力、正確さに深く感心させられました。さらに、この作品では料理をめぐって、約80年前からのレストランの歴史、レストランで供されるさまざまなタイプの料理の特徴、シェフと彼のブリガード*が生きる料理人の世界、ビジネスとしてのレストランの経営、特筆すべきはあの有名なレストランの格付けをするガイドブックの存在の意味を問題にしています。盛沢山ではありますが、ちゃんと、あるトップシェフがなぜ頂点に立った直後に自殺したのかという謎を冒頭から投げかけているので、それがストーリーを最後までまっすぐ導いています。全35章で構成されていて、奇数章ではポール・ルノワールという自殺を遂げる主人公の独白による彼の生涯が、偶数章では彼の死後のレストランの、残された料理人たちとレストランの行く末が三人称で語られています。
主な登場人物
ポ-ル・ルノワール・・・この小説の半分を占める独白の語り手であり、主人公のひとり。レストラン『レ・プロメス』のオーナーシェフ。料理人であった祖母イヴォンヌを見て育ち、祖母の仕事を引き継いだ父を持ち、11歳から運命として料理人の道を歩み、62歳でシェフとして料理界の頂点に上りつめた。
ナタリア・・・ポ-ルの妻でレストラン『レ・プロメス』のマネージャー。ポールとの間に一人娘クレマンスをもうける。
イヴォンヌ・ルノワール・・・ポールの祖母。『シェ・イヴォンヌ』のシェフ。彼女の姿がポールを料理人の道に導いた。
マティアス・ルノワール・・・ポールと前妻ベティとの息子。父に敵対的対抗心を持つ野心家。
マリアンヌ・ド・クールヴィル・・・『ル・ギッド』の革新派の新女性編集長。
『レ・プロメス』のブリガードのメンバー
クリストフ・・・スー(副)シェフ。ポール亡き後に『レ・プロメス』のシェフとなり、ナタリアとともにレストランの存続に努める。33歳でこの世界に飛び込んだが、とびぬけた才能をポールに認められ急速に出世する。穏やかな性格。この小説のもうひとりの主人公。
ディエゴ・・・ソーシエ。肉料理担当シェフ。スペイン人。少し気が荒いが、料理の才能は一級の有望な料理人。
ジル・・・魚料理担当シェフ。16歳で裕福な実家を飛び出した時、見習いとして迎えてくれたポールに魚についての全てを教わった、孤高の料理人。
ユミ・・・製菓担当シェフ。日本人。ポールやブリガードの仲間に愛される才能あるパティシエール。
この登場人物たちに加えて、多くの美食評論家や他店のシェフ、そしてポール・ボキュ-ズやアラン・デュカスなどの伝説の名シェフも登場します。
これらの料理人については、その人物の性格、特徴がオート・ガストロノミーを支える人々の必須の才能であるかのように書き込まれています。例えば、「ミツバチはぼくたちと一緒だ。働きすぎて死んでしまうこともある。本能的なものなんだ。」(16)「家で自分たちを待っているのはソファだけ、よくて猫が一匹いるだけだ。ほとんどのスタッフがひとり暮らしをしていた。」(41)「ディエゴはきっと一流のシェフになるだろう。性格的にも料理人向きだ。個人主義で、完璧主義で、自らの名前を冠する店をだすためには、健康だろうが、愛ある生活だろうが犠牲にする覚悟がある。」(145)このように、一般の人々にはあまり見られないような、並外れた忍耐力、禁欲的とも言える料理を追求する信念を持ち合わせているのが、オート・ガストロノミーの職人であり、料理を芸術の域に高めることができる人々なのです。彼らを統率し、ブリガードを指揮していく人格と能力がある者のみが最高のシェフとなることができるのです。
ストーリー
フランス南東部、スイス国境に面するオート・サヴォワ県の首都であり、避暑地としても有名なアヌシー市にある5年連続三つ星を獲得しているレストラン『レ・プロメス』のオーナーシェフ、62歳で「世界最優秀シェフ」に選ばれて間もないポール・ルノワールが、ある月曜日の朝、妻のプレゼントであった猟銃で自殺した。なぜかは誰も知らなかった。丁度その日からネットフリックスの撮影隊がポールとレストランのドキュメンタリービデオの撮影に訪れていた。事件直後は、シェフの死を隠し、『レ・プロメス』のスタッフ、ポールの妻ナタリアとスーシェフのクリストフがブリガードのみんなを指揮して厨房をまわし、ドキュメンタリーの撮影をすすめさせるが、翌日には秘密は世間に知られていた。このスキャンダルはフランスだけでなく世界中の話題となり、葬式の場には故人に哀悼を捧げる人々だけでなく、トップシェフの死とともに訪れるチャンスを狙う様々な人々、レストラン業界関係者(きらびやかな他のトップシェフたち)、ジャーナリストが押し寄せる。ポールの家族、『レ・プロメス』の料理人、従業員たちは、精神的にも物質的にも非常に困難な状況に直面する。ポールは経営については無頓着で残された財政面での問題は深刻だった。そして非常に不仲で疎遠であった実子のマティアスが相続の権利者として乗り込んでくる...
一見ありふれた筋書きのように思えますが、冒頭から平行して、ポールの語りによって、彼の祖母イヴォンヌの代からの家業である料理店が、どのようにして、村のレストランからブルジョワが来る一つ星レストランになり、さらに様々な紆余曲折を経ながらも、ポールの三つ星レストランまでたどりついたのかが、フランス料理の20-21世紀史のように描かれています。レストランは、上手く経営しなければ儲かりもしないし、うっかりすると他店に買い取られたりします。地方の小さな料理店の困難な経営の現実だけでなく、地域社会とのつながり、役割、レストラン同士の共存の在り方というようなとても興味深いことを私も初めて知りました。そしてこのポールの物語こそ、彼の謎の死を理解する大きな手がかりとなるものなのです。
『シェ・イヴォンヌ』
イヴォンヌは1910年にフランス南西部、ガスコーニュ地方で生まれた。母マリアが料理上手でレストランのような仕事を始め、イヴォンヌも幼くして厨房の仕事を覚え始めた。料理がとても好きだったので、さまざまな仕事をおぼえ、夜になると一日の出来事を鍋に向かって話した。当時は、高級レストランより、良心的な家庭料理を出す店の方がずっと人気が高かった。しかし、第二次世界大戦が始まって、すべてを失う。それでも、一念発起して、我慢強く家畜を増やし、菜園を作りなおしてレストラン『シェ・イヴォンヌ』を再開する。ただお腹が一杯になる料理ではなく、もっと繊細で、地域の町や村から、そしていつかはパリからもお客さんが来るような店にするつもりで。店はどんどん成功していったが、彼女の料理に対する思いは常に誠実だった。「近所の大食いたちが何も考えずにがつがつと食べ尽くしてしまう料理に対して、どうしてそこまで神経を使うのか、当時のぼくにはわからなかった。それこそが偉大なるシェフの証だと気づいたのは、ずいぶんあとになってからだった。イヴォンヌはすべての料理に全身全霊で取り組んだ。ゲストに満足してもらうためには、決して妥協しなかった。」(32)そして、彼女の料理の評判があの伝説的な女性シェフ、ウジェニ-・ブラジエとの出会いをつくり、それをきっかけにイヴォンヌはより挑戦的に料理に取り組み続け、ついに1968年には『ル・ギッド』の一つ星を獲得する…
もちろん、具体的に新しい料理を創造し、レストランを進化させていったのはイヴォンヌを含めた多くのシェフたちです。とはいえ、レストランの経営と同時に料理そのものの進歩の背景には、ある重要なファクターが存在することも描かれています。
『ル・ギッド』
『ル・ギッド』という呼称で登場するのは実は、日本では「ミシュランガイド」と呼ばれるフランス全国のレストランとホテルを厳選し、星による格付けしたガイドブックのことです。よくご存じの方も多いと思いますが、日本版もあり、日本中の評判のよいレストラン、料理店が掲載されています。フランス料理だけではなく、和食、中華料理など、さまざまな料理が対象になっています。その権威はいまでは不動のものとなり、毎年星の獲得と、星を失う“格落ち”が、料理人の名誉だけでなく、店の集客に大きな影響を与えます。審査の方法は、毎年覆面調査員という人たちが、誰にも気づかれないように来店し、厳しい審査の結果を翌年のガイドで発表します。その結果は世界中のガストロミーファンの注目の的となり、シェフには栄光と成功をもたらすものですが、時に敗北を恐れる心やプレッシャーによる悲惨な事件をひきおこすといわれていることも知られています。まさにシェフたちの死闘という裏舞台をこの作品は描いているのですが、それだけでなく、この現状の再考を喚起していることも重要な点であり、興味を抱かせます。この作品はフランス料理の舞台裏を描いた最初の小説だということも、問題のある種のタブー性を示唆しています。
ポールの祖母イヴォンヌの物語は、この作品において非常に重要で象徴的な意味を持っていると思えます。彼女だけでなく、1933年に初めて三つ星を獲得したウジェニー・ブラジエの存在についても同様です。作品の中では、かつての女性シェフはむしろ幸福なサクセスストーリーを歩み、男性シェフたちは、精神的にも追い詰められたような緊張の連続である厳しい、ただ辛い日々の中で料理を追求しているような印象をうけます。でもそれではあまりにも短絡的でしょう。戦後の経済成長とさまざまな社会の変化の中で、いつのまにか料理店とシェフの目指すものが変化してしまったという風にも読めます。作者のバティステッラはイヴォンヌをはじめとする女性の料理人、プロであれ家庭の母であれ、昔から家族のために、誰かのために料理をする女性を称えて、「女性が料理を発明し、男性はそれを褒め称えることに甘んじたのだ」と言います。私としては、男性、女性の区別なくシェフたちは料理の今に貢献したと思いますが、歴史的な女性シェフの存在を知ったのは比較的最近です。イヴォンヌの物語は、ですから、ひとことで言えば、驚きでした。確かにこのエッセイの冒頭に書いた『バベットの晩餐会』でも、『ポトフ 美食家と料理人』においても、料理人は女性でした。ほとんどが男性であると思われ、今でもマッチョな業界であるオート・ガストロノミーは、実のところその始まりにおいては女性に負うているものが大きいということなのかもしれません。あるインタビューで、バティステッラは多くの家庭で家族の絆が料理であったことを訴えます。少し前までは家や町のレストランで家族と食事を楽しむことが大事でもっと機会も多かったです。ところが、単純に美味しい、素朴、シンプルな料理を出すレストランが今では様々な理由から、全く違う姿になってしまっています。確かに同時に家族の在り方もかつてとは変わってしまっています。核家族化がすすみ、家族がテーブルを囲んで集うことも少なくなりました。作者はさらに、現代のオート・ガストロノミーはもっと一般の人々にも手の届くもの、開かれたものであるべきだと考えます。あまりにも特権的な人たちのための料理であってはならないというこれも料理の原点に立ち返るという発想であり、さまざまなジェネレーションにも受け入れられる、万人のための料理という民主化を想起しています。
そのような視点から見れば、歴史上初めてオート・ガストロノミーの裏舞台を文学、しかも限りなく現実に近い小説(フィクション)で扱ったのは、大きな挑戦であり、オート・ガストロノミーの将来を問うという試みでもあるでしょう。文学は、こうして、文字通りの“アートのためのアート”ではなく、私たちの世界で起こっていることを、多くの人に伝える、知らしめる、そして問題提起を促すという役割を果たすことができるのです。本当のことだけを実名で書く義務もなく、より深いメッセージを喚起するという意味で、フィクションを媒体として真実を伝えることができる文学でこそできたことなのかもしれません。バティステッラの次回作を楽しみにしています。
作者について
ゴーティエ・バティステッラは1976年、フランス、トゥールーズ生まれ。パリ政治学院で政治学、ストラスブール大学でジャーナリズムを学んだ秀才です。北京の新華社通信で働いた後、アジア各地をめぐり、その後ミシュランガイドの編集部員として15年間働いた後、小説家に身を転じました。『シェフ』は彼の第3作目の小説です。ミシュランガイド編集部に勤務している間に経験、見聞したことをもとにオート・ガストロノミーの裏舞台とシェフたちの姿を、史上初めて書いたのがこの作品です。彼は、この作品に書かれているエピソードは、それなりに小説化されていたとしてもすべて「本当のこと」だと断言しています。出版後、何もミシュランガイドからはコメントは受けていないそうですが、彼はこの作品は告発の書というよりも、すべてのシェフとフランス料理に対する敬意と賛辞を捧げるものと呼び、読者もそれを素直に認めることができると思います。すべてのシェフに乾杯‼