No 11文学を愛する人々の交流の場『真の富』書店
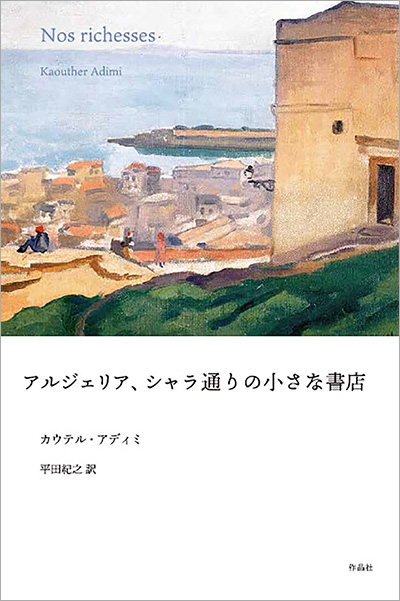
カウテル・アディミ著/平田紀之訳/作品社
伝説的なアルジェリア出身のフランス人編集者シャルロの生涯
現在は存在しない住所、アルジェリアの首都アルジェの「シャラ通り2の2」(現在はハマニ通り)を訪れる著者による街の描写からこの小説は始まります。2017年のその界隈を描く著者の視線は、彼女の生まれ育った都市を愛でるそれであるとともに、小説の舞台の書店『真の富』を初めて訪れる人の好奇心に満ちています。この小説を書くきっかけは、著者自身が散歩の途中にその書店のショーウィンドーに書かれた、「読書する一人の人間には二人分の価値がある」1という言葉を見つけたことでした。
この小説は、ある書店の誕生から始まり、その創設者である、エドモンド・シャルロという伝説的なアルジェリア出身のフランス人編集者(1915-2004)の編集者としての生涯を、少し変わった構成で描きだしています。大きな軸は、シャルロの“実在しない”日記(1935年-1961年)によって描かれる、多くの資料と調査に基づく彼の生涯と、現在の視線で描かれる、書店を閉めに来たリアドというやはりアルジェリア系のフランス人大学生の物語です。さらに、アルジェリアの1930年から1961年までの歴史が日記と並行して挿入されています。そこには現実の歴史が描かれていますが、上記の手法がこの作品を物語として読むように読者を導いていきます。
1936年、シャルロは21歳の時たったひとりで、この「シャラ通り2の2」に『真の富』書店を開きます。とはいえこの書店は同時に貸出専門図書館、出版社、アートギャラリーであり、そこから多く20世紀前半の作家が初期の作品を世に出すと同時に、彼らと文学を愛する人々の交流の場となっていくのです。彼らの中には、アルベール・カミュ、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ、ジャン・ジオノ2、アンドレ・ジッド、ヴェルコール等の日本の読者もよく知っている作家も多く、カミュの最も初期の作品はシャルロによって出版されています。この小説で語られる各作家の逸話は非常に興味深いものです。日記からは、シャルロが文学への情熱に掻き立てられて、自身の夢と理想にもくもくと突き進んでいく姿が浮かびあがります。そこには、第二次世界大戦下と、それに続くアルジェリアの独立紛争の間、困難な事業に立ち向かう彼の奮闘と、そのために彼が拠りどころとする友情も、あまり理想化されすぎずに描かれています。シャルロの驚くべき業績に目を見張りながら、作家と編集者を結ぶ絆に、読者はなにかなつかしい価値観を見出すのではないでしょうか。それをカウテル・アディミは「地中海精神」と呼んでいます。
この作品の読ませどころの一つとして、全編をとおして語られる、フランス文学出版史ともいうべきシャルロの業績があるでしょう。現代とは全く違う出版界の現実を踏まえても、一人の編集者がこれだけ多くの作品と作家の誕生に貢献したことは、編集者の存在の持つ意味を再認識させるものではないでしょうか。それが現在の状況にはすでにあてはまらないようになっているとしても、忘れられてはならないなにかを意味しているように思えます。3
一方で、リアドとアブダラーという完全にフィクションの登場人物の物語が、現代のアルジェを舞台に語られます。リアドはパリの大学生で労働実習先を探していたところ、父からの提案で、今は国立図書館の別館になっている『真の富』元書店を閉鎖して全てを処分する仕事をひきうけることになりました。そこを買った人がドーナツ屋を開くためです。4彼が誰ひとり知らない土地で出会ったのは、1997年からそれまで『真の富』を守ってきたアブダラーです。もちろんアブダラーも町の人々も『真の富』に深い愛着をもっているので、リアドの仕事に協力的ではありませんが、リアドを温かく迎えます。それまで読書を毛嫌いしていたリアドが、その町の人々との交流のなかで、人々の記憶の中に生きる『真の富』と本のもつ意味に気づいていきます。
とはいえ、この二人の登場人物は、ひどく個性的な人物でもなく、むしろ読者があまり驚きをもたずに受け入れられる人々です。リアドはありふれた現代の若者で、大学の卒業に必要な実習先がみつからず、あせっていたところで見つけた短い期間に古い書店を片付けるという任務に特別な思い入れは一切ありません。本には興味がないし、父親のメールにある「人はそれを失って初めて自分たちの豊かさに気づくものだ」、「あそこではいつもべニェ(ドーナツ)一個は本一冊よりも価値がある」5という辛辣な言葉に共感をしめすわけでもなく、ただ仕方なく面倒な仕事にとりかかります。アブダラーは、20年間、この書店/図書館の職員を忠実に務めてきた人物で、以前は字も読めなかった自分がこの仕事をすることに誇りをもっています。彼は実際『真の富』のもつ価値をよく理解していて、閉鎖になると聞くと、(既に引退の年はとうに過ぎているにもかかわらず)役所に行って激しく抗議します。昔かたぎの、実直で自分の信念に正直で不器用な男(「人が自分の感情を口にしない時代に、口にしない国で育った男」6)ですが、かといってリアドに敵対するわけでもなく、作業の行方を静かに見守って、リアドにいろいろな書店や町にまつわる話をしてやります。アブダラーがリアドに直接影響を与えたのは間違いないでしょう。それでも、それは慎しい人々が若い人々に与える「人生の教え」に似たものにも思われます。
この二人の登場人物を、シャルロのような特別な資質を持った人物の対比として持ってきたことは、読者の視点を取り込む小説の構成としても非常に効果的であったと考えられます。しかし、著者はそれだけでなく、1930年から1960年までのアルジェリアとフランスの間の問題、つまりこの小説の背景として欠かせない歴史的状況を並行して描きます。それは、著者自身が語るように、この作品は、シャルロという編集者への敬意を表すためだけでなく、『真の富』書店があった(現実にはまだある)場所の重要性、地中海精神が体現された場所の象徴的な意味を読者が理解するように意図された構造であるようです。シャルロの偉業、リアドが気づいた『真の富』の意味は、この歴史的な背景を知ることによってこそ、より深く理解されるのでしょう。
この作品は、エドモン・シャルロの業績を知り、複数の角度からその遺産の意味を問うということに読者をいざないます。それぞれの視点から作品を味わうことができるのですが、最終章にあるアブダラーの思いは、誰の心にも印象深く残るものではないでしょうか。
「人は本当はその場所に住むのではなく、場所が人に住むのだ」7
今、自分がどこにいるのか、どこに行くのかを模索している若い読者にこの言葉が訴えるものがあるからこそ、この作品が2017年の「高校生のルノドー賞」を受賞したのではないかと想像します。皆さんは、この言葉に思い当たることがあるでしょうか。