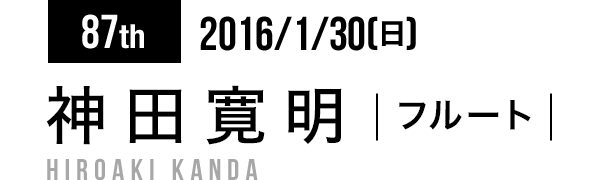今回の楽員インタビューは、1994年に入団、1995年から1年間ウィーン国立音楽大学に留学、1999年からフルートの首席という重責を担う神田寛明(かんだ ひろあき)さん。
先ずは、トレードマークの木製の楽器について伺いました。

神田さんというと、"黒い木の楽器"というイメージがあります。
「フルートという楽器は、いろいろな材料から作られてきました。木や象牙、昔は、動物や人間の骨も。今から約150年前に、楽器を大量生産するために大改良、金属製になりました。最近では、プラスチックやセラミックもあります。
実は、この木製の楽器は一見古そうに見えて、新たに開発された最新型なんです。どんな時代の音楽にも対応できますし、ソロ、室内楽、オーケストラ、全ての演奏活動を、これ一本で出来ると言っても過言ではありません。結構、大きい音が出ます。もともとは、他の人と違うことをしたいなと思って木の楽器にしました。目立ちますしね。」
オーケストラにおけるフルートの役割は。
「やっぱり、"花形"ですね。みんなが頼りにする主役は、トランペットなどかもしれませんが、"華のあるアイドル"と言ったところでしょうか。」
フルートとの出会いは、小学校3年生のクリスマスとか。
「はじめはクラリネットがほしくて楽器屋さんに行ったのですが、重くて、音が出なかった。その代り、フルートは、ちゃんと音が出ましたし、ちょっと(お値段も)安かった。」

ご両親思いですね。
「でも、その選択は間違っていなかった。後悔はしていません。
最初に個人レッスンについた先生のすすめで、神奈川県青少年交響楽団という、小学生から大学生までが一緒に演奏するオーケストラに入りました。上手に演奏するよりも、きちんとした社会集団生活を身につけるという教育でした。モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトを何度も演奏しましたので、音楽の基礎はここで学びました。」
(N響に入ってから)ウィーンに留学されます。
「ウィーン・フィルのヴォルフガング・シュルツ先生は、ソロ、室内楽、オーケストラ、 全ての演奏活動をされる、当時としては唯一のフルート奏者でした。どれも、自分もやりたいと思っていましたので、先生の生き方そのものに憧れました。それで、ウィーンに行って毎週レッスンを受けましたが、それよりも何よりも大きな収穫は、ウィーン・フィルや国立歌劇場で先生が実際に吹いている姿に沢山接したことです。当時のウィーン・フィルのフルート奏者の中でも一番輝いていた、まさにスターでした。グルベローヴァの「ルチア」、先生のあのオブリガートは、もう本当に凄かった。」
指揮者との思い出は。
「何と言っても、サヴァリッシュ先生ですね。指揮のテクニックがこれ以上の人は見たことがない。やはり、指揮者は指揮棒で全てを語らないと。ため息が出る様な美しい棒、あまりに完璧すぎて、演奏する方はちょっとくたびれてしまうこともあります。先生との最後の共演(になってしまった)は、確か、2004年11月定期での「ベートーヴェン7番」。先生が指揮台から舞台袖に帰る時に、日本語で『さようなら』と仰ったことが忘れられません。先生は、これが最後になると分かっていらしたのでしょう。」
パーヴォ・ヤルヴィが新しく首席指揮者に就任しました。
「非常に期待しています。サヴァリッシュ先生のような巨匠がオーケストラに何かを与えてくれるのではなく、お互い同じような世代ですから、新しく一緒につくっていこう。われわれが、どのような方向にもっていくのか、一緒に何をつくるのかが課題ですね。」
今回のメイン、ストラヴィンスキーの「春の祭典」について。
「学生の頃は、憧れもあって、スコア(総譜)を買ってきては、最後のところはどうなっているのかなあと図形を見ては感激したり、変拍子を一生懸命練習したりしました。フルートの5つのパートを、ピッコロも含めて全て吹いたことがあります。アルトフルートも面白いですよ。今回のオーチャード定期では中村淳二君がアルトを吹きます。皆様どうぞ御期待下さい。」
ありがとうございました。