| 第28回 2004年3月11日(木)19:00開演 |
チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ロドリーゴ:アランフエスの協奏曲
メンデルスゾーン:交響曲第4番イ長調「イタリア」op.90 |
指揮:尾高忠明
ギター:木村大 |
 |
 |
| 指揮:尾高忠明 |
ギター:木村大 |
|
| 【曲目解説】山田治生 |
本日は、現在、札幌交響楽団のミュージック・アドバイザー/常任指揮者として活躍する尾高忠明さんの登場です。尾高さんとN響との結びつきは古く、尾高さんがまだ桐朋学園大学の学生だった1968年にさかのぼるといいます。尾高さんはN響の指揮研究員となり、マタチッチやカイルベルトなどの大指揮者のもとで薫陶を受けたのでした。71年にN響デビュー。その後の、東京フィルや読売日本交響楽団、あるいは、イギリスのBBCウェールズ交響楽団での活躍は、みなさんご存じの通りです。N響からの信頼も熱く、最近では、この2月にケガのために来日不可能となったローレンス・フォスター氏に代わって、急遽、定期公演でブラームスの交響曲第3番と第1番を指揮しました。
チャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」とメンデルスゾーンの「イタリア交響曲」との共通点は、“イタリアへの憧れ”ではないでしょうか。「ロメオとジュリエット」の舞台はイタリアのヴェローナです。ロシアのチャイコフスキーは、「ロメオとジュリエット」を音楽にするにあたって、ヴェローナの古い街並みやイタリアの濃密な夜を思い浮かべたに違いありません。メンデルスゾーンの「イタリア交響曲」は、彼のイタリア旅行の思い出が基になっています。北方のロシア人やドイツ人が描くイタリアを舞台とした音楽は劇的で鮮明です。
真ん中に演奏される「アランフエスの協奏曲」はスペイン人によるスペインの音楽。ギターの盛んなスペインらしい作品です。古くから栄えたスペインの気品も感じられます。ギター界のホープ、木村大さんは、スペインでの演奏経験も多く、スペインのオーケストラとも「アランフエス」を録音しています。ロンドン留学を終えたばかりの彼が、どんな成長振りを聴かせてくれるのかとても楽しみです。
|
| ◆チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」 |
チャイコフスキー(1840〜93)の幻想序曲「ロメオとジュリエット」は、彼の初期の代表作の一つである。1866年に交響曲第1番「冬の日の幻想」を書き上げたチャイコフスキーは、1869年、「ロシア5人組」の中心人物であるバラキレフの勧めを受けて、シェイクスピアの戯曲「ロメオとジュリエット」を題材とした作品に取り組んだ。
「ロメオとジュリエット」のストーリーは周知の通りだが、念のために確認しておこう。舞台はイタリアのヴェローナ。モンタギュー家とキャピュレット家は対立し憎しみ合っている。しかし、モンタギュー家のロメオとキャピュレット家のジュリエットは恋におちてしまう。二人は両家の者たちの目を盗んで逢い引きする。ところが、ロメオがタイボルトを刺殺してしまったために追放を言い渡される。ジュリエットはローレンス神父から仮死状態になる薬をもらい、死んだふりをして逃亡を図る。仮死状態のジュリエットを見たロメオは彼女が死んだものと思い、絶望して自殺する。そこで目を覚ましたジュリエットも命を絶つしかない。そして二人の若者の死を契機に両家は和解する。
チャイコフスキーの幻想序曲は、ソナタ形式に基づきながらも、「ロメオとジュリエット」の本質を見事に再現している。
まず、クラリネットとファゴットで始まる荘重な導入部が昔々ヴェローナで起きた二人の若者の悲劇を思い起こさせる。そして、アレグロの主部には入り、まるで戦闘のような激しい第1主題がモンタギュー家とキャピュレット家の対立を描く。イングリッシュ・ホルンとヴィオラによって奏で始められる優しい第2主題は、ロメオとジュリエットの愛のテーマ。二人の夜の音楽。甘美な旋律がジュリエットであり、それに応えるホルンがロメオであろうか。そして再び、激しい闘いの音楽(第1主題)。それでも二人の愛は絶望的に燃え盛る(第2主題)。しかし最後に、両家の憎悪(第1主題)が二人の愛(第2主題)を暴力的に引き裂く。二人は命を絶ち、葬送のようなティンパニの連打となる。その後、音楽は浄化される。ハープの柔らかい響きにのって、二人があの世で結ばれ、両家も和解を遂げる。
1870年、モスクワで初演されたが、その後、チャイコフスキーは大きな改訂を加え、1880年に現在演奏されている決定稿が完成した。 |
| ◆ロドリーゴ:アランフェスの協奏曲 |
ギター協奏曲のなかで最も有名な作品は、「アランフエスの協奏曲」だろう。アランフエスは、スペインの首都マドリード近郊にある緑に恵まれたオアシス。かつて王室の離宮があり、今は美しい庭園が観光名所となっている。
「アランフエスの協奏曲」を書いたロドリーゴ(1901〜99)は、20世紀のスペインを代表する作曲家の一人。幼児期に悪性ジフテリアのために失明したが、バレンシア音楽院でピアノや作曲を学び、パリではデュカスに師事した。夫人とともにアランフエスを訪れたロドリーゴは、景色を目で見ることはできなかったが、強い印象を受けたという。そして彼は、遠い昔に思いを馳せ、民衆の音楽とかつての王室の典雅さとを結びつけた「アランフエスの協奏曲」を1939年に作曲した。翌1940年に初演された「アランフエスの協奏曲」は、内戦に傷ついたスペインの人々の心を癒し、ロドリーゴの代表作となっていった。
第1楽章:アレグロ・コン・スピリト。ギターによる、6/8拍子に3/4拍子がはさまる特徴的なリズムで始まる。スペインの民族的な舞踏のステップだ。第1主題は、第1ヴァイオリンとオーボエによって明るく歌われ、ギターが受け継ぐ。第2主題はギターが軽快に提示。独奏チェロが第1主題を短調で奏でると、哀愁が漂う。
第2楽章:アダージョ。この協奏曲のなかで最も知られている楽章。そのロマンティックで美しい旋律はポピュラー音楽にまでアレンジされている。始め、ギターの伴奏に乗ってイングリッシュ・ホルンが感動的な旋律を歌い始め、ギターがそれを装飾を交えて繰り返す。この旋律が様々に姿を変えて奏でられ、遂にギターの幻想的なカデンツァとなる(全曲中の一番の聴きどころと言っていいだろう)。そしてオーケストラが最強音で哀愁の旋律を歌い上げる。その後、音楽は静まり、余韻を残しながら楽章を終える。
第3楽章:アレグロ・ジェンティーレ。第2楽章とは対照的な快活な音楽。始めにギターが2/4拍子と3/4拍子を組み合わせた軽快なロンド主題を奏でる。スペインの民族舞踊のステップを思わせる。このロンド主題は、4つのエピソードをはさみながら、何度も現れる。
|
| ◆メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 作品90 「イタリア」 |
メンデルスゾーン(1809〜47)の交響曲の番号は、その作品の成立の順番とは異なっている。彼の交響曲を作曲年順に並べると、交響曲第1番(1824年)、交響曲第5番「宗教改革」(1830年)、交響曲第4番「イタリア」(1831〜33年)、交響曲第2番「賛歌」(1840年)、交響曲第3番「スコットランド」(1830、42年)ということになる。「イタリア」と「宗教改革」が作曲者の死後に出版されたことから、こんなにややこしいことになってしまったのである。これらの交響曲の前に早熟の天才メンデルスゾーンは、13曲の「弦楽のための交響曲」(1821〜22年、つまり12〜14歳の頃だ)を残している。「イタリア」は交響曲第4番という大きな数字が付けられているが、実際はメンデルスゾーンが二十歳を過ぎた頃の作品だ。若々しい感情が弾けている。
メンデルスゾーンは、ユダヤ系の裕福な銀行家の息子として、ハンブルクに生まれた。ベルリン大学で学び、1829年から31年にかけて、イギリスやイタリアを旅行した。特に1830年10月から31年4月にかけては、約半年の間、ローマに滞在した。このローマやイタリアで見聞きしたものからインスパイアを受けて作曲し始めたのが、「イタリア交響曲」であった。ベルリンに帰ったメンデルスゾーンは、ちょうど1832年にロンドンのフィルハーモニック協会から作曲依頼を受け、翌年、「イタリア交響曲」を完成させた。1833年5月にロンドンで初演されたが、メンデルスゾーンは自分の作品に満足できず、改訂を加えた。結局、改訂版(現行版)が出版されたのは作曲者の死後の1851年のことである。「イタリア交響曲」は、何か特定のイタリアの風物を描写するものではないが、第4楽章でイタリアの舞曲の一つであるサルタレッロが用いられてるところに、メンデルスゾーンのイタリアでの思い出が刻印されている。
第1楽章:アレグロ・ヴィヴァーチェ。木管楽器の弾むような刻みに乗って、ヴァイオリンが輝くような第1主題を奏でる。その明るさはまさにイタリアの青空や陽光をイメージさせる。柔和な第2主題はクラリネットやファゴットなどの木管楽器で奏でられる。その後、ヴァイオリンに弾むような短調の主題が現れ、対位法的な展開となる。
第2楽章:アンダンテ・コン・モート。明るい第1楽章とは対照的な翳りのある音楽。低弦楽器の重々しい足どりに乗って、オーボエ、ファゴット、ヴィオラが哀愁を帯びた旋律を歌い始める。それはヴァイオリンに受け継がれる。クラリネットやフルートによる柔和な音楽がはさまれる驕B
第3楽章:コン・モート・モデラート。メヌエット的な性格を持つ典雅な3拍子の音楽。中間部は何かの合図のようなホルンの吹奏。
第4楽章:サルタレッロ、プレスト。速く激しい短調の音楽。舞踊音楽のような楽章。サルタレッロのリズムのほか、ナポリ舞曲のタランテラも現れ、熱狂的なステップが果てしなく続く。 |
|
|
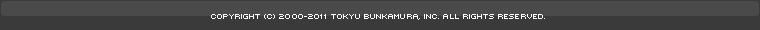 |
|