| 第26回 2003年9月23日(火・祝)15:30開演 |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調〜アダージェット
モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299(297C)
ブラームス:交響曲第4番ホ短調op.98 |
指揮:ハインツ・ワルベルク
フルート:工藤重典
ハープ:早川りさこ |
 |
 |
 |
| 指揮:ハインツ・ワルベルク |
フルート:工藤重典 |
ハープ:早川りさこ |
|
| 【曲目解説】山田治生 |
ドイツの名指揮者、ハインツ・ワルベルクは、今年の3月で80歳になりました。いくら指揮者が平均年齢の高い職業といっても、80歳を超えて現役で国際的に活躍しているマエストロはほとんどいません。1913年生まれのジャン・フルネは別格としても、あとは、1923年生まれのウォルフガング・サヴァリッシュと同年生まれのスタニスラフ・スクロヴァチェフスキくらいでしょうか(二人ともN響と関係の深い指揮者です)。
ワルベルクは、1923年、ドイツのハムに生まれ、ドルトムントで学んだ後、アウグスブルク、ブレーメン、ヴィースバーデン、エッセンなどの歌劇場の音楽監督を歴任しました。ウィーン国立歌劇場の常連指揮者としても活躍。また、ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団の首席指揮者も務めました。
ワルベルクとN響との結びつきは古く、1966年以来共演を重ねています。地方公演を入れると、N響の演奏会をなんと150回近くも指揮しています。ドイツ=オーストリア音楽を得意とし、N響とともに、ベートーヴェン(亡くなった朝比奈隆の代わりに指揮した2002年6月の交響曲第1番と第3番、2001年の「第九」などが記憶に新しい)、ブラームス(96年3月の交響曲第2番)、ブルックナー(96年3月の交響曲第9番)などの名演を残
してきました。本日も、マーラー、モーツァルト、ブラームスという、マエストロの十八番であるドイツ=オーストリア音楽が取り上げられます。ドイツ正統派の巨匠の至芸が堪能できることでしょう。 |
| ◆マーラー:交響曲第5番より「アダージェット」 |
マーラー(1860〜1911)の交響曲第5番第4楽章「アダージェット」は、弦楽器とハープだけで演奏される10分ほどの音楽である。ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画「ヴェニスに死す」(1971年)に用いられ、その甘美で陶酔的な音楽が映像とうまくマッチし、観客に強い印象を残した。
マーラーが交響曲第5番の作曲を始めたのは1901年。当時、ウィーン宮廷歌劇場の総監督であった彼は、超一流のスター指揮者であった。その年の11月、マーラーは、後に妻となるアルマ・シントラーと出会う。アルマは宮廷画家エーミール・シントラーの娘であり、自らはツェムリンスキーに作曲を師事していた。マーラーは41歳、アルマは22歳。二人は恋に落ち、急速に恋愛関係が発展。同年12月に婚約し、翌1902年3月に結婚した。そしてその年の夏の休暇にマーラーは交響曲第5番を完成させた。
マーラーと親交のあった指揮者メンゲルベルクによると「このアダージェットは、グスタフ・マーラーの、アルマにあてた愛の証であった」という。マーラーは、ラブ・レターの代わりに、何の言葉も書き添えずにアダージェットの手稿をアルマに送ったのであった。
この楽章は三部形式によっている。ハープの分散和音に導かれて、ヴァイオリンがメランコリックな旋律を歌い始める。これはチェロに受け継がれる。その後、大きな高揚を経て、中間部へと入っていく。さまようような転調を繰り返し、ヴァイオリンが新たな旋律を歌う。このあたりは弦楽器のみ演奏される。ハープの再登場で中間部が終わり、主部が再現される。そして最後の大きな高揚のあと、音楽は衰微し、余韻とともに終わる。 |
| ◆モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299(297C) |
1777年にザルツブルクの大司教と衝突したモーツァルト(1756〜1791)は、ザルツブルクを去り、ミュンヘン、マンハイムを経て、1778年3月、パリにたどり着いた。しかし、パリの人々は、22歳になったモーツァルトを、かつて神童としてもてはやしたようには迎え入れなかった。そのためモーツァルトは自分で職を探さなければならなかった。漸く、彼はフランスの外交官ド・ギーヌ公爵の令嬢に作曲を教えるという仕事を得る。令嬢は、作曲はそれほど得意ではなかったが、ハープを上手に弾いた。また、ド・ギーヌ公爵もフルートの名手であった。そこでモーツァルトはこの父娘のためにフルートとハープを独奏楽器とする協奏曲を書いた。それがこのフルートとハープのための協奏曲である。18世紀のパリのサロン音楽を思い起こさせる優美な作品だ。なお、複数の楽器のための協奏曲という形式は、当時のパリで「協奏交響曲」として人気があった。
第1楽章:アレグロ。ソナタ形式。まずはじめに全奏で快活な第1主題が提示される。そのあとエレガントな第2主題がヴァイオリンに現れる。そしてフルートとハープが第1主題を奏で、両楽器の華やかなアンサンブルが始まる。最後にフルートとハープだけのカデンツァが入る。
第2楽章:アンダンティーノ。展開部を欠いたソナタ形式。ゆったりと歩むような音楽。冒頭の第1主題は高貴であたたかみがある。第2主題は弦楽器の8分音符の伴奏にのってフルートが歌う多少動きのある音楽。そしてハープが繰り返す。この楽章も最後にカデンツァが用意されている。
第3楽章:ロンド、アレグロ。ロンド形式。フルートとハープの華麗でスリリングな掛け合いが聴ける。まず、オーケストラがロンド主題を演奏した後、ハープが躍動的な主題を奏で始める。そしてフルートが繰り返す。次の主題はフルートが先。その後、フルートとハープによってロンド主題が再現される。最後はカデンツァを経て、華麗に締め括られる。 |
| ◆ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98 |
ブラームス(1833〜1897)にとって最後の交響曲にあたる交響曲第4番は、1884年の夏に作曲を開始され、翌1885年の夏に書き上げられた。同年10月25日に作曲者自身の指揮するマイニンゲン宮廷管弦楽団によって行われた初演は、大きな成功を収めたといわれている。50歳を超えたブラームスの諦念と情熱が円熟の筆致で描かれた傑作である。
ブラームスは、リストやワーグナーなどの大掛かりな音楽がもてはやされた後期ロマン派の時代にありながらも、自身は伝統的で懐古的な創作のスタンスを取り続けた。たとえば、4つの交響曲では、ベートーヴェンの時代とほぼ同じ楽器編成(2管編成)が用いらている(したがって、同時代の他の作曲家たちの管弦楽曲に比べると響きがかなり渋い)。ブラームスの交響曲第4番とほぼ同じ時期に書かれていたマーラーの交響曲第1番「巨人」が4管編成、ホルン7本、多数の打楽器、ハープなどを要するのと比べたとき、ブラームスの伝統的で保守的な(ある種、禁欲的な)姿勢がわかるだろう。本日演奏される交響曲第4番は、第2楽章に古い教会音楽で使われた音階であるフリギア旋法が用いられたり、第4楽章にバロック時代に盛んだったパッサカリアという変奏曲の技法が取り入れられたり、ブラームスの懐古的な特徴が目立つ作品である。フリギア旋法とは、中世やルネサンス時代に用いられた教会旋法の一つ(ミで始まる音階)。パッサカリアとは、シャコンヌと同じ性格をもつバロック時代に流行した舞曲の一つで、短い主題の低声部が繰り返され、その上で音楽が変奏されていく形式。
バロック音楽や古典派音楽などの研究を通して、その成果を創作に活かしていたブラームスの作曲の特徴がこの交響曲にはよく表れている。しかし、ブラームスの作品は必ずしも「古風」で「反動的」な音楽とは言い切れない。20世紀になって後期ロマン派が行き詰まり、新古典主義が現れてきたことを考えると、ブラームスの過去の音楽に目を向けながら新しいものを生み出していく創作姿勢は、むしろ、時代を先取りするものであったとも言えるかもしれない。
第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ。ソナタ形式。冒頭、ヴァイオリンが哀愁を帯びた第1主題を奏でる。第2主題は対照的に勇壮なもの。木管楽器が特徴的なリズムを強奏したあと、チェロとホルンが情熱的に歌う。
第2楽章:アンダンテ・モデラート。展開部を欠いたソナタ形式。まずホルンと木管楽器がフリギア旋法に基づく旋律を吹奏し、クラリネットとピッツィカートのヴァイオリンがやはりフリギア旋法による第1主題を奏でる。第2主題はチェロによって広々と歌われる。
第3楽章:アレグロ・ジョコーゾ。2拍子でかかれているが、スケルツォ的な性格をもっている。ソナタ形式。ブラームスの交響曲としては、トライアングルが用いられている唯一の楽章。全奏による力強い第1主題で始まる。第2主題はヴァイオリンが伸びやかに歌う。
第4楽章:アレグロ・エネルジーコ・エ・パッショナート。パッサカリアの形式が用いられ、8小節の主題と8小節ずつの30の変奏と結尾からなる。全体は、変奏曲の形式をとりながらも、ソナタ形式的な構造ももっている。まず始めに管楽器で主題が提示される。そのあと第11変奏まではソナタ形式の提示部に相当する。フルートの活躍する第12変奏から展開部的な性格を持つ。トロンボーンやホルンがコラール風の音楽を奏でる第14、15変奏をへて、第16変奏で元のホ短調に戻る。第23変奏から第25変奏までの高揚を経て、一旦おさまった後、力強い結尾で締め括られる。 |
|
|
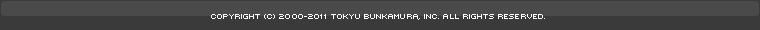 |
|