
2014/10/18(土)-12/14(日)
Bunkamuraザ・ミュージアム
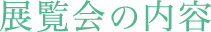
第一次世界大戦前の繁栄を謳歌していた頃のフランスでは、美術の全く異なるふたつの切り口が顔を合わせていました。
印象派とエコール・ド・パリです。両者の背景として共通するのは、フランスの繁栄と社会の一応の安定があり、画家たちは自らの感性に忠実にそのおのおのの目標に向かって邁進したことでした。そしてそれはいわば夢の実現でもあったのです。
日本人が抱くフランスへの憧れの源泉には、おそらくこの国が長年にわたり文化芸術をリードしてきたことがあるでしょう。その象徴が「芸術の都パリ」の存在であり、絵画作品はその結晶なのです。日本の個人コレクションで構成される本展は、日本人にとって最もフランス的なるものである絵画を通じての日本人からフランスへのオマージュであるとともに、それを描いた画家たちの一人ひとりの夢を追体験する試みといえるでしょう。

1860年代後半、パリのカフェ・ゲルボワに集った若手の画家達は、伝統的な美学から離れ、新しい絵画の創造を目指していました。やがて彼らはキャンヴァスを戸外に持ち出し、目に見える風景を写しとり始めます。それはまた、事物に降り注ぐ太陽の光を捉える試みでもありました。揺らぐ輪郭と踊る原色によって、自然のうつろう美しさを表現した印象派の誕生です。
セザンヌは故郷の風景に現れる形や構図を幾何学的に捉え、その再構成を試みました。モネは風景が刻一刻と変化していく様子を、すばやい筆遣いと豊富な色彩で描きとめました。ルノワールは彼をとりまく人々に愛情深いまなざしを注ぎました。彼が描いたのは生きる喜びを内側から発散させるような幸福な人物像ばかりでした。
フランスの牧歌的風景、都会のきらめき、そして若き芸術家たちが新たな絵画の創造を追い求めたこの時代の空気は、今もなお新鮮な輝きをもって絵画の中から語りかけています。

20世紀に入って、印象派の画家たちの新しさが理解されるようになり、次いで古典的な過去の作品が新たな文脈で評価されはじめると、若い画家たちは、それをふまえてさらなる表現の革新を求めるようになりました。原色を使い筆触を際立たせる描き方で、目に見える以上のものを表現しようとするフォーヴィスムや、現実にある事物を見て描くアプローチそのものに根本的に挑んだキュビスムの動きがそれです。
同じ関心から出発したために、当初彼らの作品は互いに似かよっていましたが、1920年代になると、各々独自の作風を確立することとなります。また、両大戦間の社会の状況は、フランス人画家である彼らに、古典に回帰してフランス美術の偉大な伝統に連なることを期待しました。彼らはそうした期待に応え、フランス国内だけでなくアメリカ、そして日本へと広がった市場でも人気を得て、第二次大戦後に至るまで存在感を示し続けました。

第一次大戦後のフランスは人間性の回復、そして芸術の伝統の復興をとなえ、戦争の惨禍からの立ち直りを図ります。首都のパリには、大戦前にもまして多くの外国人芸術家が集い、モンマルトルやモンパルナスを舞台に個々の創作を展開していきました。当時のパリの街角は、ユトリロが哀愁漂う風景画として作品に残しました。イタリア出身のモディリアーニが描いた裸婦は、単純化された形態の中に人の生にまつわる哀歓をしのばせています。ポーランド人のキスリングは、なめらかな質感と鮮やかな色彩で、対象の存在そのものを極立たせ、肯定するような様式を確立しました。また、ロシア系ユダヤ人のシャガールは、故郷の風景につながる幻想的な光景に、豊かな色彩をちりばめました。
一方で、日本の繊細な感覚を西洋の肖像画に見事に織りこんだ藤田嗣治も、ユニークな様式を確立した一人です。