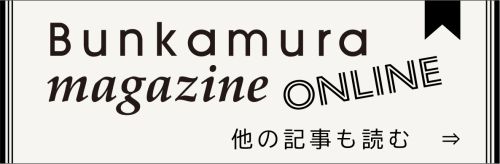能楽(ビギナーのための鑑賞ガイド⑤)
コンサートホールや劇場で生のコンサートやお芝居を体験してみたいけど、分からないことが多く、何となく敷居の高さを感じてしまう…。そうした不安を払拭して最初の一歩を踏み出すきっかけになるよう、初めて文化芸術を楽しむための入門知識をまとめた初心者向け企画「Start!Bunka ビギナーのための鑑賞ガイド」。第5回は能楽を楽しむコツや鑑賞時の基本的なマナーをご紹介します。
能楽の魅力とは?鑑賞作品を選ぶポイントは?
能楽は、室町時代から600年以上演じて受け継がれてきた日本を代表する伝統芸能。音楽(謡と囃子)と舞踊を中心に物語を展開する舞台芸術で、「能」と「狂言」からなります。能楽を上演する「能楽堂」は、伝統芸能の専用劇場ならではのおごそかな緊張感がありつつ、リラックスした状態で自然と背が伸びる寺社に似た空気が漂っています。そんな日常とは別世界の空間において、圧倒的な存在感をまとったシテ方(主役を演じる役者)が謡(台詞や歌)に乗せて型を舞う様は、まさに一切の無駄を削ぎ落とした様式美の極致。たとえ謡や舞の意味が分からなくても、その独特の世界にただ身を委ねているだけで、あわただしく過ぎていく情報過多な日常で失いがちな心の安らぎや落ち着きを取り戻すことができます。
現在上演されている能の演目は250番ほどあり、神様が優雅に舞う神話の世界や、亡霊となった武士や女性がこの世に現れる話などさまざまなジャンルがあります。数ある演目の中から鑑賞作品を選ぶ際は、穏やかな雰囲気のもの、あるいは逆に動きの激しいものなど、自分が好きなテイストを選ぶと能の世界にスッと入り込みやすくなるはず。また、昔から語り継がれている有名な伝説や歴史上の人物をテーマにした演目だと、内容が分かりやすいぶん「理解しよう」と意識しなくなり、能の大きな魅力である謡や舞に集中して堪能しやすくなるでしょう。
一方、同じ舞台で能と交互に演じられる狂言は、中世の庶民の日常生活を明るく描き出す台詞劇。260番ほどある演目は笑いを中心としたものが多く、登場人物も動物やキノコの精など人間以外のキャラクターが出て来るなど、見た目にも分かりやすく初心者でも楽しみやすいのが特徴的。心が和む上質なユーモアに思わず笑みがこぼれることでしょう。
能楽堂での座席の選び方と作品を楽しむコツは?
能楽堂の見所(観客席のこと)の座席は、エリアによって「正面」「脇正面」「中正面」の3種類に分かれています。「正面」は舞台の真正面から、橋掛かりと呼ばれる通路に近い「脇正面」は舞台の真横から、そして「中正面」は舞台の斜めから観ることになります。それぞれ見え方が大きく異なるので、どの方向から鑑賞したいかじっくり考えてから選ぶとよいでしょう。
能楽を楽しむコツとして、事前に公演チラシやインターネットで演目の簡単なあらすじや見どころだけでも目を通しておきましょう。それだけでもストーリーの理解に意識を取られず舞台に集中しやすくなるはずです。舞台の内容すべてを正しく理解しようと張りきりすぎると逆に難しく感じられるので、華麗な装束や舞の見事さといった何か一つでも素敵に思えるものを見つけ、独特の世界観に浸るというスタンスでも最初のうちは十分。そうした理屈に縛られない鑑賞スタイルによって、演者がほんの少しの動きや表情で見せる感情も感じ取りやすくなるでしょう。能楽師が初めに演目について解説したり、スマートフォンやタブレットにアプリをダウンロードすると演能に合わせて解説が表示される字幕サービス対応の公演もあるので、ビギナーにおすすめです。
また、会場へのアクセス・経路・所要時間なども事前に調べておくと、当日に心の余裕を持って鑑賞に臨みやすくなるでしょう。
能楽堂での鑑賞マナーは?どんな服装で行けばいい?
能楽堂では客席内での飲食、撮影・録音・録画は禁止。能舞台は静けさをよしとするので、携帯電話・アラーム付き時計など音の出る電子機器の電源は切っておき、上演中に音を立てたりむやみに離着席するのは控えましょう。カバンや袋を開けたりする音も、自分が思っている以上に周りのお客様には聴こえてしまうものです。補聴器をお使いの方は、開演前に正しく装着されているか確認することをおすすめします。
一方、感動を表現する拍手については、演者が退場する時に拍手が起きることもあれば、静かに余韻に浸るため誰も拍手しない場合もあり、一概にこれという決まりはありません。拍手のタイミングに困ったら、周囲の様子に応じて合わせるといいでしょう。なお、前のめりに座ると後方のお客様の視界をさえぎることになるので、座席の背もたれに背中を付けた状態で座りましょう。他にも分からないことや鑑賞中に困ったことがあれば、案内スタッフに相談してみると良いでしょう。
また、能楽堂には特別なドレスコードはありません。ショートパンツやサンダルなど過度にカジュアルでなければ、長時間座っても疲れないよう普段から着慣れた服装で大丈夫です。もちろん、日本の伝統芸能を装いからも楽しめるよう着物で鑑賞するのも一興でしょう。なお、周囲の方への配慮のため、帽子は開演中には脱いで、香りの強すぎる香水は避けた方がよいでしょう。
能楽堂で快適にお過ごしいただくために/チケット購入方法
能楽鑑賞に最低限必要なものはチケットですが、演者の表現や装束の細部まで見たい場合(特に座席が後方の場合)はオペラグラスも持参するといいでしょう。また、会場内の空調の寒暖の感じ方には個人差があるので、ショールやカーディガンなど軽く羽織って体温調整を行えるアイテムや、咳やくしゃみが出てしまう時に口元を押さえられるハンカチもあると便利です。
チケットは、おもに各プレイガイドや公演会場のチケットカウンターなどで販売されます。販売方法は公演によって異なるので、詳しくは主催者のホームページをご覧ください。Bunkamura主催公演では、オンラインチケットMY Bunkamuraをはじめ、Bunkamuraチケットセンター(電話)・東急シアターオーブ/Bunkamuraチケットカウンター(店頭)または各プレイガイドでのご購入、ご予約が可能です(詳細はBunkamuraチケットガイドでご確認ください。)。公演によっては学生向けのシートや料金を用意しているものもございますので、こちらも公演のホームページでご確認ください。