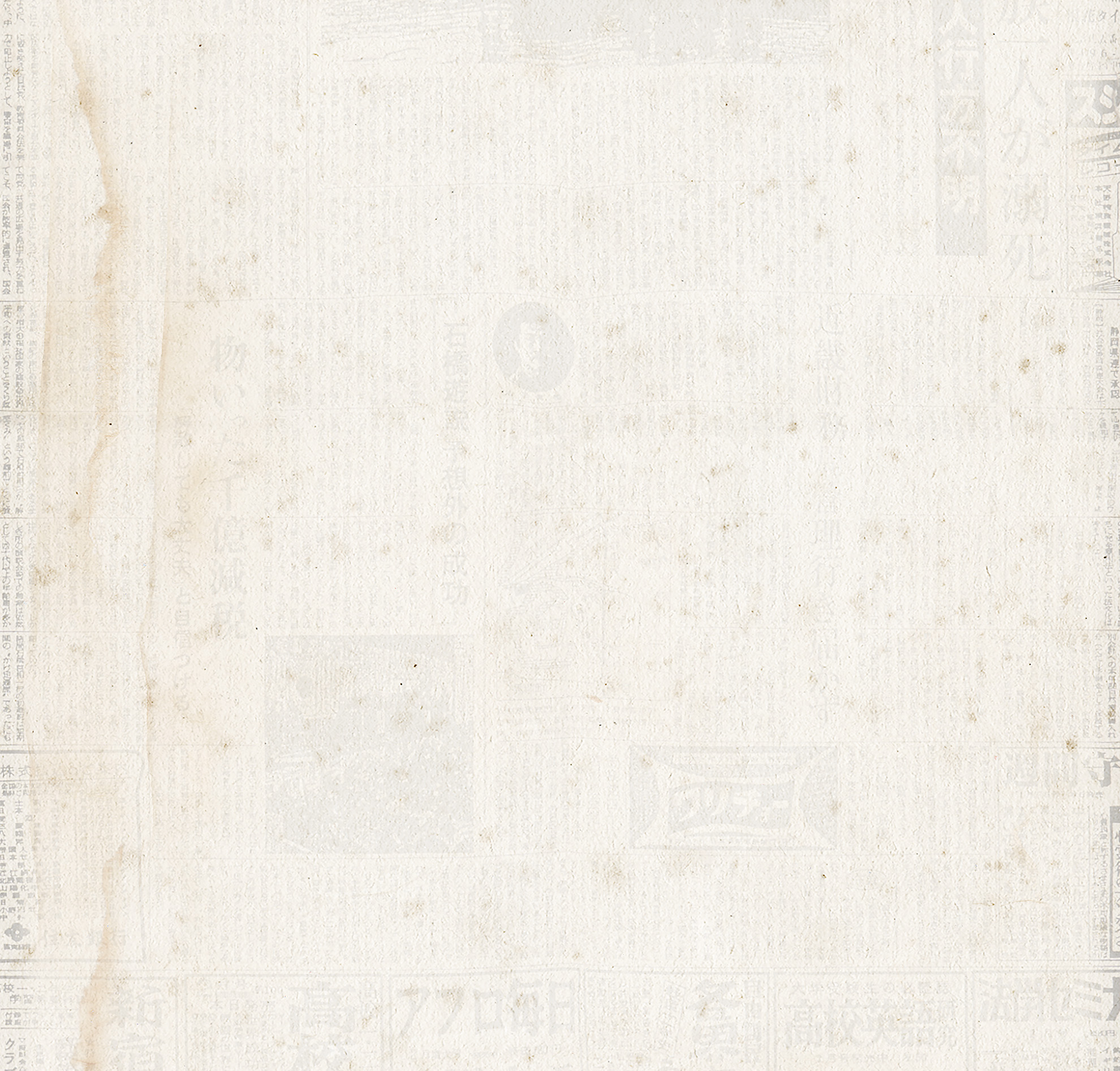トピックス
2025.09.05 UP
『アリババ』『愛の乞食』開幕レポート[舞台写真追加]
静の『アリババ』、動の『愛の乞食』
ロマンと冒険の海原が待っている

んんんんああああ〜なんだかわからんがめちゃめちゃ楽しかった! そんでワケもわからず泣けてくる! という、(個人的)唐作品“お約束”の生体反応にまた酔いしれた。テント公演はもとより、こうして劇場で唐十郎の芝居を観る時も「観劇」じゃなくて「体験」としか言いようがないのだが、やっぱりぶわわわと涙が溢れる瞬間に恍惚となってしまう。でも今回はなぜ熱い涙が湧いて来たのか、自分なりに答えはある。
初期唐戯曲の二本立て、しかもオール関西弁で、というインパクトのある企画はリスクも高かったはずだが、めくるめく唐戯曲の詩的なことばを愛する身にとっても、結果は「吉」と出たと思う。やわらかくてぬくもりのある関西弁が『アリババ』では封印していた夫婦の切ない記憶とこの世に存在できなかった子どもたちの哀しみをおくるみのように包みこみ、一転して『愛の乞食』では、しゃべくり漫才のようにスピード感ある関西弁の掛け合いが、荒唐無稽な冒険の旅へと力強くいざなってくれた。

前半の『アリババ』は、ちょっと夢見がちな夫と大らかな女房(肩が強い)という夫婦の物語だ。旦那の宿六さん(安田章大)の現実とも妄想ともつかない話を、「ほんで?」「ほんで?」と聞いてあげる貧子さん(壮一帆)のやさしさが、しっとりと温度のある歌声とともに沁みてくる。ギターの弾き語りも味わい深い安田が繊細に演じる宿六さんは、一見情けない旦那のようでいて感受性が強く、見知らぬ「ミドリのおばさん」にもちゃんと名前があることに憤る義侠心の持ち主だ。たまによからぬ“小道具”(取扱注意)の遊びも挟みつつ、この夫婦のやり取りがのほほんと心地いい。噛み合っているようでいない微妙なバランスで成り立つ夫婦の日常を掻き乱すのは、朗々と歌いながら突如現れる老人だ。扮する風間杜夫(東京・福岡のみ/大阪・愛知は金守珍)の融通無碍ぶりは言わずもがなで、この謎の老人が赤ん坊を抱いていることが物語の鍵を握っている。


なぜ老人は夫婦の前に現れたのか、なぜ貧子には長らくその姿が見えないのか。それは夫婦にとっての辛く悲しい記憶を、無意識にも封印してきたことと関係があるだろう。捨てられ、あるいはこの世に生まれることさえ出来なかった「命」たちの束の間の「母」となった貧子の姿はそのまま聖母にも見え、あり得たかもしれない幸せを思うと涙が滲んだ。宿六が待ち望んでいたのではない「赤い馬」とは何を示すのか、明確にはわからないけれど、夫婦の痛みを一身に引き受けようとする宿六の覚悟が胸を衝く幕切れだ。

静かに心揺さぶられる『アリババ』から休憩を挟んで『愛の乞食』の幕が開くと、ガラリと様相が変わる。なんせ公衆便所を舞台に元海賊たちが暴れ回るという、シュールすぎるシチュエーションだ。しかも登場するのはキャラ立ちまくりの人物ばかりで、唯一ごく普通に見えるのは、安田が演じるしがない保険屋の田口くらい。


ミドリのおばさんだけど実は元海賊(伊原剛志)とか、乱暴な刑事だけど実は元海賊コンビ(彦摩呂&福田転球)とか、その仲間だったらしい中国人(温水洋一)とか。とりわけ目を剥く登場シーンを見せてくれたのが伊東蒼演じる少女万寿シャゲで、思い切りのいい痛快な弾けっぷりに、そりゃ田口もそうなるよね!とニコニコしてしまう。摩訶不思議な唐ワールドにぴったりの変幻自在なヒロイン爆誕!を強烈に印象づけた。先ほどの「貧子さん」壮一帆は、こちらでは戦争に翻弄される悲劇の女として登場している。


気持ちいいほどコテコテな伊原を筆頭に、海賊仲間は舞台狭しと楽しげに暴れまわり、繰り広げる諍いもスケールが小さくて実に愛しい。と、いつしか時空は歪み、皆が待っているのはジョン・シルバーという名の一本足の男らしいことがわかってくる。え、時はいつ? 大正? 昭和? ん、満州??と頭に飛ぶハテナを追いかける暇もなく、現れたのは先ほどの冴えない田口とは似ても似つかぬ、安田演じる一本足の憲兵だ。
幻想の中、憲兵と万寿シャゲの場面は究極のラブシーンでもあり、愛と死の狭間で交わされるのっぴきならない言葉の一つひとつが、あまりにも切なく苦しく美しい。凛々しく女心を狂わせる魅力に溢れた安田の憲兵、脳天を貫くように悲痛で真情に満ちた伊東の稀有な「声」。このカタルシスに、こちらはもう涙腺崩壊である。
たとえ幻想から醒めても、万寿シャゲは田口をまたジョン・シルバーと海賊たちの世界へと連れ戻す。世知辛い現実を粛々と生きる私たちに足りないのは、愛とロマンと冒険に生きる海賊の心意気なのだと、なんだかものすごく勇気をもらった気がした。


というのが自分なりの「答え」ではあるのだが、唐戯曲を愛してやまない演出・金守珍の唐作品に対する態度はいつも、「誤読上等」なのである。ここに書いてあるようなことはまったく感じられなかった、何が何だかわからなかった、難しかった等々、自分が感じたことが「答え」でいいのだと、まずは自信を持っていただきたい。
だが、唐作品が内包する繊細な人の「痛み」と、エンタメ精神に溢れたスペクタクルを同居させる金演出は、今回も鮮やかに花を咲かせている。忘れられない一瞬のシーンや台詞を反芻するうちに、あれはこういうことだったのかも知れない、ああまた観たくなってきた……と思うようになったら、立派に唐十郎の沼に絡めとられたと言っていいだろう。そんな症状が現れたならば、素直にその欲求に従ってみることをおすすめする。

文:市川安紀
撮影:細野晋司