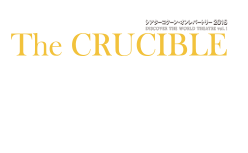2016.10.12 UP
ついに開幕!初日レポート!
人が生きる拠りどころ
『るつぼ』は怖い。でも身震いするほど面白い。幕切れの暗闇の中で、張りつめていた糸が一気にほどけ、ふーーーーっと大きく息を吐いた。休憩を挟んで正味3時間、観る側の集中力が途切れることはない。多層的な深さを持つアーサー・ミラーの傑作戯曲に、役者たちのほとばしる熱情を引き出したジョナサン・マンビィの演出、そこに美術、衣裳、振付、照明、音楽といった戯曲を立体化する構成要素が有機的にからみ合う。ずっしりと腹の底に響く見応えに、名作の名作たるゆえんを実感した。
17世紀アメリカで実際に起きた「魔女裁判」事件をモチーフにした作品だが、現代日本を生きる私たちも身につまされる危うさに満ちている。
きっかけは少女アビゲイル(黒木華)のジョン・プロクター(堤真一)に対する激しい執着だ。彼の妻エリザベス(松雪泰子)を呪い殺そうとする(こ、怖すぎる)まじないの儀式で仲間の少女たちと踊っているところを見とがめられ、アビゲイルは苦し紛れに人を魔女にでっちあげる。魔女はお前だろ、と心底ムカつきつつ、黒木の迫力が凄まじすぎて、芝居だとわかっていても震え上がってしまう。
堤プロクターの野性的な男らしさにアビゲイルたちが惹かれるのも無理はないが、家族に必要とされる夫であるべきか、真に自分の魂に恥じない選択をすべきか、最後まで葛藤する彼の苦しみが観る者に伝播する。迷いを押し殺し、夫の選択を受け入れるエリザベスの松雪が毅然として美しい。夫婦といえど個人であり、心の領域は不可侵であることを彼女は知っているのだ。二人の間に血が通い合う終幕に固唾をのむ。
マイク・ブリットンのシンプルかつ力強いセットは、天窓や壁面の小窓から差し込む光の加減で、変化に富んだ表情を見せる。その中で全4幕の転換を担うのは、アビゲイルが率いる少女たちだ。マンビィ演出は彼女たちをこの芝居の核としてとらえ、セイラムの大人たちを操っている構図を視覚的にも鮮明に見せる。少女たちの性の衝動や恐れを荒ぶる動きで表した黒田育世の振付は、少女の集団があたかも別の生き物のような鼓動を帯びてすばらしい。
背が高く、細く長く伸びた首すじが意志的な黒木に対して、彼女を告発しようと勇気を振り絞るメアリー・ウォレンを演じた岸井ゆきのの小柄さ。彼女が熱狂のるつぼに巻き込まれていく法廷シーンはほんとうに恐ろしい。瞬時にして潮目が変わり、激しく感情を揺さぶられる中で、岸井は実にリアルに少女の不可解さを体現している。そして自分がまいた火種が愛する男を取り返しのつかないところまで追い詰めてしまった黒木アビゲイルが、最後の刹那に見せる表情は必見だ。
皮肉なのは、熱血牧師ヘイル(溝端淳平)が、「女の子の悪ふざけでしょ」で済んだはずの魔女騒動に、信憑性というガソリンを注いでしまったこと。溝端は明瞭なセリフ回しで、神と正義への信頼と先走った使命感ゆえの挫折を熱を持って表現している。
多かれ少なかれ自分の中に「揺れ」を持つ人物たちの中で、自らの信じるところに従うレベッカ・ナース(立石涼子)と、「保身」という一点で曇りのないパリス牧師(大鷹明良)は、徹頭徹尾ブレがない。そして頑固者だが、一本筋を通すジャイルズ・コーリー(青山達三)も。少女たち一人ひとりに至るまで、嘘偽りなく舞台上で役を生きている役者たちが、この物語に分厚い説得力を与えている。
それにしても大人たちは少女たちの嘘をなぜ信じたのか。アン・パトナム(秋本奈緒美)のように本当に悪魔を信じた者もいたかもしれないが、多くは少女たちの嘘に便乗し、私利私欲や個人的報復に利用した構図が透けてくる。裁判長のダンフォース(小野武彦)は、たとえ疑念が生じても判決を自ら覆すことは絶対にない。そしてますます後戻りができなくなる、負のスパイラル。腹立たしいのは、無批判に体制側に付くおっさんたちだ。集団心理の恐さは少女たちだけではなく、「そういうことになったのだから、もうそれでいいではないか」と、多数派に与する大人たちに当てはまるだろう。ある熱狂の渦に巻き込まれると、正常な判断ができなくなる。そうやって人間は戦争に突入していったのではなかったか。
人を貶めても自分の身を守ろうとする人間の性、ずるさ、醜さを、ミラーはいやというほどあぶり出す。だがプロクターが自分の中に見つけた「善きものの切れ端」を思うとき、不思議なことに一筋の光を感じる。わが身を「善きもの」で満たすことは難しいかもしれないが、「切れ端」ならば、ひょっとして。プロクターのように自分が生きる拠りどころを見つけられるだろうか。
(文:市川安紀)