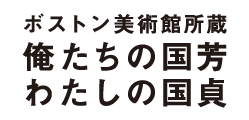EXHIBITION 学芸員による展覧会解説

歌川国芳「国芳もやう正札附現金男
弘化2(1845)年頃 大判錦絵
William Sturgis Bigelow Collection, 11.28900
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston

歌川国貞「当世三十弐相 よくうれ相」
文政4, 5(1821, 22)年頃 大判錦絵
Nellie Parney Carter Collection―Bequest of Nellie Parney Carter, 34.489
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston
二百年の時を越え、幕末の両雄 がいま再び激突 。
幕末に絶大な人気を博した浮世絵師・歌川国芳(1797-1861)と歌川国貞(1786-1864)。二人はともに歌川派を繁栄へと導いた初代歌川豊国を師としたが、兄弟子にあたる国貞が師から受け継いだ役者絵や美人画の伝統から画業を展開していったのに対して、国芳は勇猛な武者絵や趣向を凝らした戯画によって新機軸を打ち出し、浮世絵師としての地歩を固めた。町人が文化の主たる担い手となった幕末において、二人の浮世絵は流行や出版元である版元の戦略などと相関しながら多様な展開を見せてゆく。本展は江戸の「俺たち」が求めた国芳の浮世絵の世界と、江戸の「わたし」が夢見た国貞の浮世絵の世界を追体験しようとする試みである。

歌川国貞 「大当狂言ノ内 八百屋お七」 五代目岩井半四郎
文化11,12(1814,15)年 大判錦絵
William Sturgis Bigelow Collection, 11.15096
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston
役者絵と美人画の国貞
天明6(1786)年に渡船場の株を持つ材木問屋の息子として生まれた角田庄蔵は、15、16歳の頃に豊国の門下となったが、そのときすでに師を驚かすほどの技量を持っていたという。ほどなくして庄蔵は師から国の字を授かって国貞と名乗り、文化4(1807)年には早くも錦絵を出版している。
国貞は師の豊国が得意とした役者似顔の手法を受け継いで、早くから役者絵において才能を開花させた。文化9(1812)年には役者の上半身をクローズアップして描く大首絵の揃物「役者はんじもの」を、文化11、12(1814、15)年に大首絵の揃物「大当狂言ノ内」を出版する。後者は文化年間(1804-18)後半に活躍した人気役者を描いたもので、背景の豪華な
役者絵は浮世絵の最も重要な画題の一つであった。この頃江戸の歌舞伎は上方歌舞伎の成果を吸収しつつ物語としての深みを増していったが、そうしたなかでも役者はつねに歌舞伎愛好家の関心の的であった。国貞の役者絵は愛好家たちの求めに応えるものとして、歌舞伎という江戸の一大文化の一翼を担っていったのである。
国貞が師の豊国から受け継いだもう一つの画題に美人画がある。国貞は町人文化が発展してきた当時の嗜好を反映して、身近で人間的な感情にあふれた美人像を描いていった。「当世三十弐相」は、「あそびた相」や「しまひができ相」など「相」という言葉に掛けて美人の日常を生きる姿を描いた一枚絵の揃物である。そのうち「よくうれ相」では売れっ子の芸者と思われる女性が手紙を読む姿が描かれている。手紙を持つ手には力が入り、口元は手紙の一枚を咥えて固く結ばれており、見る者に手紙の内容や送り主への想像を喚起させる。また幕末には錦絵の彫りや摺りの技術が高度に発達したが、国貞による美人画の色とりどりの衣装や装身具、髪の生え際の細密な表現にはその成果が遺憾なく発揮されている。
国貞は浮世絵の主たる画題となった役者絵と美人画において一世を風靡し、天保15(1844)年には豊国を襲名、師の名声と技術を受け継いで幕末の浮世絵界を牽引していった。彼が生涯に制作した浮世絵は数万点に及ぶともいわれ、特に晩年の作品には類型化された描写が指摘されることもあるが、時代の求めに応じて柔軟に作風を展開していった国貞に対する人気は、生涯を通じて尽きることがなかった。

歌川国芳「相馬の古内裏に将門の姫君滝夜叉妖術を以て味方を集むる
弘化元(1844)年頃 大判錦絵三枚続
William Sturgis Bigelow Collection, 11.30468-70
Photograph © Museum of Fine Arts, Boston
武者絵と奇想の国芳
若くして名声を獲得した国貞とは対照的に、国芳が浮世絵師としての地歩を固めるのには年月を要した。国芳は寛政9(1797)年に染物屋の息子として生まれ15歳の頃に豊国の門下となったが、国貞とは対照的に師との関係は思わしくなかったようで、兄弟子の国直のもとに居候して仕事を手伝うなどしていた。当時の逸話として、国芳が下絵を持って版元のところを訪れたが上手くいかず、辺りを徘徊していると、知り合いの芸妓と国貞が一緒にいるところに出くわした、というのがある。国貞に対する羨ましさとともに、自らの技術が国貞に及ばないがゆえに我が身の貧窮があることを感じた国芳は、画業の研鑽にいっそう励んだという。
国芳の転機は30歳を過ぎた文政10(1827)年に訪れる。中国の豪傑たちの物語「
錦絵の定型である大判の用紙を連ねて一つの大きな画面とする手法も、国芳の得意とするところであった。三枚続きの「相馬の古内裏」は、山東京伝の『
戯画もまた国芳が才能を開花させた分野である。「
幕末浮世絵の縮図、国芳と国貞
国貞と共に仕事をした戯作者の式亭三馬は、彼を「柔和温順」な人物と評している。逸話によれば、国貞は美麗な身なりで品が良く、酒を飲んでも深くは嗜まず、晩年は質素にして財産もかなりあったという。一方の国芳は、江戸っ子の気性で礼儀など好まず、活発で侠気があり、小さなことにはこだわらない。その日に得た画料はその日に使い果たしてしまうという人物であったという。嘉永6(1853)年に狂歌師の梅屋鶴寿によって催された書画会で、畳三十畳ほどの大紙に水滸伝の登場人物である九紋龍史進の像を描いた際には、史進が踏みつける巌石を描くために自らの浴衣を脱いで墨汁に浸し、筆代わりにしたという。
二人の個性は当然その作品に反映している。だが浮世絵は絵師一人で完成するものではない。そこには大衆の需要があり、それに応じた版元の意図があり、場合によっては版元に入銀する出資者の意図が重なって、彫師や摺師の技術がある。その意味で国芳と国貞の作品は、対照的な個性の反映であると同時に、幕末の江戸文化の二つの側面であると考えることもできるであろう。
(ザ・ミュージアム 学芸員 黒田和士)