
2013/8/10(土)-10/14(月・祝)
Bunkamuraザ・ミュージアム
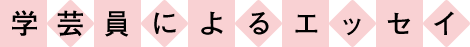
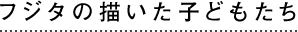
明治19年(1886年)、東京牛込(現新宿区)の武士の家系に生まれた明治の男・藤田嗣治は、単身フランスに渡り、両国を股に掛けた波乱万丈の人生を送った末、1968年フランス人レオナール・フジタとして生涯を閉じる。レオナールという名は、カトリックに入信したフジタがレオナルド・ダ・ヴィンチのフランス語名にあやかって1959年につけた洗礼名である。人はそう簡単に国籍や宗教を変えるものではない。フジタの場合、その偉大な経歴と才能にもかかわらず、従軍画家として戦争に加担したとして、日本画壇との確執によって祖国から逃れるようにフランスに赴き、晩年の生活を送るなかでの決断だった。日本で待望の回顧展が開かれたのは2006年。生誕120年後のことであった。以降、この巨星の全体像が徐々に解き明かされていくなか、本展は晩年の円熟期のフジタの世界にウエイトを置き、「子ども」「アトリエ」をキーワードに、この画家の魅力に迫るものである。
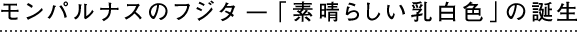
両大戦間、活気にあふれた最盛期のパリで、フジタは画壇の寵児に躍り出た。もっとも、遠い異国から来た若者がいきなりその栄光をつかんだわけではなかった。フジタがマルセイユ港に到着したのは1913年、26歳の時のこと。ボヘミアンな芸術家連中が集うモンパルナスに居を構え、ピカソやモディリアーニ、スーティン、ヴァン・ドンゲンらと知り合い、キュビスムや未来派など当時の前衛美術に触れる一方で、ひと世代前の素朴派アンリ・ルソーの作品にも大いに感化された。本展にはこれら同時代の作家の作品とともに、フジタ初期の模索的な作品も出品されている。しかしフジタは周囲の画家の模倣を避け、日本で培った技術と美意識を油彩画の表現に活かすことを考えるようになっていった。彼は日本画用の細い面相筆と墨を用いて毛髪のような細い輪郭線を、滑らかな白い下地の上に施そうとする。そして失敗を重ねながらも、タルクをカンヴァスの下地に使用することで、繊細な墨の描線と油絵具の薄塗りにより「素晴らしい乳白色」と称賛されるフジタ独自の裸婦像に辿り着いたのである。なお、このタルクは、土門拳の写真により和光堂のベビーパウダー(シッカロール)であったということが近年判明した。本展出品の作品《タピスリーと裸婦》もそんな苦労を経て生まれた作品で、乳白色の肌が美しい。このような成功の後、1929年、フジタは16年ぶりに日本に帰国し、凱旋展を開催するのであった。
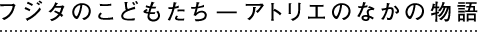
油彩だけで百数十点に及ぶ多くの戦争画を手掛けたフジタは、終戦後「画家の戦争責任」という問題に見舞われ、他の画家たちの責任をも一身に背負うようなかたちで日本画壇から戦争協力者という烙印を押され、誹謗中傷に曝されたが、GHQの戦犯リストに載ることはなかった。しかし日本の画壇に対して深い不信感を募らせたフジタが選んだ道は、フランスに戻ることであった。この時期のフジタの姿を練馬のアトリエにとらえたのが写真家の土門拳であった。戦時中からの旧知の間柄であった土門は、世界的な巨匠フジタが心を開いた数少ない日本人のひとりだったのだろう。写真家はフジタが大切にしていたあるもの着目した。1948年にフジタが造ったアトリエのマケット(模型)である。後に《私たちの家》と題されるこの理想の住居=アトリエは、彼と共に海を渡り、パリでは油彩画のモデルとなり、創作の原点ともいえるものとなった。マケットの内部をそっくりそのまま再現した油彩作品などは、その極みといえるだろう。
フジタは画業の初期から、絵画作品のなかにしばしば子どもを登場させていたが、戦時中には子どもの絵を発表することはほとんどなかった。しかしパリ画壇に復帰し、日本には二度と戻らないと決心した彼が夢中で取り組んだのは、子どもを主題とした作品だった。そしてこのマケットは、その子どもたちの情景の舞台としてしばしば登場する。ここでフジタの描く子どもたちは、東洋人とも西洋人ともつかない、大きな頭と突き出た額、吊りあがった目と小さな口をもった、ちょっと取っつきにくい子どもたちである。ときには現実のアトリエの一室の壁面全てを、彼が絵筆で生み出した子どもたちが埋め尽くすこともあったという。それら仏頂面に描かれた子どもたちは、祖国を離れざるを得なかった彼の心を紛らわす存在であったと同時に、その寂しい心持ちを映し出したものであった。フジタには子どもがいなかった。

1958年秋から、フジタはパリの街で様々な仕事に従事する子どもたちの姿を数多く描くようになる。どの作品も15㎝のかわいらしい正方形のファイバーボード(木の繊維を合成樹脂で固めたもの)に油彩で描かれ、それぞれの絵にフランス語で職業名が書き込まれているのも特徴である。その翌年の春にかけて断続的に制作されたこれら一連の作品は〈小さな職人たち〉と呼ばれるように、左官や指物師、あるいは床屋といった、手仕事に携わるいわゆる職人系の人たちが重要なテーマとなっている。さらに、古くからパリの路上でみられた馬車の御者やガラス売り、掃除夫など、実に様々な職種が描かれている。子どもたちはみな真剣に仕事に取り組んではいるものの、どことなくぎこちなくユーモアもあり、フジタの空想による子どもならではの世界が展開されている。またそこには、パリそしてフランスに対するフジタの愛が凝縮されていると同時に、「作家はアルティスト(芸術家)である前に、アルティザン(職人)でなければならない」と語ったフジタという画家の、職人仕事に対する敬意が込められているといえるだろう。なお1960年には、パリの風俗を題材にした『しがない職業と少ない稼ぎ』と題するアルベール・フルニエの小噺集に、これら〈小さな職人たち〉の連作から起こした20点ほどの小口木版の挿画を施したものが出版されている。 フジタはパリのアトリエの壁一面に200枚ものこの小品を、他の小品とともにあたかもタイルのように張り付けていた。そこからは、この作品群に対する彼の強い愛着がうかがわれると同時に、子どもに対する彼の特別な思いが感じられる。本展では連作〈小さな職人たち〉のうちポーラ美術館所蔵の95点が出品される。またこれらに先行して制作され、パリにあったフジタのアトリエのスペイン扉に取り付けられていた、同じく子どもを題材とする数々のパネル画も紹介される。
さらに本展では、画家フジタをとらえた二人の写真家の作品も紹介される。一人はすでに言及した土門拳で、近代写真のパイオニアとしてリアリズムを追求した写真家である。彼は太平洋戦争開戦の翌年から、50代半ばから62歳までおよそ8年間のフジタの姿を主にアトリエのなかにとらえている。もう一人は阿部徹雄で、フランスに永住したフジタを1952年に訪ねている。日本からの来客を好まないといわれていたフジタであったが、その10年前に戦争記録画のために広州を訪れたフジタを当時新聞社特派員として手厚く持てなした阿部との再会を喜んだ。こうして晩年のフジタの素顔をとらえた貴重な写真を残したのである。
ポーラ美術館は作品数において日本で最大級のフジタ作品を所蔵する美術館である。本展はそこから厳選した作品に、他の美術館が所蔵する油彩作品を補完的に加え、初期から晩年までのフジタの芸術を展観するのもで、「乳白色の肌」とともにフジタを語るうえで欠かせないテーマである「子ども」と「アトリエ」にスポットを当てた展覧会であり、今までとは違ったフジタ像に触れる人も多いことだろう。
Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男